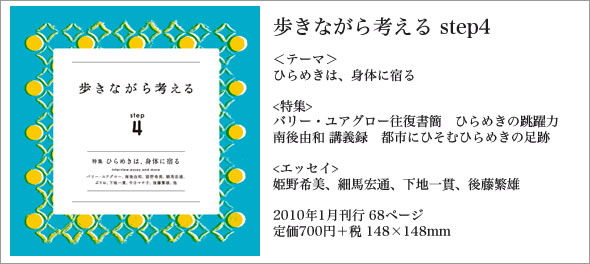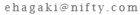The Beach : October 2010
細馬 宏通
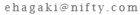
<<前月 | 翌月>>
twitter: kaerusan
つぶやく「ラジオ 沼」: radio_numa
■書いたり話したり歌ったり
モーニングツーの西島大介さんの連載『I Care Because You Do』柱に『マンガ雑誌を読む』。ぜひ雑誌でご一読を!
10/18 京都新聞夕刊「現代のことば」に「立ち上がるために必要なこと」→読む
10/9(土)13:00 かえる属@軽音楽とジャンボリー(グッゲンハイム邸)
10/24(日)音遊びの会公演@生糸会館(神戸)
11/8(月)EMCA研究会(京都大学)
11/13(土)表象文化論学会(東京大学)
11/21(日)かえるさんソロ@shiroiro-no-ie(信楽)
11/27-28 質的心理学会(茨城大学)
12/4(土)江戸東京博物館フォーラム
ライブ情報は、かえる目ホームへ。

2010.3.22「音遊びの会」にて。
「永遠野球」中継中の細馬+中尾。
撮影:松尾宇人さん
20101031
一回生の実習で豊郷へ。午前中は上着を脱ぎたくなるくらい暑かったが、午後になると急に雨。
伊藤忠兵衛屋敷、千樹寺、豊会館、豊郷小学校旧校舎と回って、帰るころには暗くなっていた。
豊郷小学校は、「けいおん!」の影響でいまや「巡礼」地と化している。音楽室の黒板はその日の「書き込み」でいっぱいになっている。おお、現実という3Dに感動する書き込みが…

 音楽室とは別に唱歌室という部屋がある。歌を唄う人があがるためのささやかな舞台がある。幕もあって、うしろには五線譜の描かれた黒板。愛らしい教室だ。
音楽室とは別に唱歌室という部屋がある。歌を唄う人があがるためのささやかな舞台がある。幕もあって、うしろには五線譜の描かれた黒板。愛らしい教室だ。
一階の講堂の舞台の横には扉がついていた。舞台に出るための扉があるのが、いいなあと思う。この学校の設計には人が人前に立つための気構えを作る構造がある。
講堂の客席には傾斜がついている。滑るまい転ぶまいとして、自然と、普段とは違う慎重な足運びになる。あたかも養老天命反転地である。講堂の二階への階段はくいっと角度がついていて、上にあがると、うわあ、と視界が開ける。いずれも、観客席に来たなという構えを産む。
見ることと見られることに向かう空気が、生まれるべくして生まれる。いい空間だな。
講堂の入口脇にはベンチがある空間があって、ここは客席とは分かたれており、ほっとひといきつくことができる。ヴォーリスの設計はいいな。
20101030
指紋、顔、歌
橋本一径『指紋論』を読むうちに妄想やまず、ノートに書き殴る。指紋が同一性のメディアなら、顔は類のメディアである。いや、そもそも一人の顔自体が類なのだ。いくつもの視点、光で構成され時空間に散らばった類。この写真はその類に入るだろうか。こんなのわたしじゃない、と思わせる写真と指紋とは似ている。「私」の「動かぬ」証拠。
また泣き虫モンスターを聴きながら、語尾が「ダーリン」に聞こえる。泣いてばっかりダーリン。わがはいはころすけダーリン。江戸の武士ダーリン。ダーリンがすきだっちゃ。
「Ten years ago」 は、「映画坂を」と聞こえる。さまざまなソラミミ。一瞬一瞬の顔が違い、その類を誰かの「顔」としてイメージするように、聴くたびに起こる聞き間違いの集積が「歌」になる。
身元を同定しようとして顔の前で困惑する人は、知らぬ間にジャコメッティに近づいている。なんて妄想を「指紋論」を読みながら抱いていた。歌を聴きながら、ヤナイハラの鼻を描きそこなうジャコメッティのように、確かだったと思った歌詞が違ってきこえる。きくたびに違ってきこえることばのどれもが正しい。鼻歌をうたおう。
結局、ノートの最後に書きつけたフレーズは「顔とは心霊である」。なーんや、これ!?
20101029
演習に院生ゼミ。ゼミ中、城さんがふと外を見て「先生、空が赤い…」というので、窓の外を見ると、これはものすごい夕焼けになりそうな予感がする。マジックアワーはあっという間に過ぎてしまうに違いない。よし、外に出る、と宣言し、四人で廊下を走り、階段を下りる。「図書館?」「いや、田んぼでしょう!」と大学の外に出て、広大な田んぼのあぜ道をずんずん行き、振り返ると、とんでもない夕暮れ。
20101028
アニメーション関連の訳出が貯まってきたので、「アニメーション文献アーカイヴズ」と名付けてまとめておくことにした。昔訳したウィンザー・マッケイ関連の文書も合わせて紹介しておきます。下記をどうぞ。
アニメーション文献アーカイヴズ on the Beach
先日、新聞週間にちなんで、読売新聞は新聞に対する意識調査を行い、その結果を報じた。
「新聞は必要」92%…読売世論調査
読売新聞社が15日から始まる第63回新聞週間を前に実施した全国世論調査(面接方式)で、情報や知識を得るために新聞は必要だと思う人は92%(昨年91%)に達した。
新聞の報道を信頼できるとの回答は87%(同85%)だった。
新聞が「必要とする情報や日常生活に役立つ情報を提供している」は88%(同88%)、「事実やいろいろな立場の意見などを公平に伝えている」は70%(同69%)、「国民の人権やプライバシーを侵さないように気を配っている」は76%(同74%)となった。
調査は9月25〜26日に実施した。
(2010年10月15日03時07分 読売新聞)
さて、この記事で紹介されているのは、あくまで調査の要約である。実際には、どのようなデータだったのだろうか。
幸い、以下のページに2010年度の調査と2009年度の調査の結果詳細があがっていた。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe6100/koumoku/20101015.htm
http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe6100/koumoku/20091015.htm
見比べてみると、興味深いことが判る。
まず、記事で要約されていたのは、数ある質問項目の一部分に過ぎなかった。
回答は四段階になっており、たとえば以下のような結果になっている。
S2 あなたは、新聞が事実やいろいろな立場の意見などを公平に伝えていると思いますか、そうは思いませんか。
答え 1.十分公平に伝えている 17 3.あまり公平に伝えていない 19
2.だいたい公平に伝えている 53 4.ほとんど公平に伝えていない 8
5.答えない 3
S4 あなたは、全体として、新聞の報道を信頼できますか、信頼できませんか。
答え 1.大いに信頼できる 22 3.あまり信頼できない 9
2.だいたい信頼できる 65 4.ほとんど信頼できない 2
5.答えない 2
「公平に伝えている」「信頼できる」と回答している人はなるほど合計するとそれぞれ「70%」「87%」だ。が、その内訳を見ると、「十分」という人は意外に少なく、「だいたい」が多数を占めている。この数値は2010年度、2009年度ともほとんど変わらない。そもそも、「あまり公平に伝えていない」「あまり信頼できない」という回答は、よほどの不信感がない限りなされないであろう。多数が「だいたい」と答えていることをもってして、「信頼できる」と結論づけてよいものか、いささか違和感が残る。
しかし、さらに気になるのは、記事には取り上げられていない次の質問だ。「次の4つ(2009年度では3つ)の点について、大きな役割を果たしていると思うメディアを、回答リストの中から、それぞれ3つまであげて下さい。」という問いへの回答結果には、2009年度と2010年度で見過ごせない差異が見られるのである。以下、抜粋して表にしてみよう。
世の中の出来事を早く伝えるのに大きな役割を果たしているメディア(%)
| メディア | 年度 | 2009 | 2010 |
| 一般の新聞 | 57 | 49 |
| NHKTV | 60 | 66 |
| 民法TV | 63 | 55 |
| インターネット | 32 | 41 |
「ニュースの背景や問題点を掘り下げて解説する」のに大きな役割を果たしているメディア(%)
| メディア | 年度 | 2009 | 2010 |
| 一般の新聞 | 61 | 52 |
| NHKTV | 50 | 52 |
| 民法TV | 55 | 51 |
| インターネット | 11 | 11 |
「社会の懸案や課題に対する解決策を提案する」のに大きな役割を果たしているメディア(%)
| メディア | 年度 | 2009 | 2010 |
| 一般の新聞 | 59 | 49 |
| NHKTV | 45 | 38 |
| 民法TV | 51 | 46 |
| インターネット | 8 | 8 |
3つの質問のいずれにおいても、新聞への評価が8-10%下がっていることが判る。しかも、それは単に、インターネットの影響によるものとは限らない。「速報性」に関しては、インターネットの評価の上昇と新聞の低下とがちょうど符丁するが、「背景や問題点の掘り下げ」「解決策の提案」に関しては、インターネットが特に上昇しているわけではない。むしろ、新聞自体の落ち込みがはっきりしているのである。
2009年でも2010年でも、新聞に対しては「だいたい」の信頼が寄せられている。そして多くの人が「必要」だと思っている。しかし「速報性」「背景や問題点の掘り下げ」「解決策の提案」のいずれの点においても、評価は明らかに低下している。調査結果は、人々の新聞への変わらぬ高評価を示しているというよりも、むしろ危険な低下の兆候を示している。このことに、新聞関係者は目をつぶるべきではないだろう。
20101027
ゼミ、講義、ゼミ。ゼミ生に自分でELANをいじりながら解説をしてもらう。
アニメーション史の講義はマッケイの話。『恐竜ガーティー』を流しながら、口上を日本語で再現してみた。スクリーンの右横でひょいとリンゴを投げる仕草をしたら、ガーティーが画面の中でそれをキャッチするのを見て学生が「わあ!」と声をあげたのでびっくりした。実はこういう見世物は現代に通用しないんじゃないかと内心見くびっていたのだが、ちゃんと通じるんだな。マッケイの描写力がそれだけすごかった、ということなだろう。
20101026
講義を終えて、たんぽぽの家に。佐久間さん、本間さん、志賀さん、岩橋さん、ケアする人のことを考える会議。帰りに志賀さんと近鉄特急であれこれ話。じつは近鉄特急には初めて乗った。丹波橋や高の原を使うことが多いので、特急は無縁の乗り物と思っていたが、意外に快適である。
20101025
ディズニー・スタジオのアニメーター、シェイマス・カルヘインの“animation”を一部訳してみた。ゲイブラーと読み合わせるとおもしろい。筆の勢いのとまらなさが伝わってくる話。
http://12kai.com/culhane_flow.html
ページに思い馳せる夜に、モーニング・ツー無料公開に気づく。平たくなったページで読む不思議な感触。38号、西島さんの「I Care Because You Do」、柱とともにどうぞ。無料公開のURLはこちら。 http://morningmanga.com/news/991
リンデン『つぎはぎだらけの脳と心』おもしろかった。特に(仮説段階が多いとはいえ)睡眠の章は妄想をたくましくさせられた。たとえば、一般に恐怖や不安、敵意の情動は強い記憶をもたらすと言われているが、「眠っている時には、何かの感情を引き起こすような外からの刺激はないのだが、記憶の統合、定着を促すために、恐怖や不安、敵意の感情を無理矢理に引き起こしている」とリンデンは考える。
それで思い出したが、ぼのぼのの「こわい考えになってしまう」という表現は含蓄が深いなあ。「こわい」という情動と、「考え」という思考とが結びついている。そしてそれは記憶の強さに関わっている。
月曜は実習三コマと講義。一回生向けの実習で、地蔵盆と江州音頭について文献調査してもらっているのだが、数年前に中川加奈子さんという方がソシオロジに書かれた論文を学生が見つけてきた。これが、単に伝統遵守でも観光重視でもなく、一つの「音頭」の名の下に実はさまざまなバリエーションや共同体間の差を持った現場の人々が、伝統をいかに捉え直していくかというプロセスを論じていておもしろかった。
中川加奈子「地域文化の再編成における媒介者の役割--滋賀県豊郷町の江州音頭を事例として 」
20101024
音遊びの会公演『音の糸』@旧生糸検査所
朝早く、彦根から神戸へ。今日は音遊びの会の公演『音の糸』。会場に着くと、すでに前日からの仕込みで、あちこちに糸をテーマにしたインスタレーションが設置されている。受付向かいに縦張られた糸電話、舞台バックには松尾宇人さんによる巨大な糸クラゲ(?)。すでにして、(文字通り)一本筋の通った環境ができている。「むむ、ここは何かが違う場所ではないか?」と思わず感知させる環境が整うと、舞台が(文字通り)ハレの舞台になる。
リハを終えて、昼休み、近くの公園に行くと、「防災ショー」なるものをやっており、各国の屋台でカレーや軽食を売っていた。何皿か買って昼飯に。
午後は本番。最初にメンバーが糸電話を持って話し合うの場。会場のお客さんの中にも話す人が現れる。そのあと、ぼくとしおりちゃんとが二人で糸電話で話す。
糸電話というのは奇妙なメディアだ。話すためには離れなければならない。
しおりちゃんに「もしもしー」と呼びかけると、最初しおりちゃんは、はーい、といって、こちらに近づいてきて、糸は緩んでしまった。電話口でしゃべるぼくの声が大きすぎて、彼女に直に声が聞こえてしまい、彼女もまた、大きな声でぼくに答えていた。糸電話を手にしてはいるものの、やっていることは遠くで呼びかけ合っているのと同じだったのである。声が大きいから、観客には何を言っているかよくわかるけれど、これは糸電話の会話ではない。
それで、声の音量を落としていき、糸電話でないと聞こえないようにする。すると、しおりちゃんは、こちらに歩み寄るかわりに、糸電話に耳をくっつける。これで糸電話らしくなった。そして、糸電話の会話は、観客には聞こえない、ひそやかで秘密めいた音量になる。
途中、「何かしゃべってくださーい」と言ってから、しおりちゃんがしゃべろうとすると、「きこえますかー」とこちらからしゃべる、と言う奇妙なこともあえてやってみた。二人で糸電話から同時にしゃべりあう、という、電話の機能からはずれたことをやってみたらどんな絵になるかなと思ったから。でも、しおりちゃんは、ぼくが「きこえますかー」というたびに、口に当てようとしていたコップをあわてて耳に当て直す。ごめんごめん。全くしおりちゃんの方が正しい。
途中、二人ほど客席の子供さんが舞台に(といっても段差はない)出てきて、わたしもわたしもって感じでしおりちゃんの糸電話を手に取り始めた。思わず自分でやってみたくなったんだろうなあ。やってみたいと思われるような所作だった点は成功だったかも。
ビッグ・バンド、アリ×藤本さんと、いまや音遊びの会の定番とも言える盤石の演目に加えて、今回は貝つぶさんが参加。大生くん、つばさくん、貝つぶさんという、かなり大胆な?トリオによる弱音演奏では、大生くんが貝つぶさんの音をシミュレートしていておもしろい演奏になっていた。加藤さん、平木さん、永井くんのトリオ。永井くんのシンセ、思い切りのよい音の使い方でいいなあ。ふつう、シンセの演奏はかなり流行に左右されて、この音色は何年代っぽいとかこの音色にはこのフレーズという縛りがわりときつい楽器だと思うのだが、永井くんの演奏にはそういう流行に対する気配りよりも、ある音色をいつ鳴らしたいかがはっきり聞こえる。坂口ファミリーの演奏はさすがファミリーの一体感。おとうさんがすごい派手なかつらをつけて出てきて驚いた。
この日びっくりしたのは、鎌田さん、しおりちゃん、ゆかちゃん、ゆりちゃんのダンスで、とりわけ、リハではリコーダーを吹きながら逡巡していたゆりちゃんが、本番でしおりちゃんの手をとって踊るところは、泣かせる展開だった。あとでゆうたくんがゆりちゃんに「あれ、よかった」と声をかけていた。ゆうたくん大人になったなあ。
お母さんバンドはゴムと鈴。お母さんバンドは音遊びの会の定番なのだが、なんだか巧くなってる!ニュー新体操の感あり。
第二部は管楽器アンサンブルでにぎやかに始まる。短いゆうごうパレード(いつもは客席までどんどん歩くのだが、演目化するとなぜか舞台にとどまるゆうごうくん)。あやちゃんヘッドで藤本さんのお母さんがチェロを弾くという珍しいアンサンブル。藤本さんは持続音でゆっくりと他の演奏者の様子を見ていて、すでに即興演奏者の風格。まさはるくんのボーカル炸裂するパンクバンド。
ぼくは、ともきくんとの初顔合わせ。初めてのセッションなので、あまり難しいことはせずに、しおりちゃん持参のニワトリ(押して離すと哀れっぽい声を出す)と、でんでん太鼓を掲げてご機嫌をうかがう。でんでん太鼓を掲げる位置を変えると、当然ともきくんの姿勢が変わる。叩くか叩かないかも違ってくる。ともきくんの注意がどこで絞られて、どこで緩むか、それがどんな緊張につながるかが表れればよい、という演奏。あとでおとうさんにうかがったら「今日はめずらしく長く続きました」とのこと。普段はもっと早く飽きて退場、となるそうだ。
ゆり、ゆうた、みやけをトリオ。指揮と管楽器の一対一ペアが6組という「指揮と管」。最後には全員が打楽器を持って散らばり、あいなちゃんの自転車が途中から場内を爆走するのを追いかける、というもの。場内二周して息があがった。日頃走ってないからなあ。
ちょっと休憩をはさんでからは、弱音→爆音ビッグバンド。踊りは鎌田さんから永井くんへ。永井くん、踊りのレパートリー増えてるやん。今日はゆりちゃんの反応がいいなー。
終演後はゆうだいくん×しおりちゃんで投げ銭ライブ。
今回は広大かつ複雑なフロアで、スタッフの方々も大変だったのではないかと思う。とこさんご夫婦をはじめ、強力なスタッフがいてこその自由度。
打ち上げは近くの居酒屋で。例によって大人もこどもも大人数でわいわいと。アダルト・アンド・チルドレン。
神戸から彦根は旅。今日は日帰りゆえ、関西ぐるっと1dayパスを使う。これだと往復で1000円くらい安くなるのである。夜中に帰宅。
20101023
久しぶりに何も予定のない日。リンデン『つぎはぎだらけの脳と心』(インターシフト)を読む。何がおもしろいかをおさえる勘所がよい。脳科学に関してはCognitive Neuroscienceの教科書を読んで勉強しているのだが、この本で脳科学を勉強する「情動」が補強された感じだ。
沼 444: 川景色の深き思い出

@miyaco__さんからのコメントを受けて。コードとメロディはより深き妄想にたどりつくの巻。
この放送をダウンロードする
ページネーション・マニュアル
鈴木一誌さんによる「[新版]ページネーションのための基本マニュアル 」
「ケイ線を、0.25ptの極細にこだわるのは、その細さが刷版や印刷精度の目安になるからだ。いわば、ページの品質を見守る指標としての罫である。」(鈴木一誌『ページネーションのための基本マニュアル』より)
『ページネーションマニュアル』のレイアウトを見ながら、PDFにおけるフッタの役割は、親指で感じる厚さ感覚をページという二次元上に展開するためのものなのかもしれぬ、と思う。触覚を、フッタやヘッダという目に見えるできごとで代替することはできるだろうか。
20101022
沼 443: 「わたしの川景色」

コード・シンコー・ミュージック計画、「川景色」(松任谷由実:作詞・作曲)。
この放送をダウンロードする
質問項目を並べ替える方法
今年は京大の浦田悠さんに質問紙実習の講師で来ていただいている。浦田さんは性格心理学を学んでからナラティヴへと進まれているので、ぼくのように大学を出てから独学で学んでいる人間よりもずっと質問紙のことはご存じである。いろいろ勉強している。たとえば。質問紙票を回収したあとの処分方法について。「昔は質問紙を焼くために焼き芋パーティーをやってましたね」。うわあ。
あるいは、作った質問項目を入れ替えるにはどうするべきか。「あ、けっこう手作業だったりします」。あ、そうなんだ。単に「ランダム」にするだけでなく、似た質問が並ばないように離したりするには、手作業のほうがよいこともあるのだそうだ。
とはいえ、100項目近い質問項目を手作業で切り貼りして並べ替えるのもたいへんなので、Excelで簡単にできないかなと、実習中に二人でうーんと考えて思いついたのが、乱数関数を使う方法。
まず、質問項目をExcelの列Bに貼る。次に、各行の右側(列A)に「=RAND()」を入れる。RAND関数はそのつど0から1までの乱数を発生させてくれる。その大小の配分はおおよそランダムといっていいだろう。最後に、全部の行を列Aをキーに並べ替える。とりあえず質問項目をざっと並べ替えるにはこれで十分だろう。そのあと、同じ質問が並びすぎてないか(いわば、「ダマ」になっていないか)チェックするとよい。
20101021
生データを読み上げると判ること
統計学基礎の講義で、ニュースソースに関する簡単な調査をしてみる。140人の受講生にチェック式の質問紙に答えてもらい回収する。一枚一枚の結果をその場で読み上げる。読み上げには(途中いろいろコメントを入れたせいもあるけれど)30分弱かかった。退屈な作業に聞こえるかもしれないが、意外におもしろく、途中、何度も笑いが起こった。一枚一枚のデータには、取り合わせの妙がある。たとえば、「ニュースはあまり見ない」という人のほとんどは、なぜか「YouTube」の利用だけに○が入っている。逆に、mixi, twitter, facebook,YouTubeを全部やってる人ってどんだけモニタ見てるねん。ラジオだけを選んだ人の番組名を見ると「NHK AM」とある。シブい……といった情報は、残念ながら単純集計では落ちるのである。図らずも生データを見ることで、単純集計という縮約から漏れてしまうのがどんなできごとかを実感する30分となった。
集計後、一応集計結果を挙手でチェックしてみたら、140人でけっこうばらつきがある。100に及ぶものになると、誤差が7,8になる。誤差の多くは左右対称ではなく、下方に集まっている。どうやら聞き逃しや寝落ち?が原因らしい。
当然ながらカウントが多いほど集計誤差は大きくなる。こうした体験は今後、偏差の議論をするときに思い出してもらうことになるだろう。
大学生のニュースソースと情報環境
ちなみに、質問項目と結果は以下の通り。回答者は滋賀県立大学の統計学基礎受講生で、多くは1回生。ぼくの感覚では、Twitterよりmixiのほうがかなり多いのが意外でした。あと、あいかわらずテレビは根強い(遠距離通学者が多いせいか、「めざましテレビ」や「朝ズバ」をあげる学生が目立った)のはともかくとして、新聞はみごとに少ないなあ、ということと、ケータイがニュースソースとして今や半数の地位を占めていることのも気になった(主にYahoo!ニュースやエキサイトが多かった)。先週、新聞に掲載された世論調査のコピーをとってその調査方法をチェックしなさい、という課題を出したら一部から「えー」という声が起こったのだが、こういうことだったのね。
1.次のうち、あなたがニュースを知るためにほぼ毎日見るものを選んで下さい(複数選択可)。
( ) 新聞 (主な新聞名: )
( ) TV (主な番組名: )
( ) ラジオ (主な番組名: )
( ) PC (主なサイト名: )
( ) 携帯電話 (主なサイト名: )
( ) その他 (主な方法: )
( ) ニュースはあまり見ない
2.次のうち、あなたが利用しているもの、行っているものを選んで下さい(複数選択可)。
( ) mixi
( ) Twitter
( ) Facebook
( ) myspace
( ) YouTube
( ) ブログ、web日記の執筆
結果:
| ニュースを見るメディア | 人数 | % |
| 新聞 | 27 | 19.3 |
| テレビ | 101 | 72.1 |
| ラジオ | 7 | 5.0 |
| PC | 34 | 24.3 |
| ケータイ | 70 | 50.0 |
| その他 | 1 | 0.7 |
| あまり見ない | 17 | 12.1 |
| 利用しているメディア | 人数 | % |
| mixi | 72 | 51.4 |
| twitter | 26 | 18.6 |
| facebook | 5 | 3.6 |
| myspace | 2 | 1.4 |
| youtube | 106 | 75.7 |
| その他 | 41 | 29.3 |
20101020
リフレインが叫んでいる
『流行歌の誕生』を読んで考える。『復活』劇で「カチューシャの唄」が二度歌われたのに観客が感涙したことと、音楽において同じメロディが間をおいて現れる構造、たとえばABAという構造に聞き手がぐっとくることとは、同じではないか。
リフレインは、物語で引き起こされた情動を生活の中で起こすための装置であり、人は歌うことで、あのときの情動をなぞろうとするのではないか。
ゼミ、会議、講義、ゼミゼミ。ゼミではたいてい映像分析をやるので、一日に三本ゼミをやると目がしょぼしょぼになる。
帰ってからオールフリーを飲み復活。最近、家ではノンアルコール。レンタル屋でまたDVDを借りてしまった。久しぶりに『隠し砦の三悪人』を見る。ひたすら石ころにまみれ土にまろぶ。泥だらけの人が累々と横たわる。この頃、人はいかに地面に近かったか。
20101019
会議。臨川書店の石川さん来訪。臨川書店というと、1980年代に京都で勉強した人間には、歴史本に強い書店というイメージなのだが、最近は視覚文化の出版にも力を入れておられる。そういえば、私の書棚にも「アニメーションの映像論」をはじめ、何冊かあった。出版のお話をいただいたが、例によって「ひとつ長い目で・・・」とお話する。
データ分析。
夜、先日借りてきた『銀座旋風児』。
20101018
朝から講義と実習を四コマ。いつもは前後期に振り分ける講義を今年は後期に固めたので、やたらと忙しい。頭をさっと切り替える訓練だと思うことにする。
20101017
ラジオ収録
KBS京都へ。『大友良英のJAMJAMラジオ』収録。せっかくなので、大友さんとレコード室に。あれもこれもかけたくなってしまう。結局、ユーミンを一曲選んだ。大友さんとまとまった話をするのはけっこう久しぶり。音楽の話や研究の話など、あっという間に二回分。持参したギターを弾きながらちょっと歌った。11月放送予定。
phour "with piano"
元立誠小学校へ。phour二日目。
長谷川健一+石橋英子。この二人の組み合わせは生では初めて聞いたが、石橋さんのピアノの入れ方が素晴らしい。いわゆるポップスのコード打ちやアルペジオとは異なるフレージングで、ざあっと音色を変えながら、ギターと見事な織物を織っていく。講堂ということもあって、ハセケンの歌は、どこか女学院のチャペルで聞いているように、清々しく響く。新しいゴスペル。
図書館。六人のアンサンブルながら、ボーカルをくっきり聞かせる心憎いアレンジとボリュームコントロール。この日はフルートが入っていっそう室内楽感が増していた。アルバム未収録の曲がいくつかあったが、どれもぐっと来るメロディとコードを持つ佳曲だった。そして足立さんの歌詞はまたしても思いがけないところから胸を突く。次のアルバムが待ち遠しい。それにしても、生でこんなに緻密なアンサンブルが聞けるとはなあ。
最後は大友さんのピアノを使ったフィードバック・ソロ。ここまでの流れとは全く異なる、手加減なしの轟音。ピアノから鳴る音、というと、つい、中のワイヤが鳴る音を想像してしまう。が、ここではそれ以上に、ピアノのフルボディが鳴っている。蓋の開いたピアノがいかにモンスターだったかを思い出す。
終演後、お客さんもいなくなってから、どんなピアノかなと思って壇上にあがってみる。なんと蓋と鍵盤前の板がなかった。80年物のピアノだという。キータッチは柔らかい。宮崎さん、みんとりさんとコードを弾き合ってきゃあきゃあ言ったあげく、「どんなーうんめいがー、愛をとおざけたのー」と歌い上げたら、FMN石橋さんがあわてて、「隣は民家なのよ!」。もう夜の9時を回っていたのだった。大人になってから小学校で怒られるのは、なぜかうれしい。
打ち上げに混ぜてもらう。楽しい宴。
20101016
元立誠小学校でphour "with piano"。講堂にぎっしり400人が体育座り。腰に来そうなので、いちばん後ろにぽつんとあった長椅子に腰掛けていると、細川周平さんがやってきて隣にちょんと座られる。幕間によもやま話。
トクマルシューゴさんとは、以前、友人の結婚パーティーでご一緒したことがあるが、いまや「トップランナー」に出演して、飛ぶ鳥を落とす勢い。バンドでの演奏は初めて見たが、ベース音を抑えて中音域の音色変化でグルーヴを産み出していくという、独特のスタイル。ものすごく緻密なギターワークなのだが、それが前に出るだけでなく、バンドの音色として混ぜ込まれている。体育座りしているのがもったいないリズム。
とびらの「と」
浜田真理子さんを生できくのは久しぶり。
『恋ごころ』。こと、ことば、ひと。最初の曲から、「こ」と「と」の音がすばらしい。「と」の音を発する舌は、上口蓋を一瞬ふさぎ、さっと開け放つ。浜田さんの「と」はとびらのようだ。はじまるために終わる音。跡、糸、うとうと、干支、音。里、使徒、スト、瀬戸、外。鳩と人。ふと、どこかへと。ほとほと。「と」で終わる「こと」。
この日驚いたのは、三上寛によるマイケル・ジョーダンが出てくる歌。新幹線に乗って窓の外を見ていると、雲間からマイケル・ジョーダンが現れる。見たいものを見せてくれるマイケル・ジョーダンはすごい、という歌なのだが、この、妄想のありかを手づかみするような大胆な詞を、端正な発音でしたためる浜田さんの歌声もすごい。まるで、ぬか漬けがまるまる一本、優雅な所作ですいと差し出されたようなのだ。
20101015
ゼミに実習。データ分析。レンタル屋にDVDを返しに行ったら、日活ものが充実していることに気づいた。二本借りて帰る。今日は『東京の暴れん坊』。セーヌの川がどうしたい!
20101014
ゼミに講義。アイワークスの伝記、「The hand behind the mouse」。データ分析。
20101013
ゼミと講義。グループホームにちょっと寄って吉村さんからデータを受けとる。データ整理と分析。
20101012
講義と長い会議。くたびれたので外食。
夜中に『メアリー・ポピンズ』。遠い昔に見たときにはモノクロだった記憶がある。ということはテレビだっただろうか。あれはいつのことだったか。カラーのDVDで見ると全く別の映画に見える。どこか、カレル・ゼマンの質感に近いところもある。実写とアニメーションを使っているからというだけでなく、異なるスケールのものをつなぎ合わせるその方法が。
何十年も忘れていたが、中学生の頃、テレビ英語会話で『メアリー・ポピンズ』の場面がいくつか使われていて、それをカセットテープに吹き込んだこともあった。最初に買ったペーパーバックは『老人と海』で、二番目に買ったのは『メアリー・ポピンズ』だった。
20101011
祭日なれど朝から4コマ。夕焼けの中を花を探して名前を調べる実習。
サイレント期の伴奏音楽文献の一つ、Lang et al.「Musical accompaniment of moving pictures」を読む。特に曲間でのハーモニーの工夫や即興の項、オルガニストのためのノウハウが興味深い。
久しぶりにレンタルビデオ屋へ。夜中に「E.T.」。明日のコミュニケーション論の話を考える。異星人とのコンタクトはコミュニケーションの基本。
20101010
朝、グッゲンハイムの本棚にある漫画をふと手に取ってしまい、気がついたら「奇子」を一気読みしていた。塩屋から彦根までは2時間半。明日は祭日なれど出講日。講義と実習の準備。
20101009
ゲイブラー『創造の狂気』補完計画
この数日、ゲイブラーのディズニー評伝を訳出してきましたが、これらを年代順にまとめ直しました。ディズニー・ファンの方はもちろんのこと、『創造の狂気』の読者の方、その他、アニメーションを創るということに関心を寄せておられる方にお読みいただければ幸いです。以下のリンクをどうぞ。
ゲイブラー『創造の狂気』補完計画について
(1)1920年代部分の補完計画
(2)1930年代の補完計画(a)
(3)1930年代の補完計画(b)
軽音楽とジャンボリー3
彦根から塩屋へ。車内で京都新聞の原稿。
そぼふる雨。
popoとかえる属とで一緒にやる曲をリハ。合間に譜面を書く。
一杯だけモヒートを飲んだが、この一ヶ月ほど普段はノンアルコールビールにしていることもあり、けっこう酔っぱらう。二階でのpopo, 水谷トリオの演奏を聴きながら、買ったばかりのSweet Dreamsを読みつつ外を眺めて、ここはニューメキシコ砂漠だという感覚に急に襲われ、向かいの家のシュロの木をじいっと眺めていると、とがった葉がユッカの木に見えだし、崖の下は砂漠のような気がしてくる。10月の妄想。山地さんがいろんなものを叩きながら二階から一階へと下りていく。
core of bellsの本番中、「なにこのバンド、男くさいわね!」といちゃもんをつけてから一曲歌うという奇妙な役回りで出演。なにしろ酔っぱらってるし、いつもは出さないペルソナを出してしまったおかげで調子がおかしくなり、かえる属では、弾いているコードが何度もわからなくなる。どしろうとがただ弾き損ねていただけなのだが、あとで泊の武内さんから「あれ、ネタでしょう!」と言われたので、よかったことにしよう。ちなみに宇波くんは端で見ていて「これはひどい!」と心底思ったという。
ペドグ、Brazil、楽しい宴。Ettの演奏にはしんとする。
外で梅田哲也くんが「遠隔操作」するという、わかったようなわからないような出し物。江崎さんがあらかじめ梅田くんから言付けされたインストラクションを読み上げて、庭をシャベルで掘り始める。そこにはコードらしきものが遠くから引かれていて、そのコードは地中へと続いている。コードの先には何があるのか。遠くからうっすら聞こえる合唱。何の演出だろう。ときどき堀り手を交替するべし、とのことで、ぼくもシャベルで掘る。やはり合唱が鳴っている。誰の声なのか。core of bells の池田君も掘る。心なしか合唱が大きくなっていくような気がする。やがて、手応えがあったのか、江崎さんが何か形のあるものを掘り出す。そして出てきたのは、スピーカー。そのスピーカーからいまやはっきりと、合唱が鳴っている。そして梅田くんの声。それは、名古屋からリアルタイムで中継されていた演奏だった。難しい仕掛けは何もない。ないのに、してやられた気がした。
PAAPの猛烈な演奏、久しぶりに香取さんの狂気を見た気がする。そして、泊の、見事にコントロールされた、有機的なアンサンブル。山の歌の三拍子は、何のリズムをシミュレートしているんだろう。何の拍子かわからないが、それは確実に山の空気をはらんでいる。
終演後もにゃーにゃーと話に興じるうちに日付が変わる。塩屋泊。
20101008
ゲイブラーの書く初期アニメーション史
そもそも、わたしがゲイブラー『創造の狂気』(ダイヤモンド社)の文章をおせっかいにも補完しようと思ったそもそものきっかけは次の部分を読んだときだった。第二章、ウォルト・ディズニーがアニメーションを志し始めた頃の時代背景を、原文に沿って訳出しておこう。
1920年、彼がガレージで実験に耽り始めた頃、アニメーションの歴史はまだ20年も経っておらず、さほど進化していたわけではなかった。一つには絵を動かすというアイディア自体があまりにも斬新で、観客を楽しませるには、動きさえあれば他にはほとんど必要なかったからである。
初期のアニメーター、たとえばフランスのエミル・コールやイギリス生まれのJ.スチュアート・ブラックトンは、ヴォードビルの伝統芸である「早描き(lightning sketch)」のスタイルを真似ていた。これは、イーゼルの前に立ち、講釈をしながら、みるみる絵を描き進めていき、語りの内容に沿って絵の形を変えてしまうという芸だった。映画の本性もまた、静止したイメージの列なりから連続したアクションを産み出すというものだったから、早描きに秀でているアニメーションのパイオニアたちにとっては、有利だった。彼らの映画ではしばしば、始めに絵を描く画家の手をわざと映しておき、そこから魔術のように絵自体を動かす。このような技法を用いたギミックによって、観客の注意を惹きつけ、アニメーションを観るその目をくらましたのだった。基本的に、これら初期のアニメーションがもたらしたのは、動く、という興奮に過ぎなかった。
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 2, p52, 細馬試訳)
ゲイブラーのこの記述は、初期のアニメーションをいささか過小評価しているきらいがあるものの、「早描き芸」とアニメーションとの関係を指摘しているところは、とてもおもしろい。が、この部分が、邦訳ではこうなっているのである。
動画の製作は二〇年ほど前に始まり、1920年当時にはまだほとんど進化していなかった。初期のアニメーターはフランスのエミル・コールやイギリスのジェームズ・スチュアート・ブラックトンのように、舞台で観客の注文に応じてイーゼルに向かう早描き芸人を真似て、キャラクターの動きをコマ描きしていき、それをカメラに収めた。つまり当時のアニメーターは腕の立つ早描き芸人にすぎず、フィルムにはよく、絵を描くアニメーターの手が映っていた。(『創造の狂気』p.62)
わたしは、以上のような訳文ならぬ要約と改変に、フンガイしてしまったのである。原文にはいくらなんでも「アニメーターは腕の立つ早描き芸人にすぎず」などという否定的な表現はないし、これでは絵を描く手が映っていた理由がわからない。「キャラクターの動きをコマ描きしていき」という表現は原文にはない。「コマ描き」とはどういう意味だろう? ちなみに「早描き」芸とは、一つの絵にどんどん線を描き加えて観客の予想をくつがえす絵にしていく芸で、ブラックトンやエミル・コールもこの方法を応用している。「舞台で注文に応じて」という表現も原文にはない。「早描き」芸では、あらかじめ用意した講釈を用いることがほとんどだった。(詳しくはD. Crafton「Before Mickey」を参照のこと)。
原文に沿って素直に訳せばこんな奇妙な訳にはならないはずだ。他人の文章を要約しようとして、自前の思い込みを入れてツギハギした結果、原文を別物にしてしまう。翻訳は魔物である。
ちなみに、このあと原文には、ウィンザー・マッケイを経てセル・アニメーションに至る1920年までのアニメーション小史のまとまった記述があるが、これは邦訳からは省かれている。
『白雪姫』に集まった若手アニメーターたち(1)
例によって、ゲイブラーのディズニー評伝の第六章から邦訳で訳出されていない部分を。ベテラン勢の紹介に続いて、以下の文章がある。
ヴェテラン勢と契約するだけでなかった。人材をすぐにでも必要としていたため、ウォルトは推薦を受けた若手や、我慢しきれずくたびれ果てた若手を育て上げるべく集め始めた。彼らはやがてディズニースタイルの主要なメンバーとなるだけでなく、スタジオを支えることになった。ハム・ラスケが言うように、ウォルトがニューヨークからこうしたアニメーターたちを加入させると、「その現象は幸福の手紙のように広がって、それぞれのアニメーターが10人のアシスタントと何ダースもの中間画家を引っ張ってきたのです」。
こんな風にやってきた一人が、ドイツ生まれのウォルフガング・リーザーマン、通称「ウーリー」である。彼は瓶詰め水の工場を経営する家に七人兄弟の末っ子として生まれた。父親は「政情不安」ゆえにカンザス・シティに逃れてきたが、娘が結核にかかると、気候のいいカリフォルニアはシエラ・マドレへと移住した。短期大学で美術を少し勉強してから、リーザーマンはダグラス航空会社で働くようになった。背が高く、大柄でハンサムなリンドバーグを夢見て飛行家になろうとしたが、その夢をあきらめて突如シュイナードの美術学校に通うようになった。そこでの指導員の一人がフィル・ダイクで、ドン・グラハムを手伝っているところだった。ダイクは当時24歳だったリーザーマンに、ディズニーで働いてみないかと持ちかけた。1933年6月にディズニー社に入ると彼の働きぶりは評判になった。ウォルトの言によれば「辛い仕事にも微笑んでいる…彼は時間のかかることもやり遂げる力がある」。
エリック・ラーソンはユタ州生まれで親はデンマーク移民だった。ラーソンはユタ大学でジャーナリズムを勉強していたが、仲間の学生といたずらのつもりでカレッジ・ユーモア・マガジンに忍び込んでいるときに、一人が天窓から落ちて死んでしまった。それをきっかけに、ロサンジェルスに職を求めて、イヤーブックをデザインする会社に入り、6年後にはアートディレクタになっていた。1933年に結婚し、収入を増やす必要がでてきたので、KHJラジオステーションのために脚本を書いていたが、どうすればもっとうまく書けるか相談すべく、元経営者のディック・クリードンに会いに行った。クリードンはすでにディズニーで働いていたが、ラーソンにディズニーで働いてみるよう薦めてみた。ちょうどウォルトが『白雪姫』のためにスタッフを増員している時期だった。ラーソンは当時28歳だったが、しぶしぶアニメーターをやってみて、二日後にはアシスタントとして起用された。
ウォード・キンボールもリクルート組の一人で、1934年四月にディズニー・スタジオに来たときはまだ20歳だった。リーザーマンやラーソンはのんきで御しやすい人物だったが、キンボールは短気な因習破壊者で、実際、丸くて狂ったようにくしゃくしゃになる顔、突き出た前頭、ふくらんだほっぺた、にやりと笑う大口(訳注:彼はのちに『不思議な国のアリス』のチェシャ猫を描くことになる)は、まさに彼の性格を表していた。キンボールの父親は巡回セールスマンで、家族は街から街へと旅をした。キンボールによれば行った学校は22にのぼり、十代のときにカリフォルニアに落ち着いた。子供時代には未亡人となった祖母のいるミネアポリスにやられたが、そこで絵を描くことを覚え、家族が西側に移ると、通信教育で美術を勉強し、やがてサンタ・バーバラの美術学校に通うようになった。このときに彼の将来の道が開けた。地元の劇場で、ミッキーマウス・クラブ・バンドが演奏に来たとき、彼は『三匹の子ぶた』を観た。「完全にノックアウトされた!」。先生は彼にスタジオで働くよう勧め、面接のために母親に来るまで送ってもらった。彼は自分の作画集を持っていったのだが、そんなものを持って来た者はいままでいなかった。もう行っていいよと言われたときには、正直に、帰りの車の金がないんですと答えた。受付嬢がそれをウォルトにもらして、キンボールは翌週から働くことになった。
アシスタントからアニメーターへと昇格する頃には、キンボールは掟破りの男として有名になっていた。「けして予想通りには動かなかった」と同僚のフランク・トーマスとオリー・ジョンストンは書いている。シャープスティーンによれば、それが理由で「個人プレーで誰とも協調する必要がない場所があるとウォルトはキンボールを使った」。
『白雪姫』に集まった若手アニメーターたち(2)
キンボールが働き始めた翌月、ミルト・カールがやって来た。当時、彼は25際で北カリフォルニアに済んでいたが、旧友のハム・ラスケの薦めに従ってスタジオにやってきたのだった。カールは辛い子供時代を送った人だった。ドイツ移民の父親は家族を捨て、母親は再婚したものの、カールは義父との折り合いが悪く金を稼ぐために学校を辞めた。ウォルト同様、彼もまた美術に救いを求めたのだった。16歳のとき、サンフランシスコのベイエリアにある新聞社の美術部門に入り、以後あちこちの新聞社を転々としたが、そのひとつでラスケとあい、その後、ウェスト・コースト劇場チェーンの広告を描き、フリーになったところに、ラスケの薦めがあり、雇われたのだった。
フランク・トーマスは子供時代に絵を描くことに取り憑かれたが、それは孤独で友だちがいなかったからで、その後、カリフォルニアのフレスノにある高校でも、そして大学でも絵のことを追求し続けた。彼の父親はフレスノの州立カレッジで学長をしていたので、最初はそこに入学し、のちにはスタンフォードに進んだ。学校を卒業すると、眼鏡をかけて教授然とした風貌のトーマスは、ロサンジェルスに行き、シュイナードの学生となった。スタンフォード時代の友人でアーティストのジム・アルガーという男もまた、先にロサンジェスルに来ていたが、彼が先にディズニーの注意を引き、このジムがトーマスを雇うよう推薦したのだった。1週間の仮採用期間を経て、トーマスは1934年9月に正式に雇われた。その頃、トーマスのもう一人の友人、オリー・ジョンストンは、スタンフォードのフットボール・チームでマネージャーをやっていたが、ローズ・ボールのためにロサンジェルスを訪れたときに自分もシュイナードに入ろうと決意した。彼はトーマスと同じ部屋で暮らしていたが、ドナルド・グラハムの誘いで、スタジオで仮採用された。三週間ののちに彼もまた正式採用された。一年もたたないうちに彼はトーマスに代わってフレッド・ムーアのアシスタントとなった。
もう一人のリクルート組はジョン・ラウンズベリである。彼は13歳で父親を亡くしてから絵を描くことに目覚め、鉄道会社で短い間務めたあと、デンバーの美術学校に入った。さらにロサンジェルスのアートセンターで勉強を続け、そこでとある教員が彼をディズニー・スタジオに推薦した。1935年夏のことである。彼が加わったのは、後に名人アニメーター集団の最後の一人となる男、マーク・デイヴィスのおかげだった。
デイヴィスの親はロシア系ユダヤ移民の第一世代で、読心術の興行で方々を回ってオレゴン州のクラマス・フォールズに落ち着いた。ウォード・キンボールと同じく、デイヴィスもまた2ダースほどの学校に通い、そのためある種孤独な、あちこち旅をする子供時代をすごしたが、どうやらこうした幼少時代は、自身で絵を描くことを楽しむアニメーターという職業には必須のものらしい。北カリフォルニアに映ってからは、デイヴィスは劇場ポスターや新聞広告を描いていた。ユバ・シティの劇場オーナーが、彼にディズニーで働くよう勧めてくれたこともあって、父親が死んでからは、母親とロサンジェルスに移り、ディズニー・スタジオを訪れ、12月にはアシスタントとして雇われた。そこで体験したディズニーメソッドの洗礼について彼はこう書いている。「昼も夜もクラスに出席して、何時間も仕事をして、食事のチケットをもらう、それだけでそこにいることは喜びだった。」
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 6, p227-229, 細馬試訳)
20101007
以下は、ゲイブラー本の第六章、アニメーター列伝に続く記述。邦訳では訳されていない部分で、ディズニー社内の授業内容や自主教育の様子が判っておもしろい。
ずいぶん強引なやり方だったが、当時ウォルトは『白雪姫』を完全なものにしたかった。訓練生たちは午前中、そして昼食をはさんで午後一杯ずっと、一日八時間、ドン・グラハムの実物写生クラスを受けた。数週間後に彼らは中間作家のアニメーターとして週18ドルの報酬を受けるようになる。だがその段階になってもなお、一日の1/3もしくは半分は授業に出なければならなかった。そして1935年の2月始めには、水曜の夜間クラスに毎週出席することが義務づけられた。グラハムは自身のコースのことを、キャラクタの構築、アニメーション、レイアウト、背景、メカニック、ディレクション、果てはスタジオの知識まで若き初心者たちに教えるというスパルタ教育だった、と述べている。
しかし、いまや出席者は訓練生だけではなかった。秋には『白雪姫』の脚本は精密に練り上げられ、映画はいよいよアニメーションの段階に入ったため、ウォルトは通常のクラスを編成し直して、スタジオのアートスタッフのすべてを重労働に疲れた火曜の夜に出席させることにした。授業は行動分析から最近の実写映画の鑑賞に至るまでで、これらを「われわれが取り組んでいるものと結びつけ、明日(つまり『白雪姫』)に備えることを主眼とした」(ウォルト)ものだった。さらに、フランク・トーマスとオリー・ジョンソンによれば、アニメーターは週に二、三度、グラハムの講義を受けていた。それは、フィルムの短い断片を前に後ろに何度も映写し分析するというものだった。グラハムの授業は録音され、書き起こされ、謄写版で刷られて、スタジオ全体に配布された。実物のアクション分析以外に、グラハムはミッキーマウスやドナルドダックの動きを分析し、これらキャラクタのアニメーションを向上させるだけでなく、『白雪姫』を描くためのスキルを研ぎ澄まさせた。グラハムはこんな言葉を残している。「簡単に言えば、描画の原理はどこまでも描画の原理ということです。ルーベンスに使えるものならドナルド・ダックにも使えるし、ドナルド・ダックに使えるなら『白雪姫』にも使えるはずです。」
いよいよ『白雪姫』のアニメーション段階への秒読みとなった。が、ウォルトが十分な準備なしには始めたくないがゆえに、歩みはじりじりとしか進まなかった。彼はさらに訓練を強化したのである。夜のクラス、鑑賞のクラス、そしてグラハムとフィル・ダイクによる行動分析のクラスに加えて、ウォルトはベテランのアニメーターをリストアップし、若手を指導させた。「タイミングの問題や特定の効果をつけることの意味を議論する…この方法でグループの連中の情熱をかきたて、向上につながる結果をすばやく得るための知識を刺激しようと思った」。(ウォルトは後年グラハムに「授業のあと即座にアニメーションが大きく変化するのに気づきました」と書き送っている)。ウォルトはカリカチュアの若き専門家ジョー・グラントに、カリカチュア・クラスを担当してもらい、そこでアニメーターが授業を受けるだけでなくお互いのアイディアを共有できるようにした。他にもさまざまなアーティストを巻き込むべくコースを拡大した。ジーン・シャルロットにはコンポジション、リコ・ルブランは動物ドローイング、フェイバー・ビレンには色の理論。さらに、彼は外部からも、フランク・ロイド・ライトのような有名人を含む講師を招いた。視覚教材を増やし、アニメーターたちがさまざまな動物や事物の動きを「取調室」で見ることができるようにした。さらにはグラハムの引率でアニメーターたちは月一回の動物園への遠足を行った。「この仕事には科学的アプローチが必要なのです」とウォルトは12月、グラハムに長いメモを書いている。「そして、若い人にこの仕事をどう教えたらいいかを完全に見つけ出すまでは、諦めるべきではないと思います」。(中略)
ウォルトにならって、グラハムもまた「キャラクタの動きを考えることがパーソナリティを作る」と言った。ウォード・キンボールとラリー・クレモンスは暑い夏の金曜、オーシャン・パークに行き、クラッカージャックを頬張り、通行人のことを考えながら「彼らはなぜちょっと動きをするのかを分析して、その人の心理に分け入っていった」。キンボールとクレモンスの才能はこうして磨かれていったのだった。フランク・トーマスは卓越したピアニストでもあったが、彼は自分の演奏を聴く聴衆を研究していた。「彼らを見ると絵に使うキャラクタのアイディアが浮かぶんだ」。
人物ばかりでなく無生物も研究の対象になった。「しまいにはレンガを窓ガラスに投げようというところまでいった」とエリック・ラーソンは振り返る。「どんな動きになるか見たくてね。で、それをスローモーションで撮ったりするんだ」。さざ波を研究するために、アニメーターたちは岩を水の中に落とすこともあった。ジョー・メドーはそれでも満足せずさまざまな大きさの岩を異なるタイプの液体に落として、密度がどのように影響するかを観察した。あえて木の扉を勢いよく閉めて、柱枠にあたるときにどうなるかを観察することもあった。ハム・ラスケはカタリーナ諸島へ船で行ったときに自分のネクタイをはずしてそれがどう風になびくかを見たり、ゴルフのパートナーのパットを真似て「予測」という心理状態を表現したりした。「ハムはいつでもアニメーションを研究してました」とエリック・ラーソンは言う。「彼の生活そのものでした」。実のところディズニー社にいるものは誰もがアニメーションをよくするために生活を捧げていた。「どんなバレエでもどんな映画でも見ました」とマーク・デイヴィスは言う。「できのいい映画なら五回は見ました。映画をよくすることならなんでも刺激になりました。場面のカットや演出、場面どうしの結びつけ方。みんな常に研究してました」。
それはあたかも「みんなが完全に一つの軌道に乗った状態」だったと言う。「ウォルトは磁石でした」。
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 6, p230-231, f細馬試訳)
20101006
ゲイブラー本第三章から、1924年、アイワークスがディズニー・ブラザーズに参入したアリス・コメディ時代の部分を訳出しておこう。この部分は邦訳p102-104にもあるが、太字になっている部分は、なぜか邦訳から省略されている。
5年ぶりに会ったアイワークスにはさしたる変化はなかった。ただ、彼の名前は綴りが変わっていた。Ubbe Iwwerksから英語風にUbe Iwerksになっていたのである。もっともこのことは、アイワークス以外は気にも留めなかった。彼は相変わらずおとなしく、引っ込み思案で、表情に乏しく、寡黙だった。「単語二つで済む場合でさえ、一つしか使わないのだから」と同僚は彼を評した。けれど、一つだけ、重要な変化があった。カンザス時代からトレーニングを続けていた頃から、彼は、すでに器用で仕事の速いアニメーターになっていた。何ヶ月も経ち、夏になる頃には、彼はウォルトの仕事の負担をますます請け負うようになっていた。一方ウォルトは、自らのアートの才能に疑問を持ち始めていた。「ドローイングで満足のいったためしがなかった」彼は後年レポーターにこう答えている。
アイワークス自身の変化はカートゥーンにも変化をもたらした。一つには、アイワークスの加入により、アリス・シリーズの重点がアリスからカートゥーンで描かれた相手役へと移ったことだ。夏も終わる頃には、ウィンクラーはウォルトに、もう実写によるオープニングやエンディングをすっかりやめてしまうよう提案したが、のちの映画づくりはより難しくなり高くついた。
もう一つの変化は、ウォルトとアイワークスが実写とアニメーションの合成方法を改良する実験を始めたことだった。これは「マット」と呼ばれる切り抜きによってカメラのレンズを覆い、アニメーションが入るべき領域を撮影しないようにする方法だった。これならアリスを白い防水シートの背景で撮影しなくてもよい。八月にはウォルトはウィンクラーに宛てて「この方法なら、女の子はカートゥーンと演技するときくっきりと映ります。撮影も今後の作品では完璧とまではいかずとも、よりよくなるでしょう。まちがいなく大爆笑がとれるようなものを作りたいと思っています」と請け負っている。
とにかく優れた映画を作りたいという並外れた欲望に満ちたウォルトは、アイワークスの貢献のもと、絶えざる改良を続けだが、アリス・シリーズの出来はおきまりの映画並みというところだった。ウォルトの実写撮影のコンセプトは、せいぜいアマチュアファン並みだったし「アイワークスのアニメーションはディック・ヒューマー(フライシャー・スタジオのメインのアニメーター)の描くココのような洗練されたドローイングとは比較にならなかった」とあるアニメーターは振り返っている。単に他と比較して撮影やドローイングが未熟だっただけではない。模倣的で想像力に欠けていた。原因はウォルトの経験の浅さによるものなのかもしれないし、イマジネーションの欠如によるものかもしれないが、ほんとうのところはわからない。ともあれ、ウィンクラーはいつも、筋運びやパーソナリティの描写よりもとにかくギャグを盛り込むよう強く要望し、ウォルトにできるだけ他のスタジオのアニメーションを観るように薦めた。が、ウォルトの方は、二月にウィンクラーに宛てた手紙に、ドタバタ喜劇よりももっと違った、洗練されたものをやってみたい、と書いている。
ディズニー・ブラザーズでは試写室にかけるお金がなかったので、ロイも含めスタッフ一同は、ヒル・ストリート劇場のプログラムが変わるたびにポール・テリーのイソップ物語の新作を観に行き、そのアイディアを拝借した。「とにかくいい映画を作りたいという一心だった」とウォルトは言っている。「けれど、我ながら先見の明があったというべきだろう。1930年になってもなお、わたしの目標はイソップ物語シリーズのようなよいカートゥーンを作ることだったのだから。」
(中略)
アリス・コメディのほとんどは模倣であり、ウォルトはウィンクラーにことごとく譲歩し、自身の創造力を彼女の支配下に置いていた。しかし、アリス・コメディには、ウォルト・ディズニーの根源的なヴィジョンが表現されていた。『インク壺から』では、ココは実写の世界で跳ね回るものの、そこはかたくなで弾力に乏しい世界だ。一方アリス・シリーズでは、実写世界の女の子が、自ら編み出したファンタジーへと入っていくが、そこはしなやかな世界である。女の子がどんな無茶な冒険をしようと、最後は彼女の思い通り、ジュリウスのたくらみ通りになり、混沌はやがてコントロールされる。このような状況を作ることで、ウォルトはカートゥーンによる解放と権力のメタファーを産み出した。フライシャーが物質世界の手なずけ難さを示したとすれば、ウォルトは、その人の心理的世界を思いのままに鍛え上げうること、アリスの逃げ込めるような場所へと変えうることを示した。ウォルトの世界では、人は常にとらわれることを避け、現実の割り込みをできるだけ食い止めようとする。どんな困難に直面しても、ウォルトの世界の住人は自由で全能である。その世界にいる限り、その世界が無事である限り、そして現実界と切り離されている限りは。
しかしながら、不幸なことに、現実はまさにディズニー・ブラザーズに割り込んできた。それも最後には破滅的なまでに。現実は、チャールズ・ミンツという男の形となって割り込み続けたのである。
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 3, p86-88, 細馬試訳)
時代は下って1932年、シリー・シンフォーニーの『三匹の子ぶた』が、パーソナリティ・アニメーションにとっていかに革新的だったかをチャック・ジョーンズは以下のように語っている。簡潔な表現で的を得ていると思うので、訳出しておく。
「それまでにはなかったことが起こっていると実感しました」とアニメーターのチャック・ジョーンズは『三匹の子ぶた』のもたらした影響を語っている。「この作品によって、パーソナリティを決めるのはキャラクタの外見ではなくその動きであることが示されました。三匹の子ぶたたちが演じて以後、わたしたちアニメーターは皆、この問題に取り組むことになったのです」。ジョーンズはパーソナリティ・アニメーションは『三匹の子ぶた』に始まる、とさえ信じている。*
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 5, 細馬試訳)
*『創造の狂気』では次のように訳されている。
アニメーターのチャック・ジョーンズは、「これまでにないことが起きている。キャラクターがどのように見えるかではなく、その動きによって、どのように人格が決定されるかである。人格のアニメーションが誕生した」と子ブタ効果を絶賛した。
三匹の子ぶたのそれぞれの外見は、ほとんど変わらない。それでいてパーソナリティの違いが顕れている。そこにチャック・ジョーンズはショックを受けたのだった。
朝、会議。午後は講義と御子柴さんのゼミ。渋谷さんへの聞き取りはしばらく見ないうちにずいぶん進んでいて驚いた。以前に比べると、インタヴューの様子もずっと頼もしい感じ。
20101005
Gabler『Walt Disney』の原作にはたくさんの固有名詞が登場する。中でもアニメーターたちに関する記述は、従来の評伝になく詳しい。固有名詞がいくつも登場すると記述は長くなるし、それを敬遠する人も出るかもしれない。あるいはそうしたことに配慮したのだろうか、邦訳『創造の狂気』では、原作に含まれている固有名詞にまつわる文章が、各所で大胆に省略されている。
たとえば、第六章で、邦訳『創造の狂気』には以下のような短い記述がある。
彼は常に人材を求め、ディック・ヒューマーやグリム・ナットウィック、ウォード・キンボールなど、ディズニーの下で働くことを希望するベテランを引き抜くだけでなく、有能な新人の発掘にも力を注いだ。
この一文には、名前がただ並べられているだけで、三人がどんな人物なのか、三人のうち誰が「ベテラン」で誰が「有能な新人」なのかすら判らない。
しかし、原作の該当部分には、それぞれの人物に関する詳しい説明がある。それも三人どころではない。『白雪姫』に関わることになる幾多のアニメーターたちが、一人一人エピソードを交えながら、ページを費やして紹介されるのである。そこには、1930年代アメリカにおけるさまざまな人生もほの見える。以下、訳しておこう。
ウォルトは才能ある者をいつも探しており、作品の出来に貢献してくれそうなアニメーターを雇うことを常に考えていた。
新たに加入したヴェテランの中には優れたアニメーション・スタジオで働きたいという希望を持っていた者もいた。カーメン・マックスウェルはカンサス時代からのウォルトの旧友で、ハーマン-アイジングの元で働いていたが、「もうここでは満足できません。彼らにはアイディアを育てて本物の第一級の映画を作ろうという基本的な欲求が欠けているのです」とウォルトに書き送ってきた。さらに手紙にはこうあった。「驚かれるかもしれませんが、もし綿密な計画でしっかりと作られた映画のために仕事ができるのなら、いまより安い給料でもっと働きたいと思います」。
同じような気持ちをもつアニメーターたちが1932から34年にかけてディズニー・スタジオに流れ着いた。そしてウォルトは彼らを快く迎えた。明らかに『白雪姫』を念頭においてのことだろう。八人兄弟の一人として貧しい父親のもとでネブラスカ、アイオワ州に育ったアート・バビットは、十代のとき、精神分析医になるつもりでコロンビア大学を目指してニューヨークに渡ったものの、実際には六週間ものあいだ教会の階段の吹き抜きで眠り、ゴミ箱から食べ残しを漁る生活を続けることになった。ようやく広告代理店の仕事を見つけ、フリーランスのアーティストとしてポール・テリーのアニメーション・スタジオで働いていたとき、ディズニーの『骸骨の踊り』を観て彼は衝撃を受けた。「これこそわたしの求める職場だ」。彼はテリーのスタジオを止め、カリフォルニアへと旅立ち、その足でまっすぐディズニー・スタジオに向かった。ウォルトとの面会がかなわないと知ると、20×24フィートのとんでもなく巨大な手紙を描いて、インタヴューの申し入れを書き込み、特別便で送りつけた。ウォルトは降参して、正式に面会し、数日後、彼を雇い入れた。
この種の「ディズニー・スタジオへの道」物語は、恵まれないアニメーターたちの間でおなじみとなり、ハイペリオンへの「ヘジュラ」を促したことだろう。ディック・ヒューマーは、高校を退学したのち、アート・ステューデント・リーグに行き、さらにそこを止めてアニメーション創成期のラウール・バレのスタジオに加わった。チャーリー・ミンツのところで働いているときに、給料のカットが申し渡されると、ヒューマーはすぐさまカリフォルニアに向かい、1933年にディズニー社に参加した。けれど、その契約の給料はミンツからもらった額の半分だった。
グリム・ナトウイックはロイとウォルトによって見出された。二人はフライシャーのベティ・ブープが走る列車に飛び乗るシーンを見て、これを描いたナトウィックをスカウトしたのだった。しかし、ナトウィックは誘いを断り、いったんはアブ・アイワークスの新しいスタジオに1931年に加わった。「東海岸ではディズニースタジオの天才はアイワークスだという評判だったからです(ナトウィック)」。しかし3年後、彼もご多分にもれず、ディズニーに改めて申し入れをした。当時ウォルトは一度自分を拒絶したものを雇わないという評判だったが、ナットウィックは友人のテッド・シアーズの口利きで、ウォルト自身に二時間ものあいだスタジオを案内してもらい、快く契約された。
加わったベテランの中でもおそらくいちばんの重要人物がいる。ニューヨーク州はヨンカーズ生まれ、ウクライナ人の父親とポーランド人の母親との間に生まれた、熊のような大男。ぼうぼう髭に濃い眉毛、ぼさぼさ髪という風体の彼こそ、ウラジミール・「ビル」・タイトラである。風体はあたかもスターリン、パーティーともなれば片手で胸をどしどし叩きながら、もう片方の手にウォッカを掲げて「おれはコサックだ!」と叫び出す。仕事に対しても、彼の態度は変わらなかった。ナットウィックによれば「ドローイングに覆い被さるその姿は、金の卵でいっぱいの巣を守るコンドルといった風だった。情熱的で、神経質で、入れ込みやすく、感情の起伏の激しい仕事人だった。」あまりにも根を詰め精神込めて描くので鉛筆で紙に穴を開けてしまうことさえあった。タイトラが特別なのは、自身の狂暴さをスクリーンに込められることだった。ポール・テリー・スタジオでのタイトラのドローイングはあまりに他のものと違ったので、ウォルトにはどれが彼の絵かすぐに見分けがついた。ロイは1933年5月にニューヨークに着いたとき、彼はタイトラを西海岸にスカウトしようとディナーに誘った。ウォルトへの手紙にロイはこう書いている。「彼はよりよい仕事をする機会に恵まれたいことを全身で表している」。ただしテリーのもとを去るにあたって、彼はあくまで「儲かる待遇」を要求した。
タイトラが自身を高く売りこむ一方で、ディズニー社の側も強く出ていた。就職・訓練担当のベン・シャープスティーンは、12月にタイトラに宛てた手紙で、こう書いている。スタジオはこれまでよそから来たアニメーターにディズニー流のスタイルを教え込むのに難儀してきたので、「能力を評定させてもらわないことには、よそから来た人を入れるわけにはいきません。それではわれわれアニメータースタッフのメンバーに不公平ですから」。シャープスティーンが提示したのは週100ドル、これはタイトラのような地位のアニメーターにはとても受け入れられない数字であった。それでも、『白雪姫』をわずかでも実現に近づけるために、ロイは翌年になってもタイトラをくどき続け、ニューヨークを訪れるたびにタイトラをディナーに誘った。「くっついたり離れたりのロマンス」(タイトラ)が続いた結果、ついに彼はウォルトとロイの招きに従って、カリフォルニアに飛んできて、スタジオ見学をした。1934年11月、その8時間のフライトとスタジオツアーのあと、とうとう彼はディズニーの猛攻の前に屈した。彼の参入によって、スタジオ付きの芸術講師ドン・グラハム言うところのアニメーションのニュー・スクール、すなわち「力と形派 Forces and Forms」が生まれた。これはタイトラがアニメーションの猛烈な動きを描くときに発揮する力にちなんだネーミングだ。彼はスタジオで熱狂的な崇拝を受けた。スタジオを去る日には若いアニメーターたちがタイトラのオフィスに急ぎ、くずかごから没原稿を拾うほどだった。……
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 6, 細馬試訳)
アニメーター列伝はまだまだ続く。ここまではベテラン勢で、ここからあとには、当時の新人だったウォルフガング・リーザーマン、エリック・ラーソン、ウォード・キンボール、ミル・カール、フランク・トーマス、ジョン・ラウンズベリーが登場する。その各人について、ゲイブラーは上記と同様の分量で丁寧に性格分けをしていく(これらすべてが、邦訳では先の一文のみで要約されている)。
このような記述を経たあとに、たとえば「こびとのグランピーをタイトラが描く」話を読むと、わたしたちは、スターリンのような風体の大男がデスクにかじりついて、女嫌いで気むずかし屋のちっちゃなグランピーを描いているところを想像することができるわけである。
いったん原作の流れに乗ってしまえば、固有名詞による記述は、むしろ楽しみとなる。アニメーターの一人一人に名前があることや、その一癖も二癖もある性格が表現されることを疎ましく思うファンがいるだろうか。『白雪姫』が好きな人なら、読み進めるうちに、それぞれのアニメーターは、あたかも七人のこびとのように親しみを持って感じられ出すだろう。
ゲイブラーはおそらく、ディズニーの言う『パーソナリティ・アニメーション』の手法を、自身のドキュメンタリに応用している。こびとたちの白雪姫に示す行動によってそれぞれのパーソナリティが明らかになるように、それぞれのアニメーターがウォルトやロイにどのように振る舞うかを綴ることによって、彼らのパーソナリティを明らかにする。アニメーターの動き(モーション)とエモーションは、読者にとって信じるに足るものになり、アニメーターに対して読者の感情が動くようになる。
七人のこびとを描き分けるようにドキュメンタリを書くこと。ゲイブラーが目指しているのは、おそらくそういうことだろう。
朝、コミュニケーション論。指さしについて。注意の獲得、注意の接続(共同注意)、共通基盤のある場合、共有知識/経験のある場合。図書館の前に止めた自転車、というトマセロ例をネタに、恋愛ドラマのシナリオの巧拙を説く。
まず、わずかな身振りによって、観客にはわからない共通基盤、もしくは共有知識/経験がそこにあることを推測させる。それが何であるかを、シナリオの中で明らかにする。最後に、もう一度、ある身振りによって、いまはもう観客のものとなった共通基盤、共有知識/経験を立ち上げる。うんぬん。
それから院ゼミ。午後は城さんのゼミ。同期と延長ジェスチャーのおもしろい例をいくつか発見する。卒論生の実験。
20101004
それにしても、どうやら「翻訳病」に取り憑かれたらしい。一年のうちに何度か、ヨコのものをタテにしないと気が済まなくなる時期があるが、どうもそれらしい。翻訳をしていると、自分の日本語のかたいところが判って、そこのコリをほぐしていくような感じがするのである。というわけで、またまたGablerのディズニー評伝の話。第五章の重力話の続きの、これまた邦訳『創造の狂気』ではまるまるカットされている部分を訳しておこう。ディズニー社にいかなる経緯で「学校」が誕生したかが書かれている。原文では3766(Kindle No.)あたりから3811あたりにあたる。おもしろいよ。
しかし、アニメーターたちの能力にも問題があった。(重力表現によってもたらされた)リアリズムの新しい基準に見合うには自らのスキルを上げねばならない。そのことは、アニメーターたちも判っていた。「現実に基づいてすばらしいものを作るには、なにがなんでもまず、現実を知らねばならないね」とウォルトは提言した。トレーニングが必要だった。早くも1929年には、ウォルトはアニメーターたちをロサンジェルスのダウンタウンにあるシュイナード芸術研究所の金曜夜の授業に送り込み、自身はまたスタジオワークに戻り、あとでまた全員をピックアップしに行った。1931年にはシュイナードと契約して、十数人ものアーティストたちを週に一度トレーニングすべく送り込んだ。そのうちの一人、アート・バビットはアーティストどうしで集まるほうが効果的だと考えて、ハリウッド・ボウルのそばにある自分の家を開放し、モデルを呼んでインフォーマルなドローイングの集まりを開くことにした。1932年の夏遅く、もしくは秋の始まる頃、アートがホストとなっていよいよ集会が始まった。第一週に8人を呼ぶと14人が集まった。次の週に14人を呼ぶと22人が集まった。数週間後に、ウォルトはバビットをオフィスに呼んで「ディズニーのアーティストたちが誰かの家にぞろぞろ集まって裸の女を描いてるなんて話が新聞に載ってごらんよ」と言った。「社としてはまずいじゃないか」。ウォルトの出した代案は明らかに、スタッフの誰にとってもより魅力的なものだった。録音スタジオとそこにあるものをすべて解放するというのだ。この代案に乗じて、バビットの家に通っていた若きアニメーター、ハーディー・グラマツキーが、シュイナードの授業を担当していたドナルド・グラハムを講師として招いて、正式な授業を受けたいと申し出た。バビットはグラハムと契約し、11月15日、「グレイト・ディズニー・アート・スクール」(とグラハムは呼んだ)の最初の授業が行われた。
最初、録音スタジオでの集まりは週に二夜、参加者は20-30人というところだった。ひと月も経たぬうちにその数は膨れあがり、グラハムはもう一人の講師、フィル・ダイクを呼んで、クラスを二つに分けた。その後の二年間で、各週の出席者平均は50人以上となり、グラハムは三人目の講師を用意せねばならぬこともあった。集まりは週に5夜となり、出席は義務ではなかったものの、バビットが言うようにそれは「行っておいたほうがいいよ!」だった。
カナダ生まれでスタンフォードでエンジニアの勉強をし、シュイナードで美術に関わるようになったグラハムは、指導の当時まだ29際だった。ハンサムでがっしりして、ウェーブのかかった黒髪、四角い顎、黒い瞳、長い腕、そして芸術家らしい長い指。洞穴のような部屋の前に立って煙草に火を点けると、話しながら片手からもう片手へと煙草を移動させ、煙草の灰が指の近くに来るまで授業に集中し続けた。彼に与えられた課題は、一人の生徒のことばを借りるなら「まったく不可能なこと」だった。グラハム自身はアニメーションの訓練を受けたことがまったくなかったが、ウォルトが彼に期待していたのはアニメーションの講義ではなかった。ニューヨークあがりのぞんざいなアニメーターや、元新聞カートゥニストや、芸術系の学生バイトや、才能ある道楽者たちに彼が教えたのは、(あるアニメーターのことばを借りるなら)「一つのスタイルにとらわれずに」事物をドローイングする技法だった。グラハムは基礎をたたき込み、どう描くかを教えた。それは本物のドローイングだった。あるアニメーターはその意味に次第に気づき出した。「コミック・ストリップを動かすという旧来のアニメーションの考え方を、彼は片手でもって攻撃して」、リアリズムという新たな考え方に置き換えようとしていた。グラハムこそはアニメーターたちに、ものの塊に重力がもたらす効果を教え、肉体や筋肉がどのように動くか、「二次的効果」がどのように生まれるかを教えた。アート・バビットによれば、グラハムこそが彼に「分析すること」そして「ほんのちょっとした調子外れの要素を動きに加えるだけで、まったく異なるキャラクタに仕立て上げることができる」ことを教えてくれた。もう一人のアニメーター、シェイマス・カルヘインは、ウォルト・ディズニーを除けばドン・グラハムこそが「映像メディアの哲学に大きなインパクトを与え、偉大なる先人たちの理論と、モダン・アートと、そして動きの科学原理とを教育することによって、洗練された映像作家集団を育て上げた」とまで言っている。
(中略)
他のスタジオのアニメーターたちもまた、ディズニーのアニメーターのような時間が持てれば、同じようによい仕事ができるのにとうらやんだことだろうが、問題は時間というよりも、メンタリティの方だった。ウィリアム・タイトラはディズニー社に来る前はニューヨークのポール・テリーのところで働いていたが、彼によれば、テリーにモデルをやとって作画の技術を向上させてはどうかと提案したところ、自分で雇うよう言われ、グラハムのような講師を雇うアイディアは却下されてしまったため、結局タイトラは諦めてしまった。「アートスクールに行くようなやつは『ホモ・ボルシェヴィキ』だって言われましたね」。シェイマス・カルヘインもフライシャー・スタジオで似た経験をした。「時間ではなく、教育の問題なんだってことを彼らはどうしても受け入れなかった」と彼は書いている。「フライシャーの連中は直感的にやっていて、描き方とかアニメーションに原理なるものがあるというアイディア自体、まるで相手にしていなかった」。
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 5, 細馬試訳)
『創造の狂気』の訳については、もういちいち書くまいと思い始めているのだが、あまりに違和感がつのるので、もう少しだけ。
たとえば、『蒸気船ウィリー』については次のように訳されている。
筋立てとしては、不格好なネコかイヌの船長から脅かされてミッキーが逃げまわり、女ネズミのミニーがホックにぶらさげられて、ミッキーと唄を歌うくらいだった。(『創造の狂気』p150)
「ネコかイヌの」というのは投げやりに響くし「女ネズミのミニー」という呼称もどうかと思うが、『蒸気船ウィリー』ではミッキーもミニーも唄など歌わないし、ましてホックにぶらさげられて歌ったりはしない。そんなばかな、と思って原文を見るとこうなっている。
The only plot elements are a hulking cat of a captain who terrorizes Mickey - the intrusion of reality - and whose severity he escapes through his music, and Minnie Mouse, who joins his recital when Mickey swings her aboard with a loading hook.
原文に沿って訳すなら、たとえば次のようになるだろう。
プロットの要素と言えばせいぜい次のようなものだ。ごついネコの船長がミッキーをどやしつけ —リアリティの割り込みである— 厳しい船長からミッキーは音楽に逃れる。ミニーマウスはミッキーによってクレーンのフックで吊り上げられて手荒に乗船させられ、彼のリサイタルに加わる。
朝、「こころのテクノロジー」。17世紀以降の神経科学の発達。神経の構造の発見など。
会議打ち合わせ。Atkinson & Hilgardの新しい版を買ったので、古い版を思い切って裁断し、ページスキャナにかける。
午後、一回生の実習。倒れかけレッスンののち、ペアを組んでもらい交替でアイマスクをして、数十分、外を歩いてもらう。ぼくも学生の一人とペアを組み、外へ。せっかくなので田んぼの真ん中まで行ったところでちょうど日が暮れるところだった。ねぎの匂い、土の匂い、モロコを買う池の匂い。目を開けているときには気づかなかった匂いのグラデーション。
20101003
先日来から書いているGabler『Walt Disney』の話の続き。邦訳『創造の狂気』と原作とのあまりの差に愕然とし続けているのだが、もはや、訳自体の問題よりも、原作の重要な部分をできるだけ救出しておきたくなってきた。
Gabler本には「パーソナリティ・アニメーション」という重要な概念が書かれている。『創造の狂気』では、第五章、p187 l7-p188 l1にあたる部分*だが、邦訳では文章が要約され、誰が何を言ったか、どんな表現だったかがごちゃごちゃに入れ替わっている。ゲイブラーの原文は平明な英語で書かれており、要約せずとも読みにくくはない。以下、原文にそって訳しておこう。
ウォルトはかつてフランク・トーマスにこんなことを語った。フェリックス・ザ・キャットのようなキャラクタは「あちこちにちょっとしたパーソナリティのようなものは感じられる」。ウォルト自身、オズワルド・ザ・ラビットやのちのミッキーマウスのパーソナリティを鍛え上げようとしたこともある。けれど、こういうほんのちょっとのパーソナリティでは足りない。ウォルトはいつもアニメーションをチャップリンやキートンのライブ・アクションにできるだけ近づけようとした。観客が求めているのは参入感 involvement だということを彼はわかっていた。観客はキャラクタのことを気にかけたいのであって、単に笑いたいだけではない。ウォルトはアニメーターたちに、観客からエモーショナルな反応を引き出すことのできるキャラクタ作りがいかに重要かを強調するようになった。「これは何よりも大事なことでした」とウィルフレッド・ジャクソンは当時を振り返る。「それもこれも、ウォルトはカートゥーンのキャラクタを観客に信じ込ませたいと願っていたからです。なにより彼は、キャラクタが単にスクリーン上を動き回っておもしろいことをするだけの存在となってしまうことを好みませんでした」。エリック・ラーソンも同意見だ。「キャラクタを作るときには、そのキャラクタは人々と関係を結べるようなものでなければならなかった」。ウォルト自身も後に彼の美学をこんな風に定式化している。「あらゆる芸術で最も重要な目標は、見る者から純粋なるエモーショナルな反応を引き出すことである」
このような反応を引き出す唯一の方法は、「パーソナリティ」を用いることだとウォルトは信じていた。パーソナリティ、それはいくつもの性質の組み合わせであり、それぞれのキャラクタに独自のもので、キャラクタにぴったりとくっついて、キャラクタを決定するものである。スタジオにはディズニーからお布令が出た。曰く、アニメーション化されるキャラクタはもはやギャグを演じるための単純な役ではいけない。それは豊かな「フルボディ」でなければいけない。あるアニメーターのことばを借りるなら「その動き(モーション)とエモーションを信じることのできるような」ものでなければならない。
ウォルト・ディズニーがアニメーションにもたらした数々の貢献や発明には、いつも優雅さへの渇望が感じられる。が、それはさておき、このパーソナリティこそは、最も重要な唯一の問題だったといえるだろう。なぜなら、肉体的な見かけでも物語の強さでもなく、観客との基本的関係こそが、アニメーションを革命的に変えたからであり、これこそが、ディズニーとライバル会社との最も重要な違いだったからである。すべてのキャラクタは単に動かされているものとしてではなく、生きているものとして扱われねばならない。このアプローチはやがて「パーソナリティ・アニメーション」と呼ばれるようになった。
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 5, 細馬試訳)
*『創造の狂気』の該当部分は次の通り。
ウォルトはウサギのオズワルドやミッキーマウスに人間性を付与しようとしたが、それだけでは不十分と考えた。そして彼はアニメーションをチャップリンやキートンの実写映画にできるだけ近づけるためには、観客が共感を覚えることが重要と考えた。そして観客がスクリーン上のキャラクターに笑うのではなく、それに取り込まれていくことが必要と判断して、アニメーターに対しては、観客から共感を引き出せるようなキャラクターづくりの重要性を説いた。
「ウォルトにとってはそれが一番大切だった。漫画のキャラクターがスクリーンの上を跳びまわり、滑稽なことをしでかすのではなく、観る者がその存在を実感するようなキャラクターでなければならない」とウィルフレッド・ジャクソンは言い、またエリック・ラーソンは、「アートで最も重要なのは、観る者から純粋に感情的な反応を引き出すことである」とする。
これに応える唯一の方法は個性だとウォルトは確信していた。キャラクターはもはやギャグのために機能するのではなく、「全人的」で、行動も感情も現実的でなければならない。ディズニーのアニメーションがほかと一番違う点は、単に「生きるように動く(アニメート)」のではなく、「実際に生きている」こと、「人格のアニメーション」であることである。
この部分に続いて、邦訳『創造の狂気』には以下の短い二文が訳されている。
ディズニー・アニメのマジックは、個性が内面化したように描かれることである。「ものが動くのではなく、生きて考えているように描かねばならない」とウォルトは言う。(『創造の記述』p188)
原作ではこの部分はもっと長い。「パーソナリティ・アニメーション」とは何かを示すよい記述だと思うのでこれまた訳しておこう(太字部分が邦訳箇所に対応する)。
ウォルトにとって、パーソナリティは、ただの身体行動から生まれるものでもなければ、ひっぱたかれたときにキャラクタが起こすような感情的な反応ですらなかった。パーソナリティがドローイングから、あらかじめ埋め込まれていたかのように湧き出てくること (personality seemed to emerge from the drawings as if it had been internalized)、それがアニメーションの魔術、ディズニー・アニメーションの魔術だった 。「こいつが動いているということを描くだけじゃだめなんだ、ほんとうに生きて、考えているのだということを描かなくては」(You have to portray not only that this thing is moving, but it is actually alive and thinks.)とウォルトは言っている。考え感じるキャラクタ、心理の動きを持ち、感情の振れ幅を持つキャラクタ。それは当時のディズニースタジオにあってさえ革命的なことだった。ほんの数年前までは、ドローイングから声を出しても観客は受け入れてくれるだろうか*などと考えていたのだから(訳注:*ディズニー初のサウンド・アニメーション『蒸気船ウィリー』のこと)。
『プルートの大暴れ Playful Pluto』(1934)では、ウェブ・スミスの担当するプルートと蠅取り紙との格闘場面に、ノーム・ファーガソンが動きをつけた。これにはスタジオの者たちが衝撃を受けた。「とんでもない大発明」とウィルフレッド・ジャクソンは呼んだ。「これはものすごいことだった。なにしろ、キャラクタが何を考えているかが、まるで目に見えるようにわかってしまったのだから」とウォード・キンボールも振り返っている。「われわれはそろそろ跳ね回ってダンスをするミュージカル時代のディズニー短編を抜け出しつつあった。キャラクタがみんな満面の笑みを浮かべて音楽に合わせたり楽器を鳴らすような世界からね。新たに考えられ始めたのは、その場の状況に必死で取り組み続ける、バスター・キートンやハロルド・ロイドや、チャップリンのようなキャラクタだった」。ファーガソンのアニメーションはすでにその流れるような動きによってウォルトの賞賛を勝ち得ていたが、いまやキャラクタの心理の深さにまで賞賛は及んだ。「ファギー、君は大した俳優だよ」ある日ウォルトはスタッフの前でこう告げた。ファーガソンが恥ずかしそうに笑って縮こまっているとウォルトはさらに続けた。「いや、ほんとうのことだ。君のアニメーションがなぜすごいかって、それは君が感じているからだよ。キャラクタの感じることを君が感じているからなんだ」。
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 5, 細馬試訳)
上の部分に続けて、ディズニーアニメーションの「重力」の問題が原作の第五章では綴られている。ここも翻訳ではまるまるカットされているが、非常におもしろい部分だと思うので、訳出しておこう。
ウォルトはアニメーションのキャラクタがより真に迫って見えるような、迫真的な視覚世界を求め、そのことで観客とのエモーショナルな絆を築き上げようとした。これこそがアニメーション化された世界、ウォルト言うところの「不可能な本物らしさ plausible impossible」であり、それは犯すべからざる自然則として打ち出された。
この新たなる自然則の出現とペンシル・テストによる場面分析によって、ディズニーのアニメーターたちは、それまで経験的に踏襲してきたアニメーションの流行スタイル、すなわち「ゴム管」と卑下されていたスタイルを止めるようになった。「ゴム管」アニメーションでは、リアリズムを実現する困難さを避けて、描きやすさが優先された。キャラクタやものの形が変わると、あたかもゴムでできているかのようにその容積も変化した。重力も重さも考慮されていなかった。ウォルトはこれに悩まされた。リアリズムの欠落は、キャラクタの心理の動きやエモーショナルなリアリティを損ない、観客とのエモーショナルな絆を断ち切ってしまう。ジャクソンによれば「ウォルトは自分のキャラクタを信じうるものにしたいと思い始めた。そのため、『ゴム管』にはおひきとりいただかねばならなかった」。いまやカートゥーンの世界に初めて「重力」が現れた。さらには、髪や服や木の葉などが重力に遅れて反応するときの「二次的動き」も問題になった。ディズニーに先だって、ディック・ヒューマーはこう回顧している。「服が体に従ったり、風にそよいだり、落ちるときには数コマの遅れを持たせる必要がある。これはごく自然な現象なのに、それまで誰も考えたことがなかった」。スタジオの誰もが、いまや重力に取り憑かれるようになった。アニメーターの壁にはさまざまな標語が張ってあったが、こんなものまで張り出されるようになった。「ドローイングには重さ、深さ、バランスがあるか?」
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 5, 細馬試訳)
わたしは個人的に、アブ・アイワークスが得意とした「ゴム管」的アニメーションが好きで、ディズニーの目指した重力表現には、諸手をあげては賛成しない。『白雪姫』で、着地に遅れてゆっくりとわざとらしく降りてくる服の裾の動きも悪くはないが、「プレイン・クレージー」のぐにゃぐにゃするスピードの方だって、ぐっと来る(ちなみに「ONE PIECE」の身体表現はまさにここでいう「ゴム管」だよね)。とはいえ、ここで考えられつつある重力表現は、のちの宮崎駿アニメーションに見られる「風になびく衣服」にまで通じる、とても革新的なアイディアでもある。それが1930年代にこれだけ考え抜かれていたのだから、驚かざるをえない。
20101002
Gabler『Walt Disney』の邦訳、ゲイブラー『創造の狂気』は、読むほどにどうも首をひねる内容である。原作に盛り込まれた重要なエピソードがいくつも落とされ、文章はつぎはぎに要約され、しかもあちこちで原作と違う意味の文章ができあがっている。気づかなければよかったのかもしれないが、不幸にもわたしはこの原作をけっこう読み込んでしまい、省略されてしまった原作部分が不憫になってしまった。他の方の訳業に首を突っ込む野暮は承知で、あえてここにその例を記しておこうと思う。
すでに20100930の日記で、いくつか例を挙げているので、ここでは、別の例を挙げておく。
ディズニー・スタジオのペンシル・テストがもたらした悲喜劇
1930年代のディズニーのスタジオでは、「ペンシル・テスト」と呼ばれる試みが行われていた。第五章で、この「ペンシル・テスト」について書かれた箇所を、原文にそって試訳してみよう。
ディズニースタジオのアニメーターたちは早い段階から「ペンシル・テスト」と内輪で呼ばれていた新たな方法を採っていた。これはまだラフ段階の絵を安いネガフィルムに焼いて、アニメーションが完成する前に見るというものであった。トム・パーマーは、おそらくは1931年の早い時期にペンシル・テストを試していた。彼はそれをムヴィオラという、短い場面を見るための小さなスクリーン付き装置にかけていたのだが、そこにたまたまウォルトが通りかかって何をしているのかたずねた。テストを見たウォルトはラフをプレヴューすることの重要さを思い知り、これをスタジオで慣例化することにした。
ウォルトはさっそくムヴィオラを、窮屈で息苦しい窓なしのクローゼットに据えた。のちにこの場所は「取調室」と呼ばれるようになった。背中を丸めてのぞき込むムヴィオラの画面はわずか4インチ四方、ウォルトとそこに呼ばれた場面担当のアニメーターとは、この「取調室」で問題のアクションを何度も何度も繰り返し見て分析し、どうすればうまく、よりおもしろくできるかを見極める。「考えてみると驚きだが、自分の作業を研究して、スクリーンにかかる前に間違いを直していくなんてことををしたのは、私の知る限りわれわれが最初だった」と、ウォルトは数年後に振り返っている。「ハイペリオン通りにあるわれわれの小さなスタジオで、すべての場面のラフが分析のために映し出され、すべての場面が「これがわれわれにできるベストだ」と言えるまで描き直された。」
ついにはウィルフレッド・ジャクソンが、ペンシル・テスト化された場面とまだ動画化されていない場面のスチル画とをつなぎあわせて、「ライカ・リールズ」と呼ばれる長いシークエンスに仕立て上げた(これらのリールを撮影するのにライカを使ったのにちなんでいる)。これでアニメーターたちは、場面どうしの関係を見ることができるようになった。ウォルトはさらに音も加えてみようと言った。その結果、ウォルトと4,5人のアニメーターたちが「取調室」で押し合いへし合いしながら、まだドローイングもインク入れもセルのベタ塗りもされていない段階で、カートゥーンの一部始終をプレヴューすることができるようになったのである。自分の権限が増したおかげでウォルトのやる気は倍増した。彼はライカ・リールズに熱中したが、製作過程はかえって簡単にはいかなくなった。カートゥーンが完成してプレヴューまでできたあとになっても、なおもウォルトはスタッフを取調室に呼びつけて改善を命じたからである。
ペンシル・テストとライカ・リールズの効果はディズニーアニメーションの質を向上させるにとどまらなかった。アニメーションの性質が変わってしまったのである。ペンシル・テストを使う以前は、アニメーターはきちんとしたドローイングとかっちりとした「中間絵 in-betweens」を目指し、できるだけやり直しをなくそうとした。しかしその結果、絵は融通の利かない、固いものになった。「かつてのアニメーションはポーズからポーズへと考えなしに描かれていました」とディック・ヒューマーは言う。「言うなれば平坦なデザインだったのです。そこには重さというものがなかった。」こうしたカートゥーンではキャラクタは「動きが完全に停止すると凍ったようになり、そこで改めてぱちぱちとまばたきしたり、髪が逆立ったりしたわけです。顔がくるっと動くのに、残りの体はそこに貼りついたままでした」。ウォルトはこうしたアニメーションのことを「君のキャラクタは魂が抜けてただのドローイングになったみたいだな」と言った。
かつてスタジオではアブ・アイワークスがアニメーション技法に関しては基本的な指揮権を持っていた。彼はアクションを描くのがうまかったものの、キャラクタに動きの連続や淀みなさを与えることはできなかった。それでも、アイワークスはスタジオのお手本だったし、ウォルト自身もそれは認めざるを得なかった。「アニメーターの連中は馬鹿みたいにおのおの別々のドローイングに取っ組んでいた。それを止めさせて、グループで一つのアクションを描くことを考えさせたかったんだが、これがとんでもなく難問だった」。しかしアイワークスが抜けてペンシル・テストが導入されると、アニメーターたちはかつての考え方から解放され、実験にとりくんだ。ノーム・ファーガソンが海底のファンタジー( Frolicking Fish, 1930)を描いたとき、ウォルトは他のアニメーターたちにその動きを研究するように言った。というのもファーガソンはコンスタントな動きの流れのようなものをそこに作り出していたからだ。「すぐに誰もが、より緩やかに描くようになった」と他のアニメーターも回顧している。「動きに自由さが生まれだしたんだ」。1931年になると、ディズニーのキャラクタたちは、ポーズのたびに動きを止めることから脱していた。キャラクタはポーズにあたる部分をスムーズに動き、「オーバーラップ・アクション」と呼ばれる流れるようなアクションを産み出した。
(Gabler "Walt Disney: The triumph of American Imagination" Ch. 5, 細馬試訳)
いやあ、おもしろいなあ。おもしろいでしょ? アニメーションの製作過程の話でありながら、ウォルトの熱しやすさも、スタッフの困惑ぶりも伝わってきて、実に血が通っている。おまけに、動きを描く技法の秘密まで詳しく明かされている。絶えざるバージョンアップのもたらす悲喜劇は、現在コンピューターで作業をしているわれわれの悲喜劇に通じている。
さて、長々と試訳してしまったが、この部分を邦訳『創造の狂気』の該当箇所と照らし合わせてみよう。『創造の狂気』では、わずか数行にまとめられている。
アニメの技法についても、ディズニーのスタジオは新しい方法を発案した。これまでのアニメ映画では、スクリーンに映し出すまでその動きが把握できなかったが、完成した絵をポジフィルムに焼き付けていき、開発されたばかりのムービオラという映写装置で縦横10センチの小さな画面に映すことで、大体の動きがつかめるようになった。これをアニメーター全員でチェックして分析し、キャラクターや背景ができるだけスムーズな動きを示すよう描きなおしていった。
これは「ペンシルテスト」と呼ばれ、またこれを利用して映像をオーバーラップする技法も開発され、ほかのプロダクションの作品にはないスムーズな動きを演出することができた。
(『創造と狂気』p186 太字は引用者による)
なぜこんな要約になってしまったのかはわからないが、とにかく、ことごとく間違っている。原文によれば
・ペンシル・テストは、「完成した絵をポジフィルムに焼き付けて」いくものではなく、ラフを安いネガに焼き付けて行うものであった。
・ムヴィオラは「開発されたばかり」とは書かれていない(実際それは1924年には発明されている:http://en.wikipedia.org/wiki/Moviola)。
・彼らはそれを「アニメーター全員でチェックして分析し」たわけではない。狭い「取調室」で、最初の頃は場面担当の一人のアニメーターが、ライカ・リールズができてからは数人のアニメーターがウォルトの厳しい目にさらされながらチェックをした。
・ペンシル・テストによってもたらされたオーバーラップ・アクションとは「映像をオーバーラップする技法」(それは「クロスディゾルヴ」である)ではなく、アクションどうしがいちいち立ち止まることなくオーバーラップするかのような、スムーズなアニメーションを指す。
ちなみに、今回の引用箇所のあとには、キャラクターにとっての「重力」の話など、現代のアニメーターにとっても興味深いであろう話が続くのだが、それもばっさり省略されている。うーん。
いや、この原作は確かにとても分厚い。コンパクトで読みやすく訳せば、より多くの読者がつくと考えたくなるのは、わからないでもない。けれど、わたしにはおもしろいと思える部分が、なぜか次々とこんな風に省略ないしは要約されているので、残念無念なのである。だって、訳されていれば、誰かと「あそこのあれ!」って話ができるじゃないですか。うーん。
彼の地では分厚い原作が、「巻おくことあたわざる page-turner」「ゴシック!」と絶賛され、ベストセラーになっている。それは、本書の細かい記述が、単なる些事ではなく、ウォルトとアニメーターたちのいきいきとしたやりとりとして書かれているからだろう。ウォルト・ディズニーの熱狂に翻弄されるアニメーターたちの悪戦苦闘ぶりと、そこから奇跡のように産み出される新しいアニメーション表現の数々は、ここにあげたような細部を通して初めて明らかになるように思う。
20101001
今日から後期講義開始。学生もまだ調子が上がらないのか眠たそうである。眠たいところを恐縮だが、質問紙調査について簡単にレクチャーする。今年度は浦田さんにも手伝ってもらうのでいろいろ変更点が出るかも。
to the Beach
contents