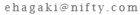The Beach : April 2008
Hiromichi Hosoma
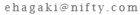
<<前 | 次>>









ハンドメイド豆本(ハガキの半分の大きさ)、管の歌は、ガケ書房@京都、Lilmag storeにて。
dotimpactさん作のRSSを使って、この日記を快適表示!→詳しく
ライブのお知らせ
5/17(土)@吉祥寺バウスシアター かえる目+「とんかつ一代」上映
20080430
さまざまなネガティヴ三角食べを試みる(あれをやりたくないときはかわりにこれをやり、これをやりたくないときにはあれをやり・・・)ものの、はかどらず。まあそういう日もあり。
白夜書房より「失われた時をもとめて」コミック版第一巻。第二巻にホテルの絵はがきを提供したので、その謝礼代わりにいただいた。第一巻で頓挫していた、失われた読書を取り戻すことができるかどうか。
20080429
花男論メモ(松本大洋論)
以前、ユリイカに書いたときにつけた模写とメモをbccksにしました。
ユリイカにはもっと長い文章を書いたけど、ここでは、模写とメモに語らせてみた。
http://bccks.jp/bcck/13340
山川直人「コーヒーもう一杯IV」
山川直人の漫画は、とてもオーソドックスなように見えて、いつもこちらの予想と少しだけ違うところに着地する。つい、何度も読んでしまう。
たとえば、第四巻の冒頭「歌のある街」は、街を行き交う人々の運命を交差させながら淡々と進んでいく、わずか16ページの掌編で、オチらしいオチはない。
なのに読み返してしまう。
変転する人々と街、その街の石畳がカーブを切るあたり、街路樹のたもとに、コーヒーの空き缶がひとつ、置かれている。どういうわけか、空き缶は、誰に捨てられることもなく、ずっとそこにある。
コーヒー缶は、奇跡のような幸運さによって人の目から免れてはいる。とはいえ、幸運を享受するにはあまりに空虚な存在だ(だって空き缶だから)。缶の底で乾いてこびりついた飲み残しのように、空き缶はただ、街にこびりついているように見える。
物語は、幾人かの成功と転落と別れを描いて終わりにさしかかる。別れを経た一人の女性が、カーブをコツコツと歩いていくと、ふと、空き缶が目に入って足を止める。空き缶がアップになる。
どうなるのか、と思って次ページをめくると、通りを俯瞰するページ一面に、彼女の足音がコツコツと響いている。
え、と思って隣のページに目を移すと、そこは違う話の始まりになっている。ということは、このコツコツが、どうやら終わりらしい。
なんだかキツネにつままれたようだ。
キツネにつままれたようだが、何かがひっかかる。ちょうど、缶の底にへばりついて出てこない、コーヒーの一滴のように、何かが意識の底にこびりついている。
足音とともに立ち去りつつある彼女の意識の底にも、何かがこびりついているのかしらん。
と考えて、また読み返してみる。
20080428
一日よく働く。
20080427
そういえば、イヤミは、穴あきの靴下でも、背広を着ていたなあ。
指さしをまなざす視点
先日、西阪さんとタクシーで話したことを、こう言い換えてもよい。
わたしたちは、ことばとジェスチャーによって、相手の語るモノだけを受け取るのではない、相手の語る視点ごと、そのモノを受け取るのである。
20080426
原稿を書く。駱駝で昼飯と夕飯。近くの古本屋で買った岡谷公二「アンリ・ルソー 楽園の謎」(中公文庫)を読み出したら、ルソーの絵をしげしげと見たくなり、また古本屋に行って画集を買ってくる。春とはいえ、夜は肌寒い。
コートを羽織って
「On the sunny side of the street」という曲の歌詞を初めて見たのは中学のときだったと思う。父親が昔買った歌集に載っていた歌を、英語の辞書を首っ引きで訳しながら、なんだかヘンな歌だな、と思ったのを覚えている。
「コートをつかんで、帽子をかぶって、悩みは戸口に置いてゆけ」
どこがヘンかと言えばそのあとの歌詞はこうなのだ。
「たとえ一文無しだったとしても ロックフェラーのように大金持ち 黄金色の埃が足下に舞う 陽のあたる側 大通り」
一文無しなのに帽子とコート?
そのときは、冬のNYやシカゴがどんなに寒いか、などということは考えたことがなかったから、コートの切実さには思い至らなかった。しかし、それにしてもなぜ帽子まで?
そんなぼんやりした考えを、扉野さんの「ぼくは背広で旅をしない」で久しぶりに思い出した。あの歌の歌い出しに顕れるコートと帽子は、もしかしたら「背広感覚」ならぬ「コート感覚」なのかもしれない。
ランディ・ニューマンの「サイモン・スミスと踊る熊」を思い出した。あれは、「コート感覚」の啄木的屈折なのかもしれない。こんな歌い出しだ。
「明日は外に出ようかな コートを借りることができたらだけど」
20080425
背広なき旅人 -扉野良人『ボマルツォのどんぐり』晶文社-
「ぼくは背広で旅をしない」という文章が収められている。昔、扉野さんsumusに書いた短い随筆だ。
啄木の「あたらしき背広など着て 旅をせむ しかく今年も思ひ過ぎたる」という歌を読んで、扉野さんはそこに顕れている「背広」感覚に注意を向ける。
朔太郎も背広を着る、という。「せめては新しき背広をきてきままなる旅にいでてみん。」ほんとだ。
どちらも有名な一節ではある。しかし、彼ら詩人の旅心に思いを馳せるとき、そこに寄る辺なさを感じることはあっても、その寄る辺なさが「背広」を羽織っているとはついぞ気づかなかった。
ふらりと旅に出よう、というときに、明治生まれの近代人にとって、旅には背広という構えが必要だった。それは、気取りのないカジュアルな格好で出る現在の旅への構えとは大きく異なっている。そのことを、さりげない文章で悟らせる。
こいつは一本取られた。
旅を、ただ抽象的な旅として捉える読み手は、そんなことには気づかない。本のさりげない一節を読みながら、旅を思い立つ瞬間、旅支度の不安、いざ外に足を踏み出そうとするときの構えが、扉野さんの身体に湧いてくるということなのだろう。
じっさい、扉野さんは、本を読んで旅に出てしまう。「背広で旅をしない」というくらいだから、これといったあてもなかろうと思うのだが、あてもないのにとりあえずは出てしまう。そして、あてどない旅先で、なぜか、拾いモノをしてしまう。
ボマルツォ、というのは渋澤龍彦の旅行記に出てくるボマルツォの怪物庭園で、扉野さんはローマからバスを乗り継いでその庭園にはるばる出かけていく。はるばる行くくらいなのだから、その奇怪な怪物オブジェの数々について熱っぽく語るのが世人のふるまいだと思うのだが、どうもそういう話ではない。バス停で出会った気の利かなそうな老人が出てきて、このなんということのない老人が、なぜか思わぬ拾いモノのように、こちらの気にかかる。
扉野さんは、この庭園でどんぐりを手に入れる。地面のどんぐりを探すが、そこにどんぐりはない。しかたないなと思って見上げた木の枝先に、まだ青いどんぐりが生えているのに気づいて、それを持ち帰る。
狙ったところから、少しずれたところに見つかるものがあって、扉野さんはどちらかというと、そのずれたところの方を書き留める。読むこちら側も、そちらの方が、なんだか旅らしいなと思う。
持ち帰ったどんぐりは乾いて、実が内側で皮から剥がれて、からからと音がするようになる。なぜ出会ったのかわからないできごとが、長い時間をかけて音を立てる。
夜、ZANPANOで、その扉野良人さんの「ボマルツォのどんぐり」出版記念ライブ。
大阪の児童詩雑誌「きりん」で長らく絵と編集に携わった浮田要三さんが来られていた。扉野さんは長らくこの「きりん」の本を作ることに関わっている。「ぼくのtruthと、扉野さんのtruthは、合うんです」。晶文社の中川さん、sumusの林さんもじつにうれしそうに挨拶を述べておられて、扉野さんの人柄のよさが伝わってくるようだった。
扉野さんが詩をつけたという曲を、坂巻さよさんと佐藤さんのデュオでやったのだが、二人の端正な演奏に吸い込まれるように聴き入った。そして歌詞。いやこれはすばらしい作詞家の才能を見てしまった。いつか、扉野さんの歌を街行く人が口ずさむ日が来るだろう。
かりきりん(下村よう子・宮田あずみ)の自在なきりんの翻案(小3の詩があんなになまめかしくなってしまうなんて!)楽し。下村さんが人前で歌っているのを見たのは何年かぶりだったが、前よりずっと歌も体の使い方も切れがよくなっていて、びっくりした。
気持ちのいい夜。
20080424
情報室メンテ、ゼミ、講義、ゼミ。東京人の書評原稿。
20080423
コントロール@京都シネマ
ジョイ・ディヴィジョン、イアン・カーティスの伝記映画。モノクロの画面にやけに凝った構図のシーンが多いなと思ったら写真家出身の監督だった。
「She lost control 」という過去形を「She's lost control」という現在完了形に書き直して、眼前のできごとと化すところとか、あの「シュッシュ」という音はスプレーで出してたんだ、とか、ジョイ・ディヴィジョンを飽きるほど聞いてた(が、文章としてはまるで読んでない)者にとっては目ウロコ多し。初めてのライブの直前に、みんなが緊張している中、スティーヴン・モリスだけが(あの特有のドコドコリズムで)スティックの練習をしていたりとか、ラジオ放送用に「transmission」が流れたりとか、イアンのスローモーション競歩のような踊りがかなりそれらしく再現されていたりと、いろいろたまらん。
淡々とイアンの半生を綴る筋立て。彼の歌詞を主として結婚問題から描こうとしているのは、奥さんがco-producerに入っているからかもしれない。良いとか悪いとか言うより「いたたまれない」映画。
大友良英+アクセル・ドゥナー+ マーティン・ブランドルマイヤー+Sachiko M カルテット@urbanguild
これはすばらしかった。
ブランドルマイヤーのドラムは初めて聞いたんだけど、「なんでこの小さな音量域でこれだけはっきりニュアンスが伝わるのか?」と驚嘆する場面多し。音量は普通のドラマーの1/10、しかしコントロール力は10倍、という、白色矮星のような演奏。
もうひとつ驚いたのは、メンバーの誰がどの音を出してるのかがあちこちわからなかったこと。ひとつにはPAの腕がよくてバランスが絶妙だったからだと思うんだけど、もうひとつには、即興なのにタイミングがあまりに絶妙だから、ということもある。音数が切り詰められていてハズシがほとんどない。いや、即興なのだから、ハズシもアタリもないはずなのだが、なぜかここぞというところで音が鳴る。一人の人間があらかじめこうしようと思ってやらなければ、このタイミングでこの音は出ないだろう、というところで、どう考えても二人以上の音が鳴っている。かといって、譜面にその音が書いてあるとも思えない。うーん。サイン波はSachiko Mのはずなんだけど、それも、ブランドルマイヤーが弦で擦ってるシンバルかもしれないし、立ち上がりのブチっという音は大友良英かもしれないし、うーん、誰なんだ。そしてこの空調だと思ってた音はアクセルなのか。うーん。
あと、なんだかすごく気に入ったのは、ブランドルマイヤーのシンバルが二つ、重なるようにセットされてたこと。この、二つのシンバルの触れ合う音がすごくいいんだなあ。
そそくさと帰って仕事。
20080422
かえるさん+江崎將史 (tp)
細胞文学、ラブラブスパーク、かえるさん+α、と、さながら「春の繁殖まつり」のurbanguild。細胞文学黒田さんの泣かせるアルペジオ、ラブラブスパークのすこーんと抜けた演奏のあとに、私こと、かえるさん登場。今回のお相手は江崎さん。
なかなかフルメンバーが揃わない「かえる目」、最近は「科」「属」「さん」のライブが多いのだが、けっこう楽しい。
歌謡曲やニューミュージックは基本的に、アレンジと歌とがセットになっている。たとえバンドの楽器数が違おうとも、基本的には同じアレンジ、同じリズム、同じオカズを目指そうとする。あえてアレンジを変えるときは「○○バージョン」などと断ったりする。
かえる目は、やってる曲の調子はユーミンであり、ほとんど歌謡曲だが、アレンジが毎回違う。演る相手によってまるで変わってしまう。バージョンというなら、毎回バージョンだらけ。
江崎さんもぼくも昼間は仕事。打ち合わせは、本番30分前の午後七時。江崎さんが聞いたことすらない曲多数なのだが、あいにく楽譜はない。「いいことを思いついたっていう音なんだけど、何がいいことなのかはよくわかってない、くらいの感じで」「夢のしくみをぱきーんと変える機械があるとして、その駆動音で」「大島弓子の『夏の終わりのト短調』に出てくる豆腐屋のラッパの音で」などと、雲をつかむような説明で打ち合わせ終了。
ステージ上で共演者に「この曲きいたことないんですけど」と言わせていていいのか。それでも曲として成立するのは、江崎さんの長きにわたる即興経験のたまものなのだが、それはさておき。
「女刑事夢捜査」(2008年4月22日@urbanguild)
http://12kai.com/kaerumoku/onna_keiji080422.mp3
「のびたさん」(2008年4月22日@urbanguild)
http://12kai.com/kaerumoku/nobitasan080422.mp3
聞くたびに違う「かえる目(ときどき科、属、さん)」、次回ライブもお楽しみに。
対バンのラブラブスパーク長谷川さんが、昔住んでたところのご近所におられることがわかり、あれこれ話す。
20080421
Perfume "GAME" もしくは貧血と観測(マカロニ篇)
「マカロニ」は温度の歌だ。
「見上げた空は高くて だんだん手が冷たいの」と、早くも貧血少女は体温の危機にさらされている。危機にさらされているにもかかわらず、「暖めて」というのではなく、「キミの温度はどれくらい?」と聞いて手をつなぐのである。まるで高熱でうなされながら相手の平熱を測ってやるようなケナゲさである。泣かせるのである。
いやまて、もしかすると、このヒトは、自分の手が冷たくなることはわかっても、それに快不快を感じることができない存在かもしれない。このヒトはもしかして、ヒトではなく機械なのではないか。
しかし、機械にしては、何度もワタシに同意を求めるのである。
「ポリリズム」が「だね」から「だ」の歌だとすると、「マカロニ」は、「よね」の歌だ。
「いいよね」「やわらかいよね」「いつまでもいたいよね」「ちょうどいいよね」と、語り手は次々と控えめな同意を求める。同意を求めれば求めるほど、同意を求めずにはいられない不安が透けて見えるのである。じっさい、不安どころか「わからないことだらけ」なのである。しかし、なぜか安心できるのである。大切なのはわかることではなく、コントロールなのである。機械以上平熱未満。それくらいのかんじが、たぶんちょうどいいのである。
それにしても、この歌でもっとも謎めいているのは、タイトルを含む以下のフレーズだ。
「あきれた顔がみたくて時々じゃまもするけど 大切なのはマカロニ ぐつぐつ溶けるスープ」
なぜ、大切なのは、マカロニなのか。マカロニくらいのやわらかさと温度が重要だと言いたいのか。だとしたら、ぐつぐつ溶かさないほうがよいのではないか。なぜアルデンテではないのか。それとも、マカロニはマカロニとして置いておき、スープは別に作っているのか。だとしたら、ここでぐつぐつ溶けているのはなにものなのか。そして詰まるところ、何がどう大切なのか。
さらに謎めいているのは、冒頭で「見上げる空は高くて」と歌われているように、この歌が、どうも戸外を基調としているらしいことである。だとしたら、この、ぐつぐつ溶けるスープはどこで眺められているのか。戸外で鍋を囲んでパーティーでも催しているのか。
いや、マカロニはおそらく、ビデオクリップに挿入されたカットのような、一瞬のイメージショットに過ぎず、かくべつ戸外とは関係ないのだろう。
それが証拠に、「よね」だらけの歌詞の中で、この部分だけが体現止めだ。
かつて井上陽水は「都会では自殺する若者が増えている」という新聞記事をくつがえし「だけども」と歌った。「だけども問題は今日の雨 傘がない」。
社会問題よりも恋人との関係を優先するその歌詞には、当時中坊だったわたしですら衝撃を受けたと記憶している。が、よくよく考えてみると、この歌は、何も世間を無視しているわけではない。少なくとも、記事のありかは「今朝来た新聞の片隅に」捉えられている。今朝という時間があって、記事を「片隅」と見る語り手と新聞とのあいだには、確かな距離がある。
「傘がない」の確かな時空間に比べると、「マカロニ」という歌の淡さがよくわかる。ここでは、もはや、社会対個人というような対比によって今が歌われることはない。そもそも新聞もテレビもなければ、呼びかける者と呼びかけられる者以外の姿も見あたらない。
「けど」ということばでくつがえされるのは、「あきれた顔がみたくて時々じゃまもするけど」という自身の行為である。行為をコントロールし、温度を保つこと、そのバランスがひたすら目指される。
しかしそのバランスさえも、「安心できるの〜」と伸ばされるや否や安定を失い、貧血に出会ったように遠く下降していく。再び貧血少女の危機なのである。
「最後のときがいつかくるならば」とは、これまでの語り手が言おうとしているのか、それとも貧血少女の見た夢なのかはわからない。ともあれ、このあまりにはかないフレーズは、アイドル自身のはかなさを言い当てるかのように際どい。とても恐ろしくてアイドルの声では唄えそうもない。
しかし、そのきわどさが危うくかわされているように聞こえるのは、その声が、彼女たち自身の声から変調されているからだろう。生身の声を消し、変声された声をあてがわれた彼女たちは、このかつてない希薄な歌詞世界を、アイドルとして生き延びている。そしてその希薄さゆえに、「それまでずっとキミを守りたい」と思わせる。
「マカロニ」のPVは8mmカメラで撮影されているように見える。ときおり露出過多で撮影された普段着の彼女たちの姿は、粗い粒子となって揮発せんばかりだ。
大本彩乃はこの映像が撮られつつある時間をなぞるように、彼女の年代には似つかわしくない、Fujicaの古いカメラを構えている。撮っている側も撮られている側も粗い8mmの世界である。
別々に撮影されていた三人は、やがて川辺に集い、手をつないで踊る。
手をつないで踊る場面を見て、マリアンヌ・フェイスフルの「Witch's song」のPVを思い出した。デレク・ジャーマンの撮ったそのPVの中で、どこからともなく集った魔女たちは荒涼たる高みで手をつないで踊る。そこは明るい真昼で、魔女たちは手に手に鏡を取り、あちこちから太陽光を反射させ、明滅する合図をこちらに送る。8mmカメラで撮影されたその光は粗い粒子となって見る者の眼を射た。
「マカロニ」PVの光は柔らかい。おどろおどろしい魔女の世界はアイドルには似合わない。おそらく、これくらいのかんじがちょうどいいのである。わたしは、ちょうどよくないくらいのほうがいいのである。だから残念ながら、このビデオを見て涙を流したりはしないのである。でも、この徹底した希薄さに、ぐっとくるかんじは、なんとなくわかるのである。曲間のトークに入ったときの、三人の意外に押しの強い生声を聞いて、ああ彼女たちも生きていたのかと、奇妙な「安心」さえ感じてしまうのである。
最初はメンバーの名前にちなんでつけられたという「Perfume」というグループ名は、いまや、空気中で希薄になっていくその存在を名で表すかのようだ。
「ってどんだけ?」「ツンデレーション」といった、いかにも消費期限の短そうなフレーズをあえてちりばめた歌詞になぜか違和感が感じられないのも、それらが時流に乗るためのことばではなく、むしろ、この現在がはかなく消えてしまうことのしるしだからではないだろうか。
「ポリリズム」でも「マカロニ」でも、歌は、機械的で温度のないこの世から身を引き剥がし、体温を得ようとする。しかし、引き剥がされた声に、確かな温度があるわけではない。声は、エコーとなり遠く下降しながら、引き剥がした身の置き所さえも揮発させていく。変化だけのある世界を言祝いでいるようでいながら、じつはこの希薄さを支えてあげたいと想う人情を誘っている。
それにしても、みんな、「マカロニ」にでてくるのがどんなスープだと思って聴いているか。
20080420
Perfume "GAME" もしくは貧血と観測(ポリリズム篇)
むかしよく貧血で倒れたころ、「ああ、これは気を失うな」とわかる瞬間が、意外に心地よかったのを覚えている。お笑い芸人が階段でつまずきながら用意周到に体の向きを調節するように、薄れ行く意識の中でかろうじて、前後にばったり倒れて致命傷にいたるのはかろうじて避けようとしている。自然と、体は頭を守るように足下から崩れて、その場にへなへなと崩れるような格好になる。
貧血の刹那、一瞬の観察の中で、意識は、その場に垂直に崩れていく自分からのささやかな幽体離脱を試み、我が身の外から我が身が安全にくずおれる様を見守る。
PerfumeのGAMEを聴きながら、その、貧血の一瞬を思い出した。
過去、さまざまなアイドルが愛や恋を歌ってきたが、これほどまでに抽象的な歌詞を歌うアイドルはいなかったのではないだろうか。モーニング娘。がかつて熱をもって「ニッポンの未来」を鼓舞したことは、ここにいたって完全に遠い過去に葬られた感がある。
中田ヤスタカの書く詞には、内容らしい内容がほとんどない。
『ポリリズム』では、ぼくやキミの「気持ち」や「想い」や「衝動」や「感動」が盛んに歌われるものの、「とても大事な」はずの中身は歌われない。わたしは長いこと「反動」を「反応」と聞き間違えていたことにCDを買ってから気づいたが、それでもこの曲の印象はまったく変わらない。
もちろん、コンピューターシティでplastic smileでセラミックガールで、変質させられた声とぎくしゃくとした振付をあてがわれている彼女たちは、あらかじめ機械的な演出で売り出されているのだから、抽象的なのは当然ではある。しかし、それだけではない。
「行動」や「衝動」や「感動」は(「反動」と「反応」がそうであるように)取り替えの聞く便宜的なことばに過ぎず、極端に言えばXやYでもよい。
歌われているのはむしろ、「行動」や「衝動」や「感動」が「うそみたい」になったり「繰り返し」たり「よみがえる」ことである。感覚の内容ではなく、ある感覚から別の感覚に移動することだけが歌われている。
となると、どうやら歌詞のポイントは、機械らしさそのものではなく、むしろ移動すること、機械らしさからわずかに身を引き剥がすこと、体温がないことではなく、体温を取り戻すことにあるのではないか。
たとえば、「ポリリズム」という変則的なリズムにはさほどぐっと来ない音楽ズレした大の大人も、「ああプラスチックみたいな恋『だ』」というフレーズには少なからず心動かされる。少なくともわたしには、この「だ」という言い切りとともに、フラフラと Perfumeファンに落ちていった数万の群衆が見える。
「まるで恋だね」「うそみたいだね」と、それまでは何度も親しげに問いかけてくる「だね」が、突然「だ」という叙述に変わる。「ああプラスチックみたいな恋『だ』」。そのときに何が起こるのか、しばらく考えてみよう。
「だね」という語尾は、相手となんらかの体験や知識を共有しているときに用いられる。しかし、中身のわからない「衝動」を、自分ならともかく他人は「あの衝動」と指すことはできない。他人同士で共有できるはずもない。
そこをあえて「だね」というのだから、この相手は少なくとも他人ではない。かといって、自分ではない。では誰なのか。このような「だね」は、語り手である自分と、聴き手である自分を分裂させて、わたしの中にもう一人のわたしを作り出す。ここにはいない、もう一人の自分が生み出され、わたしはここにはいないわたしに「だね」と言い聞かせる。
とはいえ、このような、わたしならぬわたしに宛てた「だね」や「よね」といった使い方は、かつて小室哲哉の歌詞にもよく見られたもので、そのこと自体はさほど珍しくない。
むしろ珍しいのは、「だね」という呼びかけの連続が、突如「だ」と、叙述に裏返るところだ。
それまでは自分と自分ならぬ者との間で親しく会話を行っていた者が、突然、その関係から身を引き剥がす。自らを叙述の対象として、冷徹に見下ろす観察の視線を得る。
言葉遣いだけではない。ここまで律儀に拍に合わせて歌われてきた歌は、「恋だ」と歌うとき、「こ・い・だ」とぎくしゃく歌われるのではない。「こ」から「い」に移るとき、メロディは母音の「o」と「i」の間に潜り込み、拍から解放されて「こぉぃだ」と人間らしい響きをまとう。すると声には突然エコーがかかって、三人の「恋だ」に分裂する。それまで伴っていた倍音は失われ、遠く生身の声を響かせて消える。
プラスティックな関係から微かに生身の感覚が「よみがえ」り、自らを観察する。そのときだけ、自分が生身に帰るような気がする。まるで貧血みたいな恋だ。
しかし、ようやく観察眼を得たかに見えるこの束の間の生身感覚は、それこそ「ポリリズム」によってはかなくも分断されてしまうのである。
彼女たちの歌の淡さは、単にこの世の淡さではない。この世から離脱した先もまた淡い。離脱という変化だけが、繰り返し演じられる。作者はそのことを十分自覚して、狙っているらしい。拍の密度を上げては解放し、浮遊感を繰り返し演出するアレンジにも、同じ現象は表れている。
20080419
長谷川健一BOX SET発売記念ライブ@ガケ書房
ガケ書房に行くと、いつもは雑誌が縦に指してある棚に、ずらりとBOXセットの箱が並んでいる。それも、一箱一箱、違う生地で布張りされたもの。この生地はハセケンのお父さんから提供されたものだという。
凹凸のある布地には、さまざまな手触りがあり、見る角度によって柄の見え方が変化する。どれにしようかなとしばらく迷ってから、草花のあいだを天の川がもくもく流れるようなのにする。傾けると顕れる花、隠れる花。着物だと、こうしげしげと生地を傾けて眺め続けるわけにはいかないが、箱だから遠慮はいらない。085/200。
ライブは言うまでもなくすばらしい。眼をつぶって聞くと、まるで自分の身体が鳴っているよう。新曲の『何処かへ』。「世界はいま何処かへ ぼくを越えて何処かへ」すごい歌詞だなあ。
終演後の抽選で、いきなり番号を呼ばれてびっくりする。次に当てたのが隣に座ってた伊達伸明さんだったのでさらに驚く。二人のおっさんは、はせ犬トートバッグを手に入れた。かわいいなー、はせ犬。
20080418
アールブリュット/交差する魂@NOMAミュージアム
京芸センターチームと近江八幡で待ち合わせ。作品制作のために京都にいるロイック・ストラーニさんも。彼のお父さんはEnrico Sturaniという、絵はがきコレクターで、宮武外骨についての論文を書いているという。
NOMAの展示はちょうどいい規模だなと思う。見ていて集中できる時間の分量だけ作品がある。
ローザンヌのアール・ブリュット美術館にはずいぶん前に行ったことがあるのだが、その頃は、ヘンリー・ダーガー目当てだったこともあって、あまり他の作品に注意していなかった。が、ここで改めて見るとおもしろい作品が多い。
たとえばWillem Van Genkというオランダ生まれの作家の作品。絵はがきやパンフレットから取ったらしい題材なのだが、遠くから見ると目もくらむような細密画で、どうやって書いたのかわからない。それで近くによってみると、絵のあちこちにでこぼこがあって、これは自身の絵が切り貼りされたコラージュなのだなと分かる。
さらに裏面に回ってみると、旅先のパンフレットやチケット、広告のコラージュになっている。絵の構造が裏面のコラージュによって決まっていたりする。これはすごいなあ。
今回の展示は、ローザンヌのコレクションが半分、日本からのコレクションが半分くらいなのだが、とりあげられている作風に少し傾向の違いがなるなと思う。
ローザンヌの方は、なんというか、出来上がったヴィジョンの世界観を重視しているというか、図像をどう読み解くことができるかという点を重視している感じがある。それに対して、日本の方は、必ずしもヴィジョンの特異さにはこだわってなくて、むしろ、繰り返しや作業の積み重ねがもたらす抽象性を重んじているように見た。
帰りにたねやに寄ったら店員に、せんせい、と声をかけられた。が、すぐに名前が思い浮かばない。あ、あの、と息をのんで口ごもる表情ではっと思い出す。表情の記憶は、空気を変えるように生々しい。
帰ってから、その教え子にもらった日牟禮餅を食べる。するすると口溶けがする。不思議な味だ。
20080417
風船モデルのようなジェスチャー
今年も木曜日は多忙になりそうな予感。院生ゼミ。高知県のジェスチャーをする人々。井上京子さんの論考と合わせて、おもしろい事例になりそう。とくに、あらかじめ作られたマップが、あとから完全に配置転換してしまう例。あたかもソシュール>丸山圭三郎の風船モデルのように。
のぞき込みと断念
藤本さんによるチンパンジーののぞき込みデータをブラウズしてもらいながら、里ウエストと分配のあいだを考える。チンパンジーは、何かを食べている他の個体をしばしばのぞき込む。それも、人間のようなちらちら見るのぞき込みではなく、ときにはほとんど対面に回り込んで、ドリフのコントのように露骨にのぞき込む。これだけ見られたら、思わず食っているものを分配してしまいたくなりそうなものだが、ほとんどの個体は、のぞき込まれても動じない。結果的には、のぞき込んだ個体は相手の手元から少し食べ物をちぎったり、おこぼれを拾ったりする。食べている側から積極的な分配は起こらない。
この、異様なまでの分配の欠如は、チンパンジーとヒトとの間にあるルビコンを感じさせる。黒田末寿氏が「人類進化再考」で以前書いていたように、断念の表情の有無や、チンパンジーの他個体に対する推測能力が問題になってくるだろう。
院生、四回生と月曜日の実験の準備。そのあと兼広で慰労会。鶏鍋がうまい。
20080416
今年は三回生だけでなく、新四回生とも個人面談をやっている。短い面談だが、卒論への構えが聞けて、就活のよもやま話も出るので、なかなかおもしろい。「え、そんな職種をめざしてるんだ?」というような人も。
20080415
講義。三回生のゼミ相談。会議。原稿。
20080414
朝、村山さんと移動しながら四方山話。京都駅で新幹線に乗る村山さんと別れて彦根へ。
倒れかけレッスン
気が付くと、演習にこのレッスンを取り入れて三年目。今年はあまり余計な要素は入れず、人数を増やしながら、その感覚の変異に注意してもらうというプログラムにする。最初は三人(倒れる人・受け止める人・観察する人)、そこからだんだん、受け止める人の数を増やしていく。「観察する人」を入れるところがミソ。
フィールドノートを書きまくる
演習のはじめに、フィールドノートの書き方について話す。
ノートと、レポートとは違う。
レポートは他人に読んでもらうためのものだ。体裁を整えて、結論までのショートカットを見通しよく書く。
ノートはそうではない。ノートは、未来の自分が思い出すためのものだ。思いあたるための体裁があればよい。
アイディアは箇条書きではやってこない。アイディアを真空パックするためには、レイアウトを大胆にとること。端からちまちま書くのではなく、見開きの画用紙を渡されたと思えばよい。これは鍵だと思ったことを好きな場所に書く。ことばにならなかったら絵で描く。何か関係あることを思いついたらそこに矢印を入れていく。最初は想定していなかった中心が別にできたなら、そこにも矢印を入れていく。ページはケチらず、どんどん書き込むこと。何冊でも書くこと。
・・・とけしかけても、最初はなかなかページが埋まらない人が多いので、こちらから「この一テーマで四ページ!」などと指定する。
倒れかけをやるたびに、ノートをお互いに回覧してもらう。お互いに、これはいいと思った書き方はどんどん取り入れてもらう。
見たこと、思いついたことをできるだけ鉛筆の速度にのせること。まずはそれを覚えてもらう。
20080413
京都芸術センターの松村さんと話。今年の秋の企画についてアイディア出し。
松村さんは、20世紀の終わりにHOSEの彦根ライブを目撃している数少ない一人である。開学間もない滋賀県立大でビッグバンド部を立ち上げた彼女は、卒業後NYに渡り、アートマネジメントの勉強を始めた。ちょうどセントラルパークで「ザ・ゲート」をやってて、一緒に見たんだっけ。
その後、勉強を終えて帰国し、めでたく京都芸術センターの学芸員となった。かつて彦根の雑居ビルを改装したスペースでサックスを吹いていた松村さんとNYで会い、時を経て京都で芸術密談をすることになろうとは。月日というのは不思議なものだ。
urbanguildでFttari Festivalをちょっと見る。竹内光輝 +江崎將史+ 木下和重のセット(譜面をめくるタイミングと音)と、宇波拓、noidのセット(珍しく宇波オブジェクトがイケイケで鳴り続ける)を見たところでタイムアップ。shin-biに行ってリハ。カポと楽譜を忘れたことに気づきアパートに戻る。
かえるさん@shin-bi
会場を縦横に動きながら管弦打のやりとりをするサラミ&チーズに続き、かえるさん初のソロ。あいかわらず歌詞は何カ所か間違えたし、ギターにいたってはどうしようもない。が、ギターのどうしようもなさを引き受ける構えはやや向上したかもしれない。うまく弾く方向ではなく、出した音を聞き取る隙間を作る方向で。千住さんの、もやを吹き飛ばすような明快なドラム。ハイハットの音色が美しい。
終了後、再びurbanguildへ。村山さんと一緒に宿へ。道中、フランス即興シーンのことなどあれこれ話す。
20080412
花見
午後三時、アパート住人の花見の場所に行ってみると、藤棚の下で小さなコンロを囲みながら早くも飲む人々。ゆうすけくんの持ってきた直径三十センチほどの小さなコンロから、どうやら今日の食い物は生み出されるらしい。ゆうすけくんは毎週のようにこのコンロを使って外で食べているらしく、手慣れた手つきで肉や野菜に塩を振り、裏返す。できあがると、網ごと、どうぞ、と差し出してくれるので、そこからよく焼けているのを取って食べる。
塩の量が、じつに思い切りがよい。振っているときは、あ、振り過ぎかな、と思うくらい、ばっと振っているのに、食べてみるとちょうどいい。ゆうすけくんの決断力を食っているような感じだ。まさに「エッジが効いている」。
そのうち山本さんが来て、小山田さんが来て、日本酒がどんどん空き、にぎやかになる。
日が落ちて、小山田さんが二階の部屋の前に照明をつけると、桜が見事に浮き上がった。部屋の暗さと外の暗さがちょうど釣り合って、外から見ると、窓ガラスに映った桜の花が、あたかも部屋の中で咲いているように見える。桜キャプチャ。
20080411
サンセット・ゴールデン
何年やっても脱臼だらけの書類仕事をくぐり抜け、一日の仕事が一区切り、外に出ると一面の曇り空で、夕暮れどきの薄赤は天頂にあり、斜めに見通す雲の色は青を透かしてもくもくと水平線に向けて拍を刻む、これならスケベニンゲン、いやシュヘーフェニンゲンの海を見たゴッホならずとも、「世界には無限のグレーがある」。自転車を漕ぎながらみるみる失われていく色。暗い階調の中で濃くなっていく桜の色。いろいろえろえろ。
アイデア5月号
24組のデザイナーにそれぞれA4四ページをまかせた冊子が綴じられている。いや、これはむしろA3二ページの折り込みでは?
ともかく、そのA3の折りのためにわずかにふくらんでるところが、書店置きの他の雑誌にはない感じ。各誌を広げてみながら、ぼくはデザイナーに文章を手渡す側だから、手渡した先に待っている覚悟を見る思い。ますます緊張と弛緩を持ってテキストを手渡すしかない。
などと格好をつけてみたものの、戸塚泰雄氏の誌面に見える通り、渡すテキストは繰り返しとひっかかりだらけ。戸塚さんとしゃべったのは一時間くらいだったと思うけど、よくもまあこれだけ話が飛んだもんだ。戸塚さんお疲れさま。
拝借
そのアイデアの佐々木暁氏の誌面を見て、大友良英「2台のギターと2台のアンプによるモジュレーション」のジャケットを想い出す。
「2台の・・・」のジャケに使われているステレオ写真は、じつは拙蔵のステレオ写真を佐々木さんにどんとお貸しした中の一枚。でも、あんな仕上がりになるとは想像だにしていなかった。
ステレオ写真というのは、どんと飛び出す写真であるからして、しばしば「飛び出す」感が強調されやすいのだが、あのジャケには、そういう野心がない。ステレオ写真なのに、とても静かなジャケットになっている。ある素材が編集されている、というよりは、そこに盛られたものを見る態度が示されている。ここに写真がある。これを黙ってみてみよう。汚れもかすれも含めて。という感じなのだ。
同じ感じが、今回の誌面にも表れている。
佐々木さんの「拝借の彼岸」というフレーズがすごく気に入る。
そういえば、「ちょいとお耳を拝借」っていうなあ。あれは、耳を借りるだけでなく、耳のついている頭ごと借りて、そこに息を吹き込むのだ。ナイショの話はあのねのね、といいながら、借りたお耳を通して、相手の頭を鳴らす。ナイショ話を吹き込むとき、耳に添えられる手は、拝む形をしている。頭の拝み取り、いや拝み借り。あ、かえる目セカンドアルバム(まだ吹き込んでもいない)タイトルは、「拝借」でどうか。どうでしょう、小田さん。
20080410
会話する二人は剣豪のように
城さんと会話のなかのユニゾンを見るうちに、Lernerもびっくりの超絶コントロールの場面を見つける。
ディズニーランドのアトラクションの名前を想い出そうとしていた二人が「スプラッシュマウンテン!」と同時に声をあげる。じつは二人の発声としぐさは微妙にずれていて、それが最後の最後でどん、と同期するのだが、同期が達成するや否や(それは同期のコンマ1秒以下のちで、まさに「するや否や」なのだ)、二人は同時に体をそらせて爆笑する。あたかも剣豪どうしが刀を交えた瞬間にぱっと飛び退くように。こういう、意識の追いつかないほどのやりとりを見ていると、人の会話にはすさまじい速さのやりとりが横溢しているなと思う。
滋賀県立美術館の山本さんと浅井さんが来訪。秋のアール・ブリュット展でレクチャーをすることになった。とはいえ、美術史的に何か言えるような知恵はないので、人が描いている様を拝見しながら、あれこれ思いついたことを言うことになるだろう。
20080409
オリエンテーション。新入生の自己紹介を聞くと「お笑いが好き」という子がけっこう多い。もちろん、お笑いブームはずいぶん前からあったわけだが、新入生が自己紹介の中で、自分の趣味のひとつとして「お笑い」を挙げたり、好きな芸人名を挙げたり、というのは、これまであまりなかったように思う。
時間割微調整。その他書類もろもろ。
あ、もう朝日の次の原稿だ。週刊の〆切はあっという間だな。いつも、おおよそこれくらいかなと思って書くと、たいてい700字を越えていて、ことばを少しずつ刈り込む。刈り込もうと目を光らせると、けっこうダブついている表現がみつかるから不思議だ。ただ、刈り込みすぎると、息苦しい文章になるので、わざとなんでもない語句を投げたりする。
新四回生が集まってきてゼミ。
20080408
入学式。会議会議。
桜とアパートとシンメトリーでbccksをもう一冊作る。
(http://bccks.jp/bcck/13042)。
20080407
むっちり村
YouTubeに気になるアニメーションをいくつもアップしている谷口崇さんのwwwサイト。いやはや、どのアニメーションも、突き放し感がすごい。それが、フラッシュの切り貼り感とよく合っている。切り貼りされたキャラが動くだけのフラッシュは、ともすると手抜きとか狙いすぎたヘタウマ(古い)に見えがちなんだけど、この人のは、もうこの表現しかありえない、という感じがする。
そして、声の入りが妙にいいんだなあ。ぶつぶつ言ってるところと言い切るところの対比。歌もいいなあ。
20080406
山本精一『ゆん』(河出書房)
昨日買った『ゆん』を読む。夢の話、なのだが、その夢の鮮度が高い。なんというか、「取り立て!」なのだ。脳から取り立て!イチゴ狩りよろしくその場で夢を食ってる感触。獏も気づかぬ間に囓る。
デジカメで桜を撮ってたら、サカネさんが来たので、カメラをちょっとお貸しすると、ちゃっちゃっとツマミをいじりだす。ぼくはいつもすべておまかせのオートで撮ってしまうのだが、サカネさんは写真家だから、ちゃんと露光を調節しながらマニュアルであれこれ試すのである。その、カメラと格闘してるようなしぐさが格好いい。返してもらって自分でも撮る。真似してちょいちょいとツマミをいじる。さっきより上等のカメラになった感じがした。何枚か撮ると、ちょっと上手くなったような気もする。
デジカメもいいのだが、液晶ごしでは物足りなくなってくる。久しぶりにローライであちこち撮る。じつはずいぶん撮ってなかったのだ。一年前くらいのフィルムが入ってたんじゃないだろうか。変色してるかも。
カフェ工船でヨタ話。日曜らしい日。夜遅く彦根へ。
20080405
EMCA研究会@京大時計台ホール
朝一番の電車で京都へ。東山三条からアパートまでの道中、桜がどこも満開だった。今年は心の準備がないままに満開で、なんだかうろたえる。
早朝の疎水沿いを歩いて本日の花見終了。
世話人兼発表者なので、いろいろ忙しい。ホールについて会場設営。ゼミ生の御子柴さんにも急遽バイトに入ってもらう。
発表はどれもおもしろかった。鶴田さんの性別カテゴリーの話は、トランスジェンダーの「移行(トランス)」状態で、本人がどちらかの性別に落ち着くことを望む語りをすることに着目したもの。ただし、関東と関西ではこの点にはけっこう違いがあって、ごくおおざっぱに言うと、関西には移行状態を楽しむ気風があるのだという。
わたしはジェスチャー・データセッションについて。先日の合宿のバージョンアップ版(焼き直しともいう)。あとで甲南女子大の林先生とempathy論との関連であれこれとお話する。
川島さんの話は、基礎体温表を「つけてますか?」と聞く医者の話。「つけてますか?」と聞かれると、患者は「はい」と体温表を差し出し、「はい、じゃ拝見しましょう」ということになる。「つけてますか?」という表現が、体温表をその場で提出することをリクエストしている。
そういえば「宿題やってますか?」といいながら宿題の提出を求めるってのはあまりないなあ。
増田くんの話は、インタヴューデータを用いたwh表現の話。wh質問が、答えの候補を伴う場合に何が起こっているか。たとえば、「どういうことですか、ちょっと怒っているとか?」という風に。
打ち上げに出たあと、タクシー車中で西阪さんと短いが深いディスカッション。Kendonの「準備」というタームには、振り上げた手の位置じたいが持っている性質(視点や垂直位置など)が抜け落ちているのではないか、という問題。
『Presentation 23:山本精一「ゆん」出版記念イベント』
午後八時半と遅い始まりのshin-biの大友良英・山本精一デュオへ。フィードバックを多用した曲もよかったが、「終わります」といってとりあえずひっこんでからの、Cのフォークかブルースかという始まりからねじれていく展開がおもしろかった。フィードバックの音は、突然、ぽーんと理不尽なボリュームで鳴るときがいい。コントロール不能なものが挿入さえる感じ。
細川周平さんが偶然目の前にいらして、幕間、少しお話する。
山本さんに新著「ゆん」のサインをしてもらったら、すごい時間をかけて絵を描いてくれた。会場にはサインの行列ができて、その一人一人に山本さんは違う絵を描いている。
打ち上げで吉田屋。ものすごく久しぶり。途中から回文を考える会に変貌。むかし、パソコンで文字を打ちながら回文を考えていたときは、すごく長いのを思いついたものだが、ソラでやるとなかなか難しい。マジックナンバーの壁か。
深夜二時。その場の笑いを誘った数少ない結果は
「和民を見たわ」
だった。
20080404
明日の準備をいろいろ。朝日の原稿。
20080403
東京人書評バックナンバー
東京人に書いた書評バックナンバーを掲載。発売後1ヶ月以上経ったものを随時追加していきます。
ちなみに、いま発売の号では、大谷能生『貧しい音楽』、北里義之『サウンド・アナトミア』を書評しています。
いろいろ書類や役回り。気が付いたらとっぷり日が暮れていた。
部屋の本がえらいことになっている。ジャンプして椅子へ。棚は崩壊寸前。
本が崩れる、と言えば草森紳一氏。氏の訃報を見たのは、伊東の旅館の新聞だった。その前の年は、同じ伊東の旅館で、植木等の訃報を見たのだった。
books
20080402
ピナ・バウシュ「フルムーン」@びわ湖ホール
人の日記を見て今日であることを知る。あわてて琵琶湖線に乗って膳所へ。
でかい月の欠片のそばで水だらけ。助けようとして崩れ、その崩れる者を助けようとして崩れる、対の動き。オートマティックに動く者と、それを助けようとして報われない者。内周を走る男が外周を走る男の手をぶん、と引っ張るのがよかったなあ。これは援助なのか罰なのか。だとしたらどちらがどちらに?
全員が登場して水を浴び出すと、時間律は狂って、これまでの動きがあちこちで再生される。この時間軸の乱立には思わず身を乗り出した。最後はそれぞれが水場でソロを取る。速い速い。
20080401
始業式。笑い分析のゼミ。話し始めに起こる微笑をマイクロ分析。また、いままで気づかなかったタイプの笑いを発見してしまった。
to the Beach
contents