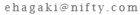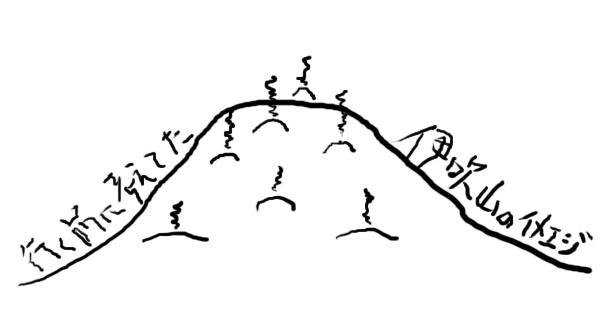The Beach : July 2009
細馬 宏通
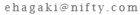
<<前月 | 翌月>>
tumblrを付けてみることに。付けてみると何かに気づくかしらん。
http://kaerusan.tumblr.com/
歌う:
9/5(土)音遊びの会@神戸
9/5(土)かえるさん@shin-bi
いずれも詳細はかえる目ホームへ。
20090731
伊吹山山頂へ
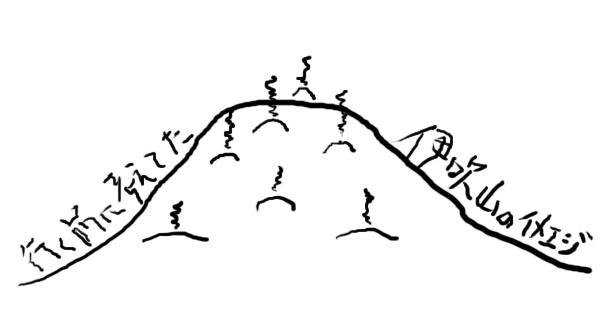
伊吹山と言えば、いぶきもぐさ。せんねん灸。というわけで、事前に抱いていたイメージは上図のような感じ。





霧の山道。アカソの群落。イブキトラノオ(白い花)。シュロソウ(六弁の花)。カワラナデシコの向こうは霧。
ずだ袋のようなカタマリの中から花をぼろぼろともらすシシウド。また行きたい。
20090730
ゼミに講義。スゴシゼミのあと、カメラオブスキュラを試す。琵琶湖岸が映りそうなよいロケーション。
えっとこのまえさー
会話のことばには、相手に特定の構えをおこさせる前置きがたくさん組み込まれている。
たとえば、何かを言い出そうとして「えっと」という。これは、単なる口ごもりとは限らない。会話のやりとりをよくよく分析してみると、相手のことばじりとこちらの言い出しがかぶっているときにしばしば「えっと」ということばが観察される。つまり、えっと、は、相手のことばの終わりかけたところをねらって、ここから自分の話す番が始まるよ、と予告する役割も持っている。相手は、ことばを終えながら、あ、次はこいつが話すのかと身構える。こうして、新しい話題をはなし、きくための、お互いの身構えが整う。
もし相手が身構えていなければ、さらに前置きを続ければよい。
えっと、このまえさー、なんていうのかな、とにかく。
文章では、逆のことをする。文章を読む人は、読み始めた段階で、すでにそのページやモニタに注目し、「文章を読む」という身構えをとっている。そこにさらに前置きをおく必要はない。たとえば
えっと、今日さー、歯医者に行ったんだけどー、
という語りだしは、文章にするとき、
歯医者に行った。
とする。相手の身構えにすっと入る。
もっともこの手の刈り込みをやりすぎると、鼻もちならない感じがしたりもする。たかが歯医者体験じゃないか。小説でも始めようというのか。そんな違和感を感じる場合は、少し前置きを足してみる。
えっとこのまえさー、歯医者に行った。
あ、いいね。
20090729
診察券の名前
久しぶりに行った病院で何年も前の診察券を出したら、帰りがけに新しい診察券をもらった。氏名欄にはすでに、それぞれの画の先が細く曲がって伸びた自分の名前が書かれていた。定期入れのクリアホルダに入れたのだが、開くたびにおばけを見るようで、なぜこんなおばけを毎日見ているのだろうと思う。
記号の骨
じつはwww日記は、ずっと自分でタグを打っていた。
改行のbrも表題のh1,h2,h3も全部そのつど指定して。それが習い性になっていたので格別面倒くさいとも思っていなかったのだけど、こうやって、テキストを整形するためのタグを打たなくてよくなってみると、妙にすがすがしかったりする。もうそういうのは人任せでもいいか〜。誰がデザインしたページでもいいか〜。
いいのだが、その一方で、失われたものもある。
デザインが気軽に変更されてしまうことで、テキストの純粋さは、より強調されるはずなのだが、どうもそうではない。
スタイルシートにせよ、ブログツールにせよ、このtumblerにせよ、これだけさまざまなデザインがあらかじめ用意されると、逆にテキストの記号性が浮かび上がる。昨日あるデザインの下で書いたテキストが今日は違う意匠をまとうと、レイアウトの向こうにあるテキストの骨だけが透けてみえる。wwwで書いていると、テキストは自然と記号の骨を探り当てる。よきにつけ悪しきにつけ。
20090728
講義会議会議。夏休みは遠い。
軒下が弱み
5月にベランダの下をちょっと耕してもうすぐ三ヶ月。
気がつくと、仕事の行き帰りにベランダ下に寄るようになり、そこでうずくまってそれぞれの草の様子を見るようになり、薄暗くなってふいと立ち上がって同じ棟の奥さんを驚かせたりしている。
雨が降ると外に出て、どのくらいの雨ならば軒下のどこまでが濡れるかを確かめるようになった(軒下にお隣りからもらったヘデラを植えているからだ)。小雨なら濡れていない部分に水をかけ、大雨ならよしよしと見守る。チャペックが「雨が降ると、庭に雨が降っているんだな、と考える。日が照ると、ただ照っているのでなく、庭に照っているのだと思う。夜になると、庭が休息しているのだ、と思ってうれしくなる。」(園芸家の一年)と書いているのは、けして大袈裟ではない。ほんの少しの、菜園というほどもない軒下の一角が、いまや雨風を測り、陽射しを確認するアンテナとなっている。戸外の雨音に敏感になったのは、聴力が増したからではなく、軒下の一角が無意識の一角を占めるようになったから。無意識の一角に落ちる雨音だから、それはすばやくキャッチされる。
そして、軒下のできごとすべてが無意識の一角に反映されているわけではない。最初の一ヶ月あれほど弱々しかったヘデラは、知らぬ間にそのツルの先端でベランダの壁を触っており、タイムはいつのまにか花を咲かせ、ペパーミントもオーデコロンミントも、こちらが気を揉もうが揉むまいが、存分に地面を這いながら手頃な日向を探している。肝心な瞬間はいつも無意識の外で起こっている。これまたチャペックが書いているように「予期もせず、なんの世話もしなかったのに、クロッカスとスノードロップが、忽然と庭に出現する」。
気がつくと、こちらが思っていたのとは違う場所に、ミントの新しい枝が伸びている。ためらうことなく摘み、盛大にポットに入れ煮出した茶をごくごく飲むと、また雨音が聞こえる。
間違いの分析から中間分析へ
第二言語習得場面で以下のような問題が指摘されている。
「誤用を見ていれば学習者がどこを間違えるかは見えてきますが、それだけ見ていたのでは、学習者言語の全体像はわかりません。学習者は使いにくい表現を「回避」することができるからです。たとえば、ある学習者が本当に冠詞の使い方がわかっているかどうかは学習者の誤りだけ見てもわかりません。一例として、ある学習者が a book と言おうか the book と言おうか自信がない場合、それが自分の本なら、 my book と言っておけば、いちおう間違いは回避できるからです。」(白井恭弘「外国語学習の科学」岩波新書)
このことをシャクターが指摘してから、70年代になって、第二言語習得研究は誤用分析から中間言語分析(学習者の使う言語の全体像を見る分析)へ向かうことになったという。
同じことは、会話分析やジェスチャー分析にも考えられるだろう。言い間違いや言い淀み、ジェスチャーの停滞ややり直しじたいは、興味深い問題を提供してくれる。しかし、これらの現象だけから、会話やジェスチャーの特徴がすべて抽出できるわけではない。行為者は、使いにくい表現を「回避」して、いっけんすると間違っていないかのような表現を行うことがある。この「回避」現象までを視野に入れた「中間分析」的な視点が必要かもしれない。
こうした中間分析的アプローチとして、「データコレクション」を位置づけることができるだろう。特定のシークエンスがどのようなバリエーションをとりうるかをできるだけ集めてみること。それらを、言い間違いややり直しとともに総合判断すること。
エコロジー
田んぼの傍らに、よく回る風力発電機と太陽電池のついた塔があり、傍らにはコイン精米所のプレハブ小屋がある。精米所からはわずか四文字サイズの電光掲示板が突き出て、近所のうどん屋や食堂の宣伝をゆっくり流している。歩く人もほとんどいない通りに掲げられ、行き交う車からはとうてい読めないその一文は、まるで風車の力で物理的にスクロールするかのように右から左に送られていく。精米所の横、かつて田んぼだったところには、古いマンションがあり、さらにその横では原色の看板で焼肉屋が車を誘っている。焼肉屋のそばの田んぼは最近埋め立てられて、広い駐車場を持つコンビニになった。黒雲が近づき、風車は激しく回り出す。文字はあいかわらずゆっくり流れ、土砂降りににじむ。
天気読み
天気は西から変わる。琵琶湖には立ち並ぶ建物もないから、犬上川の土手から西をのぞむと空が広々と見渡せる。朽木の山々の向こうから不穏な雲が次々とやってきて、琵琶湖の上が黒ければ、それはもうすぐ夕立がくる知らせで、それでもまだ雨が降るまでに間はあるから、自転車を飛ばせば助かる。いよいよ近づいてくると、半袖から出た腕に感じる湿り気で、これはよほど濃い雲だなと判る。じっさい空が暗くなる。土手には雨をよける場所がないので急がなければならない。庄堺公園に屋根付きのベンチがあるのは判っている。案の定土砂降りになる。土手を降りて雨宿りしながら、琵琶湖のほうを見る。そこがすこし明るいようなら雨は小降りになるから、そのすきにまた自転車を飛ばす。
トイレ文
自分のメモを書きつけるつもりで始めたtumblrだけど、reblogしてもらううちに、reblogされやすい文章とはなんだろうと考えるようになる。自分で何度か見直す文章は、意外とreblogされない。もういいやと思った文章が意外にもreblogされる。reblogされる文章は標語に近い。トイレに貼っておくのにちょうどいい。湿った文体。ヒラタキクイムシが掘り返す文体。消臭剤の匂いのする文体。
バケツの水
バケツリレーをする人は、水の名前を知らない。それまで誰によって手渡されてきたのか、その履歴を考える暇がない。右から渡されたバケツを左に渡す。できるだけこぼさぬように。渡した手は空になり、疲れたら一服する。
20090727
ヘクソカズラの花が咲き始めた。
回想法と理想の会話
コミュニケーションの自然誌で発表。高齢者によるグループ回想法について。回想法を考えるとき「理想的な会話とは何か」という非会話分析的なテーマがどうしてもついてまわる(回想法は「何かの役に立つ」と思われているがゆえに行われる、セッティングされた会話なのだから)。分析する側としては、できるだけひとつのモデルに落とし込むのではなく、いくつかの多様な価値を見出していきたい。
「ごく短時間のうちに、ことばと身体がみるみる動いて組織化されていく瞬間」を見ると、いつもすごいなあと思う。強いて言えばそういう瞬間を多く含む会話が、内容はどうあれ豊かな会話なのだろうと思う。
忘れる、膝を打つ
お年寄りは、忘れる主体だと思われがちだ。
お年寄りは忘れることによってコミュニケーションに愛敬を産む。
忘れることがいかほどのことか。
忘れられて困ることは山ほどある。けれど忘れることは、お年寄りに限らず、すべての人類が負うべき枷であって、忘れることをことさらに難じても始まらない。むしろ、忘れつつ、いかに相手の表情やことばにリアルタイムに反応することができるか、その力がいかに頑健で、年齢にかかわらず居残るかについて考えること。忘れながら、相手のことばに対してぽんと膝を打つ。膝を打てない人にも、口にしたものを呑み込むすばやさ、まばたくすばやさがある。そのすばやさに注意すること。
会話へこぎ出すための介助
高齢者の中にはいっけんすると、聴力が衰えているように見え、また声量も下がっているように見える人がいる。こうした人は、ヘルパーさんの力なしには、会話できないように見えることがある。が、たとえば膝を近づけたり、視線をはっきりと送ったり、部屋のテレビを消して静けさを取り入れることで、ずいぶんと話がしやすくなることがある。ヘルパーさんを介さずに直接話を聞くことができ、同じタイミングで笑いあうことができる。この、相手の発話とともに刻々とこちらの表情が変わり、こちらの発話とともに刻々と相手の表情が変わる関係ができると、会話のいたるところに声と表情、表情と声の同期が起こり、濃密な時間が訪れる。残念ながら、ヘルパーの方を介したとき、これほど濃密な感じを得るのはなかなか難しい。機転の利くヘルパーさんは、高齢者がまだ体を後ろに倒しているときは耳元でことばを言い直し、あるいは本人のことばを相手に伝えるが、本人が体を前に出して自ら話し始めようとすると、こうした行動を止めて、本人が話すにまかせている。単に聴力や声量を補う介助ではなく、会話の豊かな時間へとこぎ出すことを介助する方法があるのだ。
20090726
カメラ・オブスキュラののち、窓を開け放つ

カメラ・オブスキュラの時間
スミス記念堂(彦根)でお見せしているのは、外界が暗い室内に映し出されるというもので、それは節穴現象とかカメラ・オブスキュラと呼ばれる、昔から知られている現象に過ぎない。けれど、それは単に、室内に倒立像が写ります、以上、というような瞬間のできごとではない。
それは暗闇に目をならしていくという体験であり、暗がりの中におぼろげに映し出される不確かな光のもやに突如かたちが与えられる体験であり、車、鳥、人、外の物音に注意を動かされ、視線をあちこちに惑わせるうちにそれまで気づかなかった細部がほのかに立ち現れていく時間である。少なくとも30分、できれば1時間くらいカメラ・オブスキュラの中に居ると、次第になにが起こっているのかが判ってくる。この一年にわたってスミス記念堂でやり続けて、ようやく、これは従来のスタイルのカメラ・オブスキュラとは違うのだということがわかってきた気がする。これは、シールズ・ロックやエジンバラにあるような伝統的で明るいカメラ・オブスキュラではない。もっと暗く、長い時間をかけて体感される特別な体験であり、その点で、どちらかといえばタレルの作品に近いものだ。
20090725
予兆による充足
さまざまな現象や行為に、未来の予兆を見ることじたいは、人に備わった能力であり、それはしばしば当たる。これに慣れてくると、特定の現象や行為を見ただけで未来が判り、しかも未来を確認しなくとも気に留めなくなる。午前5時過ぎにバタンと玄関で音がするのは新聞が来た音であり、わざわざ起きなくてもよいように。雨上がりの空気が変わると夏が来たのであり、夏を疑う必要もないように。誰も夏自身を見たことはないが、洋の東西を問わず季節が「来た」と言う。季節は予兆だけでできており、予兆によって来たことが充足される。夏は妖精の親玉のようなもので、一本道に立つかげろうも新しい雲も夏のしわざであって、それを疑う人はいない。夏のようにカミサマを信じる人がいて、妖精を信じる人がいる。ぼくは夏しか信じないけど、カミサマや妖精を信じる人がどんな気持ちかは、少し判る気がする。
活けセミ
 たぶん、隣の子が宿舎の玄関脇に置いた、セミの抜け殻。場所の選び方がいけばなの如し。
たぶん、隣の子が宿舎の玄関脇に置いた、セミの抜け殻。場所の選び方がいけばなの如し。
通り道と抜け殻
5月に摘んだヌカススキを、まだトックリに挿している。
すっかり実は落ちて、からからの茎とさやだけが残っている。茎が葉になり、葉が花になり、花が実になった通り道。ヌカススキの抜け殻。
冬虫夏草
蝉の幼虫は土の中で木の根と接続し、もはや樹液の通り道となって暮らす。その生活様式も長い年月とゆっくりとした成長ぶりも、動物というよりはむしろ植物に近い。蝉の幼虫からセミタケが生えたものは冬虫夏草だけど、あれは、幼虫に寄生した菌類というより、蝉の正しい抜け殻ではないかしらん。つまり、冬虫夏草の上に花が咲き、蝉が結実するのではないか。木についている蝉の抜け殻は、このプロセスを飛ばした早生まれに過ぎず、ほんとうは幼虫からキノコが生え、その先に蝉の花が咲き、結実したものがいま鳴き続けているのではないか。
地中で密かに伝説を育んできたセミの上に突如キノコが取り憑き、何年かに一度、詩が生まれる。生まれた詩は7日間、定型を鳴き通す。
20090724
図書館の新世界
時間を縦に割る音楽がこの世にはあふれているけれど、この音楽は時間を横に揺らせている。確かに居場所の決められた音ではないけれど、確かに鳴って去っていく。誰のものでもない書物はどこにあるだろう。あなたが座り、わたしが座り、知らない誰かが座ることのできる椅子はどこにあるだろう。椅子に座って、どんな時間を過ごそう。「図書館」の答えをきいてみよう。
(図書館「図書館の新世界」に寄せて)
バンドの名前は「図書館」。どんな音楽なのかな。
http://www.toshokan.net/
メンバーの声を読んでみよう。
http://www.hmv.co.jp/news/article/907220053/
下記サイトに文章を書きました。
http://www.hmv.co.jp/product/detail/3612393
妖精現象
妖精について考えるとき、妖精じたいの姿に考えを巡らす方向と、妖精の行為によってもたらされる現象を記述しようとする方向とがあるように思う。「グリム兄弟メルヘン論集」(高木昌史/高木万里子訳/ウニベルシタス叢書)を読むと、グリムの集めた妖精の記述にはたとえば以下のようなものがある。
・車道で大きな砂埃が上るのが見えたら、彼らが住居を変えて、まさに他の場所に引っ越そうとしているのである。
・それはあたかも一群の蜂あるいは蚊がざわざわと通り過ぎてゆくかのようである。
・敵対する者たちに、彼らは眼に見えないまま一撃を与え、人々を麻痺させる。
これらの記述には、この世のささいなできごとを、妖精の存在を感知するための手がかりとして捉えようとする態度がある。こうした態度によってつかまえられる現象のことを「妖精現象」と呼んでおきたい。
眼に見えない妖精の気配は、妖精現象と祭礼(祈り)を通して濃くなっていく。眼に見えないもののリアリティは、おそらくどれもこうした手続きを経て増してゆく。
動物のような詩、植物のような史
グリムによれば、昔話は詩的(poetisch)であり、伝説は歴史的(historisch)である。柳田国男は、昔話は動物的で、伝説は植物的であると指摘している。前者はどこにでも同じ姿を現すのに対し、その土地に根付き固有の成長を遂げるからだ。むかしむかしあるところに、ということばとともに動物は走り出し、土地の名前と共に蔓は繁茂する。どこにでも連れて行ける詩、株分けされる史。今年、お隣さんから分けてもらった伝説がベランダに届きつつある。
いもむしでんしゃ
いーもむしでんしゃのいうことにゃ〜
いもいも もいもいもいもいもい!
こっちもってこい もいもい!
もーいーんだよ、もーいーんだよ、いーもーだーかーらー
いもむしーいもむしー、いつかでーんーしゃーになーりーーーまーすーーー
しまるとびらにごちゅういください
(遠くにいるこどもちゃんの歌と合唱してみた)
reprise
もうこの町を出たと思った豆腐屋のラッパが、小路の向こうから聞こえてくること。
(図書館をききながら)
20090723
夕暮れからどちらにも抜ける
一度は夕暮れに近づいた空がまた明るくなる時間を過ごした翌日、空がかき曇り暗くなると、この夕暮れのような空は夜に向かうようにも昼へと抜けていくようにも思える。中間色としてのあいまいさではなく、方向の可能性が、低い雲にこめられている。さて、黄昏時に同じような感じに陥るのかしらん。夕方には塔にのぼって湖を眺めてみよう。
長く観ること/書き続けること
先週は夕立を二時間くらいずっと観ていた。昨日も30分(みじかいなー)くらい日食を観ていた。長い時間をかけて立ち上がる感覚というのが気になっている。5月に刈られたギシギシがもう腰まであるほどの株立ちになり、カタバミとミントが繁茂する二ヶ月。駐輪場に置かれたままの古い自転車のかごにヘクソカズラがたどりつく季節。三年前に机に置いたヘクソカズラが乾いていく年月。テキストになった本は一気に読まれるけれど、書く時間は読む時間と同じではない。日食のような本、夕立のような本、ギシギシのような本、ヘクソカズラのように伸び、乾いていく本があり、そのように書かれる時間がある。吉田秀和氏は連作のなかで、これまでにも書かれたことのあるアナクレオンの墓のことを改めて説き起こしている。ピアニシモからディミヌエンドを経て、 verklingend(次第に音が消えてゆく)でpppに至り、ついに完全に姿を消してしまう、その冬について。
コントラスト
ゼミが終わるとちょうど6時すぎ、夕暮れどきなのでみんなで鉛筆塔にのぼる。もう四回生なので臆することもなく、下の人達にわあとかおおとか声をかけたりして、それも飽きるとぼんやりして、ぼんやりしていても別段気まずくもなく、数十分、琵琶湖に日が落ちるのをみていた。今日はいわゆる「オランダ日和」ではなくて、くすんだオレンジと薄青に雲があいまいに染まっていく、色褪せた夕焼けだったけど、それはそれで夕方らしくてしみじみとした。でも、携帯のカメラで写すと、やけにコントラストがきいて、まるでむかしの金曜ロードショーのオープニングみたいで(という比喩は、もちろん若い人には通じない)、確かにそんな風にコントラストをつけたほうが見栄えはするしいかにも夕暮れ時だけれど、これはそんなあざやかな時間ではないし、下はハトの羽が点々と散らばるコンクリートで、冷却塔の湿った空気が吹き上げてくる狭苦しい塔の上で、転落防止の緑のネット越しにみるまだらな塔の景色を観ている時間であって、いかにもな写真で記憶するような時間ではない。そう思いながら、結局撮ったのはそのコントラストのきいた一枚だけだった。
20090722
部分日食
10時前、大学に出がけに曇り空を見上げる。しばらく待っていると、雲間から微かに欠けた日。分厚い雲は遮光グラス。ときどき見上げながら自転車で大学へ。科研を手伝ってくれる綿谷さんが来ている。「まだ見てない」というので、もう書類なんかほっぽってコーヒー持って見に行こう、と中庭に出る。中庭には誰もいない。みんな曇りであきらめてるのかな。角さんが向こうからやってくる。待つことしばし、雲間から三日月。歓声。空は不穏な暗さで風が涼しい。これだけ欠けると、さすがに夕暮れの少し前に近い感じ。声を聞きつけて教室からわらわら学部の先生も出てきた。さっきから見慣れてる人は、さっと雲間を通り過ぎるだけでも「あ、三日月!」と声をあげるのだが、初めて見る先生には「ん?」という感じらしい。
ああ、久しぶりに日食の不穏な空気を浴びた。
拙著から、明治20年8月19日の日蝕について。
明治とは、天体のできごとがあらかじめメディアで予告され、そこに予兆を見出すことが可能になった時代だった。日食もハレー彗星も、到来する前からそれと知れるようになった。この日に備えて日本鉄道会社は、皆既日食帯となる白河と上野間の往復切符を発売し、瓦斯会社は暗転時にガス燈を付けるため、ガス輸送の準備をした。
田山花袋は小説『時はすぎゆく』の中で、この明治になって初めての皆既日食の様子に触れながら、維新前を生きてきた老人と明治の若者たちの反応を対比させている。
---------------
昔は日蝕はあったけれど、それが何時かけるか、どの位多くかけるか。そんなことはお城の中の天文所でもあらかじめ知らせることは出来なかった。それが今では一月も二月も前からちゃんと知れて、日本が一番それを見るのに位置が好いと言って、わざわざ外国から学者が研究にやって来た。(中略)
「ああ、もう星が見える。」
「すっかり夜と同じだ。」
こういう声が外からきこえた。
老祖父は、「年寄なんか見たって仕方がない。役に立たない。これからは若い者はそういうことを研究して、えらくならなければならないけれど-」こう言って、勧められても、出て見ようとはしなかった。(「時はすぎゆく」)
(細馬宏通「浅草十二階」青土社)
20090721
クラシックかわらばん
オペラは手紙を歌いうるか?(2) - 手紙を読むアデーレ -
シュトラウスの「こうもり」を取り上げて、オペラの手紙場面について論じています。
20090720
びわ湖ホールで「魔弾の射手」。これは人間探求学の実習も兼ねていて、中村先生と一回生も。2500円でオペラが楽しめるという格安の企画だが、歌手の皆さんは歌い込んでいて楽しい内容。悪魔の表現はCGだったが、これは舞台装置と照明でやったほうが座りがいいような気がした。
ジム・オルーク/ピアノ・フィードバック@立誠小学校
京都へ移動。立誠小学校でジム・オルークのピアノ・フィードバック。最初の繊細な、場の空気をわずかに膨らませるような一音で、あ、いいなと思った。ぼくは壁際、床板が剥き出しになっているところで見ていたのだが、低音が鳴るとこの床板が震動して、講堂の大天井を見上げると小学校全体が鳴っているような錯覚。モスグリーンのカーディガンを着たジムさんの手つきも気になったが、どちらかというと、ホールのあちこちを見て、フィードバックを視覚的に捕捉して楽しんだ。
講堂の前に校歌が掲げてある。
朝夕に仰ぐなる/われらを囲む紫を/おのが姿の山として/力強くもいざ立たん
京都を囲む山々をひとことで「紫」とは大胆な歌詞、するとこの講堂もさしずめ小紫、などといらぬことも考えつつ、フィードバックは遠く近く。
20090719
雨を見る
長岡綾子さんと鈴木篤さんとが来訪。長岡さんの作品をあれこれ拝見する。カードゲーム、絵本、ワークショップ用ツール、どれも抒情がシンプルで美しい形式に乗せられており、すばらしい出来だと思った。カードゲームはすでにworkroomから発売が決まっているらしいが、絵本はとくにどこから出す予定もないという。もったいない。彼女の絵本を出す出版社が日本にないのが不思議である。
長岡さんの持って来たセットで三人で絵を描き、そろそろ解散、という時間に、ものすごい夕立。しばらく収まる気配もなく、みんな呆然と雨を見る。雨宿りするヒヨドリ。小雨をついて鳴き出すセミ。川のような道にテールランプ。そのうち、なんとなく部屋のガラス戸をはずしてみたくなり、わっせわっせとたてつけの悪いのを二枚、はずしてしまう。ぽっかり風穴が開いた部屋。こうなるともはや部屋というよりは洞穴なり。
20090718
寺川努・ムートン・かえるさん+繭ごもり
それにしても暑いな。新幹線で京都へ。散髪してからZANPANOでリハ。客入れ。なんか今日は坊主頭の人と角刈りの人が多いような気が。寺川さんの奔放なプレイはお寺できいたことがあったが、暗くさえない内容がみるみるさえないまま船出するエクスタシー。ムートンの声は、南野陽子の天然口内リバーヴを思わせる。ふたりでちゃらちゃらしてやる曲もよかったし、南野の1stの一曲目、というのもよかったなー。神戸の小景。
かえるさんでざっと6,7曲やってから繭ごもりの二人と。ピアノの弱音ペダルを入れて、さらにソフトペダルを踏んだまま演奏、もやがかかった感じでちょうどいい感じ。
「子どもと貨物船」「時の鐘」「ぴかぴか星人応答せよ(さよちゃんのボーカルで)」「虹を見たかい?」「坂の季節(アンコール)」
打ち上げで例によってユーミンを歌いまくってしまう。自分の歌よりも歌詞を覚えてるのだから困ったもんである。
20090717
かえる科@loop-line
今回は中尾さん抜きの三人で。新曲に一曲、カントリー&ウェスタン調の曲があったのだが、木下くんに「カントリー&ウェスタンってどう弾くんですか」と尋ねられて、まともに答えることができないのに気づく。「とんがりコーンみたいな感じで」「『亀田のあられ、おせんべい』というメロディーはカントリー&ウェスタンに似ている」などと、いい加減な思いつきで逃げる。本番、驚いたことに木下くんは、愚直なまでに「亀田のあられ、おせんべい」を繰り返した。ある意味、ミニマルなサウンドに。
20090716
歌はことばからの偏差である
午前から二コマ、岸野雄一さんの肝いりで、東京芸大の映像研究科でゲスト講義。スコット・ブラッドレー音楽の分析。そのあとなぎ食堂でちょっと休んでから、夜、映画美学校で講義。こちらも岸野さんの講義のゲストで。「歌はことばからの偏差である」、つまり、歌は、オートマティックな記号としてのことばから離れようとする試みである、というテーマで。逆に言えば、ことばは、歌から声をはぎとって記号に近づこうとする試みである。歌<音声言語<テキストの順に、人類は記号性を高め、声から(記号にとっては)余計なものを剥ぎ取ってきた。だから、歌詞カードを見ても、歌は判らない。そこにはテキストだけがあって、歌のもつ「余計なもの」が、剥ぎ取られているからだ。
・・・などと大風呂敷を広げたけど、話はユーミンなのである。
ユーミンの1stアルバム「ひこうき雲」から、「ベルベット・イースター」と「雨の街を」を取り上げる。とくに、「ベルベット・イースター」の冒頭二行の音節の取り方にどんな揺れがあるかについて。どんな揺れかというと・・・その答えは受講した人の胸のうちにあるのです。
といいつつ、サービスしてちょっと内容のさわりも。「ベルベット・イースター」と「雨の街を」とでは、ともに「雨」を扱っていながら、決定的に違うところがある。それはなんでしょう。一人の受講生が「『雨の街を』のほうは、あまり歌詞が飛躍していなくてなだらかな感じがします」と、ナイス解答。
ぼくが用意していた答えは「『雨の街を』には促音便がないこと」。注意してみると、「雨の街を」には「っ」がひとつも使われていない。「っ」は、音声上は単語内の沈黙を作る。促音便で、ことばの音はぽんと沈黙をまたぐ。
「雨の街を」は、音韻のレベルでも意味レベルでも、ジャンプを避けるなだらかな構造になってて、「どこまでも遠いところへ歩いていけそう」になっている。いっぽう、ベルベット・イースターでは、シャッフル(「むかっしー」「おりてっきそうなほど」など)と促音便(「いぃっぱい」「とぉぉってーもー」など)によって音韻レベルで、一行一行記憶をパッチワークする歌詞によって意味レベルで、イメージを飛躍させる構造となっている。
ユーミンの「sh」「s」音は、音符の位置よりも早く忍ぶように始まって、ことばのリズムを揺らせる。雨を歌う二つの曲にはこれらの音が多用されていて、そこも聴きどころ。
後半、岸野さんとの対談では、ぴんからトリオの「女のみち」を取り上げ、宮史郎の声について話す。
20090715
三回生ゼミで図書館調査。まずは図書館内の地図づくり。資料でいただいた地図だと、机や本棚の配置がちょっと実際とは違っている(たぶん後から足されたのだろう)。机と椅子のすべてに番号を振り、調査員どうしで確認しやすくする。簡単な予備調査をして、どこがやりにくい点かを話しあう。次回からは本格的に調査。
夜、東京へ。車中読書は谷口幸一・佐藤眞一編著「エイジング心理学」(北大路書房)。着くと夜半近く。宿で査読。「マンガノゲンバ」で上野顕太郎さんが出演、その場で集めた三つのお題で4pマンガを描くというとんでもない試み。
20090714
交流センターの前のナンキンハゼが花盛り。アブ、ハナムグリからクマバチにいたるまで、日盛りの花に虫がたむろしている。クマバチなどは大きな花序をいちどにまさぐるように雄花の上をずんずん歩いている。ナンキンハゼの花は、穂のように枝先に伸びて、そこに雄花と雌花の両方が咲く。福岡教育大学の福原先生のページによると、木によって雄花と雌花の咲くタイミングがずれているらしい。
これが秋には、白いろうのような実になる。
夜、護国神社の中にあるカフェ、「朴」で、「まっくらカフェ」。アイマスクをして、おちょこ一杯ほどの食材を次々と味わっていく。やわらかい実から種がほぐれる感触に遅れてやってくる匂いに「きゅうり?」、ピーマンのような酸っぱさの奥にリンゴのほのかな甘さがあるのが「赤のパプリカ?」、くらがりで食べる野菜は驚きの数々。木の匂いを嗅ぎ、木の肌を触り、2時間のフルコース。楽しい夕べ。
20090713
午前の講義のあと、ジェスチャー読書会へ。坊農さんの発表でNorrisの「Analyzing Multimodal Interaction」を半分ほど。ジェスチャー論ではしばしば見落とされるレイアウトやBGM、印刷物の話も取り込んだ、盛りだくさんな議論。学生向けということもあって、ひとつひとつのツッコミは浅い感じがするが、いろいろ考えるヒントがある。
20090712
放送大学の面接講義の二日目。1:西浦田楽の語り、2:空間参照枠とジェスチャー(おかあさんのうしろ問題、左右問題)、3:グループ回想法のターンテイキング、4:隣接ペアとグランド・ジェスチャー、音遊びの会の話、と盛りだくさん。
あとで、回想法に実際に携わっている方から、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)の使い方について「ただ単にできる、できないをチェックしているわけではありません。スケールを通して、相手の表情、仕草、声量、問いかけの理解力などを観察、評価、考察し、相手のできるところ、相手の苦手とすること、配慮、声かけをすればできるところ、トレーニングすれば改善の見込みがあるところをみつけていっています。」という感想。ぼくがHDS-Rについて、ごく限られたやりとりに基づくスケールだと話したことについての反論だった。本当は、こういう反論を、講義の間にしてもらえるようにしなければならない。もう少し意見をもらえる隙間を作らないと。
放送大学の滋賀サテライトは、龍谷大学の一角にある。そばには竹林と二次林。ウグイスが盛んになわばりコールをしている。ヒグラシが長く鳴くのを、今年初めて聞いた。
さすがにくたびれた。明日も京都なので、早く寝る。
20090711
放送大学の面接授業。
放送大学、というと、ビデオ録画された放送を受講者がTVで聞くだけのもの、と思われがちだけれど、じつは直接講義を受ける「面接授業」というカリキュラムもあって、これを年に何度か受けることができる。今回は、「日常生活の声と身体」と題して二日間8コマの面接授業。
一日目。30数人の受講者の方々は年齢層もバックグラウンドも幅広い。1:会話分析の基礎、2:隣接ペア、3:今日ヒマ?と投射概念、4:「あ」の行動論。
京都へ。拾得でbikke, 山本精一, オクノ修。その後、ザンパノ。ブルーチーズとブルーベリーのあいだにあるエロ話。ブルーにこんがらがって午前2時。
20090710
明日からの面接講義の準備。岡田暁生『音楽の聴き方』を読む。これは書評によさそう。
夜、お寺で、かえるさん+繭ごもりの練習。「ぴかぴか星人応答せよ」「虹を見たかい」しんとしたよいアンサンブル。帰りにちょっとザンパノへ。
20090709
朝、近所の空き地で繁茂しているスペアミント(もうすぐ花が咲きそう)を、わしっとつかんで、スゴシカフェへ。ミント茶を飲みながら、スゴシゼミ。Jeffersonのリスト構造の論文を読む。
昼、御子柴さん、城さん、ゆうこさんも登場して、みんなでお昼ご飯を作る。鳥のワイン蒸し焼き、茄子の味噌汁、夏野菜のオリーブ油炒め、厚揚げと玉葱のマリネバンカンのマーマーレードなどなど。豪華な食卓。すっかり満腹してから大学に戻り、講義と卒論ゼミ。
20090708
綿谷さんに来てもらい、科研の予算執行を次々と。書類の苦手なぼくにはたいへんありがたい。
三回生ゼミでは、図書館でゼミ生と予備調査。図書館の利用状況を調べるために、試しにそれぞればらばらに図書館に散り、30分ほど観察してメモをとる。驚いたのは、けっこうヘッドホン率が高いことと、何人かが携帯ゲームをしてること。図書館の音ってのはけっこういいもんだけどなあ。観察後、集まってアイディア出し。来週からは、図書館の図面を大量にコピーして観察記録をつけることに。
20090707
会議会議。
20090706
デイケア、グループホーム訪問
今年度から科研費でデイケア、グループホームでの介護職員の方々と利用者の方々との関係を観察することになった。そのキックオフ。県下の三施設を次々と回る。
デイケアに来ておられたTさんに、昔の鉛筆に名前を書いた話を伺うと、いきいきと手が動き出して、鉛筆を机の角に斜めにあてて、上向きに鉛筆を削る仕草を始められた。この「机の角にあてる」というところが、いかにも体験者ならではの所作。こういうディティールは、体験していないと出ない。身体の記憶はすごいなと思い知らされたが、あとで職員の方にうかがったら、Tさんは車の中で「そんなこと話しましたっけ」と言ったそうだ。
会話の中ではその場でしか想起しえない記憶が引き出される。たとえ、想起されたことが忘れられたとしても。それが会話の力、というものなのだろう。
グループホームでのかるたとり。Yさんが手許の札をしげしげと見て確信が持てないのを、遠くからKさんが手をのばして「それ」と言いながら手先を振る。それでYさんは、ちょっとKさんに札をさしだしかけて躊躇したら、Kさんが少し残念そうな顔をして手を少しひっこめかける。Yさんはそれを見ながら、ちゃっかり自分の手許に札を置く。札を見つけて取る力だけでいえばYさんはちょっと弱いのだけど、手札を誰のものにするかという駆け引きはなかなかのものだと思う。個人の認知が弱っても、関係の認知はわりと頑健なのかも、と思う瞬間。
20090705
かえるさん+山本信記@梅田さかさまマップ(OZC ギャラリー)
彦根から大阪に向かうJRの中でトランペットの譜面を書く。6曲書いた。こんなにがつがつ譜面を書いたのは、大学生の時分に吹奏楽の譜面を書いて以来かもしれない。
信記さんと会場の上の階で練習。譜面のない「のびたさん」で、「曲をやってる最中に遠くでトーフ屋が通り過ぎる感じで」と言ったら、信記さんが「それは・・・一回ですか?」と思いがけないクエスチョン。それで、しばし妄想を飛ばしてから「狭い町なので(なにが「なので」だ)路地をあちこち入っていくのです。それで遠ざかったと思ったら向こう側の路地からまた聞こえてくるのです」と思いつきを言う。そんなわけで、本番では、あちこちからトーフ屋が聞こえた。
「女刑事夢捜査」では、「夢の中で眠ってしまったので覚めるのがたいへん、という音で」。これはぶっつけ本番のほうが楽しいと思ったのでほとんど練習しなかった。すると、信記さんは、吹こう吹こうとしながらなかなか吹かなくて、ついに最後になり、いよいよ吹くか?と思ったら、なんと一音も吹かなかった。いままででいちばんテンションの高い「夢捜査」であった。
みにまむすの晴れやかな演奏、隕石少年トースターのメイドカフェ劇楽し。打ち上げにまじらせてもらい、彦根へ。
20090704
原稿。日杳(ひより)で昼食。カフェ工船で豆を買う。トーストのジャムとチーズ旨し。隣はストックルーム。かっぱの本を買う。
大阪へ。梅田さかさまマップ。JRがさかさでワイドに走る。くらがりで目が慣れていく過程が楽しい
Dramathology@伊丹アイホール
伊丹アイホールで相模友士郎×エルダー世代:Dramathology。これはすばらしかった。
70歳から95歳までの「エルダー世代」の一般参加者の方々芝居をされる。そう聞いて通常思いつくのは、それぞれの方々に経験談をお話いただき、その話の帯びている、経験者ならではのオーラや雰囲気をドラマにするというやり方だ。
けれども、この劇は、そうではなかった。かわりに採られていたのは、それぞれの出演者の語ったことばをテキスト化し、それを出演者自身が読み直すという方法だった。テキストにはかなり編集が加えられている。本人の語ったであろうことばにはすべて「わたしは」という主語がつけられ、列挙される。「わたしは72歳です。」「わたしは昭和○○年に、長男を授かりました。」「わたしは戦後すぐ、駅前でしろちゃん、くろちゃんと言われる子供を見ました。」テキストは、必ずしも時系列に並んでいるわけではなく、ひとつひとつの文は、ときに連鎖し、ときに飛躍して聞こえる。それが、六人分、続く。いつしか「わたしは」という主語は「わたしたちは」に変化している。
自分の体験をただ語るのではなく、いったんテキスト化されたものを読み上げることによって、ことばとことばを語る人とのあいだに距離が生じる。さらに、「わたしは」と主語を付けることによって、叙述特有の、第三者性が生じる。おもしろい。「わたしは」というほうが「わたしは」といわないよりも、人ごとに聞こえる。
それぞれの文は会話の連鎖から切り離されており、あたかもいきなり登場したように聞こえる。「わたしはコロナを買った」という一文は、戦中に大阪の郵便局で働いた給料でたばこのコロナを買った、ということらしいのだが、そんな風に踏み込んだ話というのは、本来、その人と何分、何時間と話して、ようやく打ち明けてもらうような話だ。そんな話を、まるで長い手でいきなりつかむように、ひょいとつまみあげる。ぼくは、いつも回想法で、時間の流れに沿って人の話を聞いていることもあって、あ、こんなところにいきなり届いた、また届いた、と、飛び石のように話から話へと越えていく展開の不思議を楽しみ続けた。
そして何より、みなさん絵になっている。もちろんお年を召しているということじたいのもつ、独特の落ち着きもそこでは重要なのだろう。でも、それだけではない。プロフェッショナルではない人の発声法が持つ、フラットであろうとしてもにじみでてしまうその人の発音の感触(みなさんちょっと関西弁だ)、できるだけ朗読に徹しようとすることで、かえって顕わになる語の癖が、それぞれの方々の、役に徹しようとする実直さと、そのような役に添いきらない違和感=来歴とを、同時に表している。けれど、そうした違和感を受け入れるだけの年齢があって、度量がある。その度量に支えられながら、声が揺れ、ページが繰られていく。
95歳の藤井さんが、若い増田さんに耳打ちするようにもたれかかり、そのまま数分動かないのではっとする。そのあと、すいと立ち上がって歩いてゆかれたので、やられたなあと思った。しかも、その歩みは、じつはとてもゆっくりだったのだけれど、終演してもう一度舞台に出て来られると、意外なほど速く軽い足どりだったので、二度やられたなあ、という感じだった。
あとで、トークショーに出たけれど、内容がすばらしかったので、もうぼくの方からとりたてて何もいうことはなく、以上のような点について、いくつか相模さんに投げかければ十分だった。
20090703
沼 429: 呼吸の節

キャッツ・アイ、Human Nature、マイケル・ジャクソンの声
この放送をダウンロードする
ダーガー、アロエ、會津八一
神田へ。丸石ビルというおもむきの深い建物の一階には、昔風の受付があって、エレベーターの扉も古風(中身は新しかったけれど)。その三階、あたかも小津安二郎の映画に出てきそうな廊下を抜けて扉を開けると、そこが小出由紀子事務所。昔、作品社から出たダーガーの本を訳しておられたのが小出さん。その小出さんの事務所でヘンリー・ダーガーの部屋の写真展をやっているというのを風の噂で聞いて、ふらふらと覗きにきた。小出さんは実際にダーガーの部屋に入った数少ない人の一人でアールブリュットにも長く関わっておられる。お目もじするのは初めて。
金属の皿に固まった水彩絵の具(ヘヴンではないセヴンの緑、などと、詩的な名前が綴られたものもあるのだとか)。宗教画。電話帳にびっしり新聞の連載コミックを貼り込んだスクラップブック。ポピュラーメカニック。1916年製のタイプライター。長年積み重ねられていたせいかページが圧せられて変形している雑誌(たぶん拾いもの)。雑誌のように堆積しているシカゴの空気のこと。奥の壁には引きのばした写真が張られてダーガーの部屋の一面に見立ててあり、黴臭い空気を少し吸った気がした。
帰りがけにわわわっと入ってきたお客さんの一人に、拾ったアロエをもらう。あちこち葉の折れたアロエの根元に、根っこのかわりに鉛筆の芯が生えている。これは鉛筆なのだという。不思議な人だ。長谷川迅太さんとおっしゃる。アロエを持とうとするのだが、芯が生えているので、どうしても、鉛筆を握る手になってしまう。迅太さんに写真を撮られた。鉛筆を握る手の形のまま、事務所を出て山手線に乗る。
なるほどしげしげ見ると、葉の折れたアロエは生ゴミにされやすそうな風体をしている。しかし、鉛筆握りをすると鉛筆に見えるから不思議だ。
お茶の水から神保町へ。鉛筆をしまう。資料をいろいろ。書泉グランデで発売されたばかりの「東京人」が平積みになっている。こうの史代さんのマンガを書評した号なので、なんとなくうれしい。そういえば、この書評は鉛筆の話で始まるのだった。たくさんの人に読まれるといいなあ。
八木書店の三階で會津八一墨蹟展。會津八一は王維の
行到水窮処 坐看雲起時
(行きて到る 水の窮まる処 坐(そぞ)ろに看る 雲の起こる時)
を何度も書いている。水の字は流れ、坐の字が、ひょいと膝を折って坐っているようにも見える。ある軸では、「雲起時」を「雲生時」と書いてあって、この生の字もいい。
竹藪の夕日涼しき厠かな
麦粉などひとりとり出しくらひけり
確か、昔の『墨』の會津八一特集だったが、誰かの回顧で、戦後の會津八一を新潟に訪ったら、書斎にそばが一筋落ちていて、それで會津先生は一人で書斎でそばを食べたのだなあとその孤独を思いやった、という話が載っていた。麦粉の句にも、そんな暮らしぶりが感じられる。でも、そのひっそりとした句は、しっかりと軸装されて、いまは神田の古書店で数十万円の値がついている。
うめにきてはるかにうみをみるひかな 秋艸道人
京都へ。前から気になっていた「バー探偵」にちょっと行ってみる。とくに知り合いがいるわけでもなかったので、店の気分を味わいつつ、隅っこで原稿のアイディアを書きつける。
20090702
図書館二題
大学の図書館から、行動観察をしないかというオファーが来る。じつは図書専門委員会で、図書館の利用状況を調べる話になったときに、ついうっかり、「それ、行動実習でやったらおもしろいと思います」などとクチを滑らせてしまったのである。というわけで、正々堂々と、静かな図書館でフィールドノートを広げ、人々の身振りを観察できることになりそう。いやあ、楽しいオファーだなあ。どうしよう。
図書館といえば、「図書館」。田中亜矢さんボーカルのすてきなバンド「図書館」がついに「図書館の新世界」でデビューしますよ。近藤さん、イトケンさん、宮崎さんの練達の演奏に加えて、アダチさん、宮崎さんのソングライティングがすばらしい。ぼくも及ばずながら賛辞をちらしに書かせていただきました。
20090701
放送室
このところ、三回生ゼミでは、松本人志の「放送室」を分析している。これはじつにおもしろい題材で、いかに松本人志という人が会話や語りに意識的かということがよくわかる。「放送室」を土台にして「すべらない話」の司会ぶりを聴くのもまた楽しい。全部聴くのは大変なんだけど、ちょっとずついこうかな。
to the Beach
contents