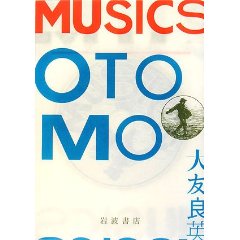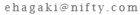The Beach : November 2008
細馬 宏通
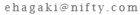
<<前 | 次>>
20081130
質的心理学会大会(二日目)
筑波研修センターからてくてく歩いて大学会館へ。大学構内は紅葉の終わりで趣き深い。
午前は、野村侑加さん、高木智世さんのシンポジウムに。子どもが絵本をめくる場面での母親と子どものインタラクションを通じて、三歳児にすでに現れているターン構造の組み立てをあぶり出し、「心の理論」の論点からしばしば抜けている相互作用の構築能力を見てとろうという試み。以前、大人どうしの読書場面を研究したことがあるので、いろいろ思いつくこと多し。
「こっち」と選択
とくに「ここ」と「こっち」という発語の使い方が印象的だった。いろいろ妄想がわく。
「こっち」ということばは、なかなかに企みの深いことばだ。
「こっち」ということばには、たいてい、身体動作が伴っている。
いちばんわかりやすい例は、指さしを伴う場合だ。「こっち」といいながら指さすと、それは指さされたものを意味する。
ただし、含意されているのは、単に指さされたものだけではない。わざわざ「こっち」というときには、そこに、指さされなかったものの存在、つまり「こっちじゃないもの」がほのめかされている。こっち、は、選択の結果を身体で指し示すときに現れる語だ。
今日見た事例では、ページをめくりながら「こっち?」という語が発せられていた。これもおもしろい使い方だ。検索をしたり、移動しながら「こっち」という。そこでは、検索や移動の方向(もしくは方法)が問題になっている。現在進行形の方向や方法が「こっち」であり、もし間違っていたら、こっちじゃない方向や方法をとらなければならない。ここでもまた、ある種の選択が身体で行われている。身体はいま、ある選択結果を行っている最中であり、この選択があっているかどうかを尋ねるのが「こっち」だ。
あるいは、こういってもいい。
「こっち」と言った瞬間に、言った本人は、それが唯一の道ではなく、他にも道があるかもしれない、という漠然とした予感を抱えている。「こっち」じゃない可能性のあるなしを、他人に向かって開いている。
三歳児のいさかい
午後、シンポジウムの打ち合わせ。砂上さんに保育園の場面をDVDで見せてもらう。そこで行われている発語や身体動作がなんともリッチな気がした。すでに手元のデータでpptを作ってはいたのだが、急遽予定を変更して、このDVDをじっさいに分析するという発表内容にする。そのほうが、分析の手順が生々しく判るだろう。
というわけで、「映像データの質的研究の技法と実践」。簡単に身体動作の連鎖分析について解説して、あとは、三歳児のいさかいの場面をじっくりと、コマ単位で分析する。これは自分でもいろいろ発見があっておもしろかった。
三歳児といえども、相手の言ったことばのどこに認知点があるか(どこにムカッとくるか)、わきあがる衝動をいかに抑えるか、いつ、どのように手を出すか、いつ泣くか、といったことを、じつに微細に調整している。叩く、泣くといった、情動的なできごとでさえ、お互いの発語と身体動作のタイミングの上に深々と錨をおろして、しかるべきタイミングで現れる。
スロー再生、コマ落としの陥穽
斎藤こずえ先生から、ビデオ分析は生々しくて、気をつけて使わないとちょっと怖いな、というご感想をいただき、ちょっとコマ分析を使いすぎたかなと反省する。
コマ落としやスロー再生を多用すると、ちょっとした動作がすごくインパクトの強い動作に見えてしまう。本来のスピードが判らない状態で、一コマ一コマをゆっくり見せると、おそらく見る人の脳のほうが、その一コマから、勝手にありうべき行動のスピードを補完して、より強く、より速いものとして置き換えてしまうのだろう。だから、ちっちゃなこどもの何ということのない拳でも、ボクサーの放ったパンチのように協力に見えてしまう。
動作のスピードというのは、じつは分析の重要な手がかりなのだが、マイクロ分析ではしばしば見過ごされがちになる。スロー再生、コマ落としと通常速度での再生とは、バランスよく使わねばならない。
つくばは交通の便に難がある。大学そばから乗った東京行きバスは途中で20kmの事故渋滞に遭う。最初は同乗していた砂上さんや荒川くんと話していたのだが、眠気に襲われてしばし仮眠。そのあと、社会言語科学会の発表要旨をがーっと書いて送信する。
東京駅で軽く飲み、最終の新幹線の中で査読。米原に着く頃にはあらかた査読ファイルができた。夜半近く、帰宅して送信。長い一日だった。
20081129
質的心理学会第一日
新幹線の中で寝て、つくばへ。午後のシンポ。アートと教育のシンポジウムでは、土佐信道さんが壇上に出て明和電機のプレゼン。
手元に現金がなかったので懇親会に出そびれ、高梨くんと駅近くの蕎麦屋であれこれ話。帰って明日のppt書類を作る。
20081128
沼 404: 家具は見過ごされる
 ハンマースホイ展を見て。
ハンマースホイ展を見て。
この放送をダウンロードする
関連リンク:
ハンマースホイ展webサイト
ユリイカの初音ミク特集に原稿。じつは、一度依頼されたものの、なんとなく気の乗らない返事をお送りして、今回はスルーかなと思っていたのだが、二日前に「金曜までにしゅっとお送りいただけないでしょうか」とメールをいただき、この際なのでがーっと書く。
ニコニコ動画は滅多にみないのだが、この機会に山ほど見て、初音ミクの歌もあちこち検索してできるだけ聞く。結局夜明けまで。
20081127
ゼミ三本。ビデオを見過ぎて目がしょぼしょぼになる。毛様体の限界。卒論までのスケジュールを告げると、なんとも年の暮れな気分が卒論ゼミに漂った。
昨日の「ためしてガッテン」で得た知識が最大に生かされた柚子づくし夕食。
20081126
講義のあと、近さんがやってきて久しぶりにいろいろ話す。
夕方、とんでもなく大きいひこうき雲。いくらなんでもばかでかいと思ったが、ひこうき雲というのは、成長するものらしい。
「ためしてガッテン」(じつはわりと見てる)のゆず特集にガッテンガッテン。さっそく「南半球しぼり」を試し、皮を粗みじんに刻み、柚子味噌をつくる。あ、旨い。
20081125
朝、新幹線で戻るも、不調。ローペースで仕事。
20081124
横浜トリエンナーレ
朝早起きして、横浜馬車道へ。そこからバスで三渓園。広々。大正のジャポニズム・パッチワーク庭園。内藤礼の「ループ」。外に蜘蛛の糸が一筋。横浜のすぐ近くにこんな場所があるとは知らなかった。
午後、馬車道に移動、三会場を回る。角田さんの扇風機スクリーン楽し。すごく楽しみにしてたフィッシュリ&ヴァイスは、なんと息をしてなかった(どうやら故障だったらしい)。残念というより、悲しい。
テキストものという説明を聞いて半信半疑だったミランダ・ジュライの廊下時間は意外にも楽しめた。
たぶん、ひとつひとつしみじみ見れば、もっといろいろ反応できたのだろう。が、これだけなんでもありだと、展覧会というよりは展示会という気がしてならない。とくに新海ピア会場の騒がしさはちょっとすごかった。音ものが多く空調のきつい会場では、音楽を使った展示はつらい。ここはあくまで本番ではなくお試しコーナーで、どこかに別の本番がある、という感じがしてならない。
もっとも、こちらが詰め込んで見過ぎているのにも問題があるのだろう。この連休はいくらなんでもあちこち行きすぎた。ざっくり見て大局をつかむ、というのは苦手だ。
夜、横浜で飲む。地元民大谷氏がいるので、あちこち旨い。すっかり酔っぱらって最後はハットリ邸にお邪魔。トウキョウソナタを言祝ぎつつ、「月の光」をいろんなピアニストで聞きながら、わけのわからぬ舞を舞う。
20081123
昨日は、昼に「友達」を観たあと、夜に新・転位21の「シャケと軍手」。さらにそのあとは、かえる目のミックスダウン。盛りだくさんな一日だった。秋田児童連続殺人事件を扱った「シャケと軍手」についてはいろいろ思うところがあった。それは以下の「ラジオ 沼」で。
沼 403: シャケと軍手 記憶のもやの先へ
 「シャケと軍手」、太宰治「魚服記」、飴屋さんのこと
「シャケと軍手」、太宰治「魚服記」、飴屋さんのこと
この放送をダウンロードする
「その日のまえに」@角川シネマ
六角鉛筆を発明したのは誰なのだろう。人類は六つの角が転がる音を得た。鉛筆を握るたびに、頭は鉛筆を思い出し、鉛筆の転がる音がする。転げ出そうとする鉛筆を見ると号令をかけたくなる。転がっているのは鉛筆であり、転がる事情は鉛筆の側にあるのだが、わたしには鉛筆の気持ちがわかるので号令をかけるのである。鉛筆の気持ちがわかると、鉛筆が転がろうとする瞬間がわかるので、出発進行と号令をかけるのである。号令をかけると鉛筆が転がり、鉛筆が転がると転がる鉛筆のように叫びたくなり、叫びとともに列車が動き出し、リールが回り出し、回るリールが花火を映し出す。これは青い幻燈です、といえるほど青くなるまで。
ハンマースホイ展@上野
これもノートに何枚もメモが貯まった。また近いうちに書くことがあるかもしれない。
20081122
友達@世田谷シアタートラム(岡田利規演出)
舞台には、建材用の金属パイプを曲げてつないだだけの、簡素な部屋らしきもの。そこには壁も、床の間仕切りすらなく、二つのドアがなければ、それは部屋とすら判らない。
冒頭、まだ薄暗い舞台の上を、闖入者たちが現れ、パイプの存在を気にすることなく、思うまま舞台を縦横無尽に歩く。
この、不思議な導入部は、安部公房の原作と比べると、圧倒的に違っている。
確かに安部公房の原作には、「ドアを含めて、すべての家具調度が、可能なかぎり単純化され、省略されていることが望ましい」とある。しかし、その一方で、原作には「家具、調度をふくめて、赤っぽい粘土色、もしくは灰色で統一されていること。上手、手前に、台所に通ずるドア。下手、奥に、別の部屋に通ずるドア。下手、手前に、玄関のドア。(中略)玄関わきに、格子状の靴箱。」などと、舞台の配置配色は事細かに記されている。おそらく、「可能なかぎり単純化され、省略されていること」というのは、あくまで抽象性を高めるための指示だったのではないか。
ところが、この舞台の「部屋」は、抽象どころではない。
下手と上手のドアには、玄関と室内の意匠の区別すらない。どちらも、プレハブ用の、ホームセンターにありそうなものだ。あとで闖入者が下手から礼儀正しく、「ごめんなさい、すっかり遅くなってしまって」と入ってくるから、かろうじてそこは玄関に見えるのだが、実際には、上手のドアと全く同じである。
なによりも重大なのは、壁の不在だ。
この主人公の「部屋」には、壁がない。
壁があり、玄関があるならば、劇はとりあえず「平凡な男」を主人公として始まるし、そこにやってきたものを「闖入者」として位置づけるところから始めることができる。ところが、この舞台ではもはや、そうした区別すらが無効となっている。
もう舞台の冒頭から、部屋はあってなきが如きなのだ。
闖入者達がいったん舞台から降りたあと、舞台が明るくなると、一人の男が、牛の着ぐるみパジャマを来ている。原作ではこの男は「三十一歳、商事会社の課長代理」なのだが、ここではそうした職業を微塵も感じさせない、幼稚で奇矯なかっこうをしている。
主人公は電話をする。耳障りな音でちっちっちっちと舌打ちのような音。主人公が「違うよ、故障じゃないよ、キッスだよ」と言わなければ、それはキスの音とはとうてい思えない。
このように、主人公は奇矯な格好をした、耳障りな舌打ちを発する男で、どう考えてもまともじゃないのは主人公であると思わせる演出である。
どうやらこれは、正常な主人公の感覚が闖入者によって徐々に冒されていくのを楽しむ、という舞台ではない。あらかじめ蹂躙され、部屋の体をなさなくなった場所を、わずかな手がかりをよすがに住みかとしているあわれな男のもとに、やたら正論を吐く人達が訪れる、ということらしい。
物理的な壁だけではない。舞台設定としての壁すらも、この演出にはない。登場人物たちは、一応ドアを使って出入りすることはあるものの、それは、演劇上のお約束を少しなぞってみた、という程度で、あとはドアにこだわることなく、組まれたパイプの下(そこは「壁」として想定されそうな場所だ)を堂々と通過してしまう。
麿赤児にいたってはステッキをふるって暴れ出すと、パイプの下を通過しながらカンカン鳴らしてしまう。こうなるともう、パイプは部屋の枠組みですらない、ただの金属の空洞に過ぎず、それはかき鳴らされるギターと同じく、従順に音で反応する物体に過ぎない。
こんな風に、部屋であって部屋でない演出だから、最初は、この舞台は一種の「部屋論」なのかなと思って見ていた。部屋がもはや部屋でなくなってしまった者が、どこでどうやって住み為していくかという話。
が、「部屋論」だけでは説明できないことも起こる。
本来は壁の中で、役者どうしで交わされるはずの台詞も、壁の中で閉じてはいない。言わずもがなの台詞を言うために、役者はしばしば、舞台の前面に出てきて、いかにも客席に向かって言ってます、という風情で台詞をきめる。それは、客席の共感を呼ぶための素振りというよりは、むしろ、壁を持たぬ世界に生きる人々の異文化的振る舞いに見える。
この、舞台から客席への非-問いかけは、くどいほど繰り返される。途中、若松武史が観客席へと移動しても、観客との一体感はほとんど起こらない。
麿赤児の突拍子もない身体動作、木野花や若松武史の舞台で叩き上げた発声は、別の舞台であれば、観客を巻き込んで離さないだけの力を持っているはずのものだ。しかし、この演出では、彼らの舞台的動作や声のほとんどは、空振りに終わる。彼らの動きや声が、彼らのホームグラウンドを喚起させるだけの力があるだけに、その空振り度は、ものすごい。今回、この出演メンバーと組むことによって岡田利規氏が得たのもののひとつは、おそらく、この空振りの「大きさ」なのだろう。
管理人さんがやってくると、スポットライトが当たる。服の色がよくわかる。しかし、管理人さんは、スポットライトを浴びるにふさわしい何かをするわけではない。ここでも空振りなのである。そういえば、スポットライトを投げる場所というのは、舞台とどういう関係にあるのだろう。このスポットライトは、誰が、何の権限によって、投げかけているのだろう。そこは、舞台の声の届く場所なのだろうか。
どうやら、これは「部屋論」である一方で「舞台論」であり、声の空間論でもあるらしい。
人と人とが声を交わすことのできる空間はどこにあるのか? たとえば、相手が目に見える場所にいるだけで、その相手は声の受け手であることが保証されるのか? もし目の前にいるだけでは足りないのなら、どうすれば声は届くのか?
そういうことをこの舞台を見ながら考えていた。
後半、原作では舞台が公園へと移るはずの場面でも、部屋を表すパイプは取り除かれない。闖入者たちの手によって部屋の下に堂々とベンチが置かれ、部屋内公園ができてしまう。主人公は部屋の中につるされたハンモックにくるまったまま、その、部屋のような公園にやってきた婚約者と、目を合わすことなく語らう。ハンモックの中で主人公が体位を変えると、微かにトーンが変わる。声は眠りの回路を使って通う。おもしろい演出だ。
しかし、ぼくがいちばんショックを受けたのは、後半、檻に入れられて冷たくなっていく主人公に向かって、次女がマイクで語り出した場面である。
それまで、挿入歌をカラオケ的に歌うために使われていたマイクが、じつは、声と距離について考えるための道具として扱われていることに気づかされたからだ。
この、マイクごしの声は檻の中に向けられているらしい。マイクによってのみ、声が届けられる場所が、檻の中なのだ。だとすれば、さっきまで挿入歌をマイクごしに聞いていたわたしたちもまた、檻の中なのだ。
そういえば、カラオケというのは不思議な場所だ。あの箱のような部屋の中で、ささやきだって聞き届けられるはずの場所で、わたしたちは音楽を拡声し、声を拡声し、わざわざマイク越しに何かをがなっている。あの声は、誰に聞かせるために拡声されているのだろう。あの声が、何らかの通路を通って、どこか知らない檻に通じているのだとしたら、それはどんな檻だろう?
舞台終盤、もはや主人公が死んでしまったあと、次男は、舞台と客席との接面で後ろ向きに立ち、あたかも何かが聞こえたように、不審そうに振り返る。それがどこから来た声なのか、客席からは察するよすががない。この舞台は、客が察するときに使おうとするよすがをことごとく覆してきた。だから、ここでも、客は空振りを観るしかない。
呉キリコがセーラー服のまま、舞台前面に立ち、客席に向かって片足をあげて奇妙なポーズをする。しかしこれもまた、客に何かを判らせる、というものではない。
この舞台を通して一貫してあった唯一の壁は、舞台と客席の間にあったように思う。登場人物のしぐさや台詞は、方向こそ客席に向いていたが、それらはむしろ、客に届けることを拒むかのように、あらかじめ伏線も客への親密なそぶりも注意深く排されていた。(唯一、木野花と若松武史が客席に親しげにことばをかける場面が一カ所あったが、あれは、むしろこの劇の中では浮き上がった、インターミッションのように見えた。)
客に届けることを通してこの世でない誰かにことばを投げるのが既存の舞台だとしたら、この舞台は、客に向きながら客に届けることを拒むことを通して、この世でない誰かへの隘路を築こうとしているように見える。
名だたる役者を配しているからだろうか、今回の演出では、やや空振りの大きさのほうを強調しすぎている気もした。が、問題は、しぐさやせりふが空振りすること自体ではなく、それがどのような隘路を開けているか、だろう。そして問題はつまるところ、舞台がどうだったかではなく、こちらが舞台から何を持ち帰ったかだ。
それで、こうやって、舞台を観て持ち帰った考えをつらつら書いている。この文章にだって、どこかに隘路があるはずなのだ。

20081121
ゆめまち観音
実習を終えて東京へ。浅草で下町コメディ映画祭の前夜祭。あほまろさん監督の「ゆめまち観音」を観る。以前、事務所にお邪魔したときに、撮影のもととなったジオラマを見せていただいたのだが、あれが、このようなディティールある映像になるとは。あとで聞いたら、拡大撮影をするにあたって相当塗り直しや作り直しがあったそうだ。
全編、動かないジオラマで作られているのだが、70分、不思議と退屈することがない。これは画期的なのでは? 機関車が動き出す場面やモンパパの場面の躍動感(挿入歌がまたいい)も楽しく、絵はがきや紙モノを駆使したカットの数々にはコレクター魂が感じられる。
もちろん、ふんだんに出てくる十二階もたまらない。
終演後、生田夫妻、平林さんはじめ郵趣出版の方々と飲みつつお話。
20081120
終日ゼミの日。今日は携帯電話研究をしている卒論生のデータを皆で見る。見所多し。
20081119
大学院志望の学生向けに後期から自主英語ゼミを始めた。人間行動学はようやくフライシャーまできた。
20081118
学科の中間発表会。まだ萌芽的なものばかりだが、うちの学科のようにゼミ形式になってると、他のゼミの学生が何をやってるかを知るいい機会になる。他のゼミの学生と何人か相談。
20081117
朝の講義を終えて京都へ。コミュニケーションの自然誌研究会。出るのは久しぶり。串田さんの発表は、語り、もしくは話題という長い単位の現象における聞き手の問題を扱おうとするもので、いろいろ考えさせられる。聞きながら妄想していたのは、話し手にとって秘密とは何か、という問題。
20081116
パーフェクト大分ツアー
朝、近所を散歩。山の上で、タヌキのペアがくつろいでいた。
バクさん宅で一同充実の遅い朝食。山内桂さんが迎えにやってくる。それからもさらに食べていると、もう昼過ぎ。
山内さんの案内で今日は湯布院あたりに行く、らしい。らしい、と曖昧なのは、何もかも山内さんまかせゆえ。わたしとゆうこさんは山内号に、外山さんは倉地号に。
大分川を遡るように国道を走っていく。「川に沿って行く、というのが本来の道なんです。」と山内さん。どうやらこの道の選択からすでに、旅は始まっているらしい。
高崎山を右に見ながら回り込むように川が進む。扇状地の田畑の合間に、林がそここに残されていて、まだ紅くなり始めたばかりの木々の中で、イチョウだけが、切り抜かれたように、こちらに黄色い合図を送ってくる。庄内、という看板を過ぎる。「ぼくは庄内のイチョウがいちばん好きなんですよ」と、これまた山内さんの計画には織り込み済みらしい。
ときおり道連れのように現れる単線の線路は、久留米と大分を結ぶ「久大本線」。こちらより少し山に近いところを走っている。いつか乗ってみたいものだ。
途中で「ちょっとここで回り道をしますが」と、山内さんはぐいっとハンドルを切って山道に入る。回り道、ということばに急がされたようにスピードがぐんと上がる。マニュアル車をあやつる山内さんの運転は、ギアの入りもハンドルさばきもメリハリが効いている。車体の動きが明らかに切り替わり、それに合わせて助手席に乗っているこちらの気分もさっと変化する。
登ることしばし、路肩に車が泊まったので「ここですか?」と聞くと「ここです」と言われる。「これ要りますか?」とタオルを肩にかけるしぐさをすると、「もちろんです」と言われる。ここで温泉に入る、ということらしい。倉地さん、外山さんも降りてくる。
すぐそこには石畳の坂があり、旅館らしい看板が誘う気に続いている。ようやくここが「湯平温泉」なのだと判る。温泉地はいくつか訪れたことがあるが、こんな坂のある場所は初めてだ。ここは温泉が豊かなのだな、と直感する。火山があって、火山故の坂があって、そこに当たり前のように湯が沸くのだろう。
山内さんはその坂からひょいと小路に入る。ついていくと、その先に小さな橋があり、川沿いに公衆浴場がある。入浴料200円なり。受付も番台もなく、箱に200円を入れるだけ。さっそく入ると、小さな檜の湯船と蛇口が二つ。石鹸もシャンプーも見あたらない。山内さんはさっさと服を脱いで湯船へ。それにならってお邪魔する。四人の大人がそれぞれ湯船の隅を陣取ると、まるであつらえたように四人用である。
さっそく外山さんは湯口の木箱をこんこんと叩いて響きを確かめている。「ここ、ウォータードラムできますね」と言うと、外山さんはそのうちちゃぽんちゃぽんと水面で合いの手を入れ始めた。さらにプラスチックの桶を一つ二つと浮かべて指先で弾くと、ほがらかな音がする。「これ、水の入れ方で響きが変わるんですよね」。
外山さんが浮いた桶をちょっと押すと、ぷかぷかとこちらに桶が漂ってくる。この身は桶の漂着する岸辺である。目の前に来ると叩かざるを得なくなる。飽きたらちょいと押して、桶パスをする。倉地さんも叩き、山内さんも叩く。「それ、誰叩いてるの〜」と女湯からゆうこさん。あちらにも聞こえているらしい。
外山さんは手刀をふるって水面をばんばん切り出した。水面を叩くときの掌の形で、空気の入り方が変わり、響きが違ってくるのだという。真似をしてみると、ぽこ、が、ぱし、になり、ぱしゃ、とも、ちぴ、ともなる。なるほど。その間にも興に乗った外山さんはときおり足を伸ばしてかかとで水面を切っている。もうステージ上の動きだ。
そのあと、休んだり叩いたりで30分はいただろうか。
大の大人が風呂でばしゃばしゃ音を鳴らしてるだけ、なのだが、メンバーが山内桂、外山明、倉地久美夫、である。録音しておけば間違いなしの珍盤になったはずだが、ドルフィーも言ってるように、「音は一度空中に放たれると二度と戻ってこない」のであった。
湯から上がり、外へ出ると、一組の夫婦とすれ違う。「ね、タイミングいいでしょ」と山内さん。もし彼らが湯船にいたら、あのような風呂セッションははばかられたところだ。
再び車に乗り、山道をとって返す。信号待ちの車から眺めていると、橋の上で、カメラを持って身構えていた一人の男が突然、ライオンに襲われた小動物のようにぶるっと震えて身を乗り出す。ごーっと音がして橋の下を黄色い電車が通り過ぎた。「いまの人すごいビクッとしてた」「ビクッとしてたねえ」。
山道を飛ばすことしばし、小さな山をひとつ越えると、目の前が急に開ける。正面には雲をかぶっているらしい山、全貌はわからないが、やたら大きいことは判る。これが由布岳なのだろう。そして手前に広がっているエリアが湯布院なのだろう。遠く山沿いには、あちこちに煙突が立ち、湯煙が上っている。「ここが大分川の源流でね。昔は全部湖だったという説もあるんですけどね」山内さんの地理学的な説明には、ドライブの時間が重なっている。川を辿るための時間があり、その時間から解放されたところに広がる水底の町として、湯布院が開けている。
田畑を抜けて、trico cafeへ。白塗りのカフェのそばには湿地らしき場所が広がっている。なぜかクレソンが群生しているのだという。火山でできた浅い水瓶の底に置かれた、小さな箱の中にいるような気がする。おそらく湯布院じたいが、巨大な湯船なのだろう。城崎にも、この湯船感があった。けれど、湯布院は、海から隔てられている分、より湯船感が強い。
珈琲をいただき一服してから、由布院駅へ。倉地さんの歌に出てくる、風倉匠の絵が待合室にかかっている。なかで「異国への扉」と題された、青に鉄錆た金具の痕のようなものが描かれた絵がいいなと思った。その、手にはとれない痕のぐあい。
湯布院の町をあとにし、福岡で演奏をひかえている倉地さん、外山さんと別れる。今度は由布岳のふもとに上り、あらためて湯船のような町を見下ろす。
見上げると、木々のない、なだらかな草原の山腹で、大分の山深い時間が、夕暮れていく草原に溶けていく。各地の渓谷を遡るのが趣味、という山内さんの、土地を訪れ、去っていく時間を、半日の間、ちょっと分けていただいた。
鶴見岳を抜け、別府駅まで送っていただく。この世に来たような気がする。
駅前のロータリに入ったら、こちらに襲いかかってくるような像が正面にあって驚く。ネームプレートを見たら、油屋熊八の像だった。油屋熊八の別府開発の話は橋爪紳也さんの本で知ってはいたが、こんな破天荒な像が駅前にあるとは思わなかった。
特急ソニックに乗る頃にはもう夜。新幹線に乗り継ぎ、彦根に戻る。
20081115
別府観光、かえるさん@バクまつり(大分 AT HALL)

戦前の観光絵はがきを集めていくと、自然と別府のものがたくさん集まる。
別府絵はがきの中でよく見るものに、「砂湯」がある。波打ち際にずらりと並んだ浴衣姿の女たちが、砂に埋められて横たわっている。遠くに山がボワーンと浮かんでいる。
湯浴みというより埋葬に近い。不思議な光景である。
大分に来たからには、ぜひこの砂湯を体験したかった。というわけで、バクさんにお願いして、海浜沿いの砂湯に案内していただく。
大分市から別府に向かうと、右は海、左は山。ニホンザルの立て看がある。これがサルで有名な高崎山だと初めて知った。ということは、あの絵はがきのボワーンは、高崎山のボワーンであり、あのボワーンは、サルだらけなのだった。
別府のまちなかをしばし歩いてから砂湯へ。ひなびた温泉、というイメージとは裏腹に、砂湯は意外にも広い海岸通り沿いにあった。一回千円なり。
屋内の脱衣場で浴衣一枚に着替えて、浜に出る。すると、そこは普通に人が散歩をする砂浜で、その一角に、広めの砂場のような場所があって、たすき掛けをした女性陣が待ち構えている。先客がすでに何人か埋まっている。これが砂湯らしい。
招かれるまま近づいていくと、砂かき棒で人の大きさに浅い穴を掘ってくれる。そこに浴衣のまま横たわる。
その仰向けになったところに、掘った穴でできた砂山を、足先からすとん、すとんとかけてくれる。さほどの分量ではないのだが、腹、胸と埋まってくると、けっこう圧力が大きい。腹が圧迫されて呼吸が浅くなる。
先日あったという砂場遊び事件をつい思い出す。やっぱり人を砂に埋めちゃいかんよ。こんなに浅くても呼吸が変わる。
最後に、頭の下に木のマクラを入れ、さらに少し盛り土をしてから頭を載せる。正面に別府湾が口を開けている。これはいい眺めだ。
いつごろからこんなことをやってるんですかね、と聞くと、年配の女性がなめらかな口調で「この辺はあちこちでお湯が沸いてるので砂が自然とあったかいんですよ。それで、砂の上を歩いていて、座ってみましょ、寝てみましょ、かけてみましょ、で砂湯になって」と言う。座ってみましょ、寝てみましょ、かけてみましょ、というのが、いかにも調子よい。ホップ・ステップ・ジャンプのようだ。
「別府湾は鶴が羽を広げたようになっていて、向こうが四国ですからね。ちょうど鶴の頭から見たようだちゅうので鶴見岳というんですよ」。
では、この、砂浜より木マクラ分だけ高い我が頭も、鶴の頭のようなもので、砂に埋まった手足の代わりに、湾岸を肩から生やして海を抱き、遠く四国を見晴るかしているところなのかもしれない。遠く、人の形をした雲が動いていくのは、自分が飛んでいるからだろう。などと、夢うつつになっていく。
額に汗がじんわり浮かんできたところで砂を取り除いてもらい、起き上がる。屋内のシャワーで砂を流して、湯船に浸かる。
 砂湯を満喫したら、もう今日一日が終わった気がした。気がしたが、旅先の貪欲さゆえ、もう一カ所バクさんにリクエストする。それは「ひょうたん温泉」である。
砂湯を満喫したら、もう今日一日が終わった気がした。気がしたが、旅先の貪欲さゆえ、もう一カ所バクさんにリクエストする。それは「ひょうたん温泉」である。
以前、別府絵はがきの一枚に、田んぼの真ん中に立つ奇態なひょうたん型の建築物を見つけて以来、このひょうたん温泉がいかなるものなのか気になっていた。風の噂で、すでにひょうたんタワーはないとは聞いていたが、せめてその跡地なりとも確認したかったのである。
バクさんに案内していただくと、場所は鉄輪温泉の一角で、かつては田んぼであったであろう周囲は広い道路になり、いかにも観光地然としている。が、立て看板には確かに、絵はがきで見たひょうたん塔のかつての姿が表示されている。どうやらこの不思議な塔は、創業者の河野順作の創案によるものらしい。
せっかくなので、温泉にも入ってみる。こちらは700円なりで、中には広々とした瀧湯をはじめ、各種湯船が揃っており、畳敷きの食堂もある。温泉のコース料理という感じ。
湯からあがって休憩所で、さきほどの砂湯の印象を歌にまとめる。初めての土地に呼ばれたら、土地誉めをする、というのは、歌作りの基本である。
砂湯、温泉と、別府を堪能した。ここから、大分市に戻り、旦那の笑顔がまぶしいこつこつ庵でとり天をいただき、バクさんおすすめの庭付き喫茶ばんじろうで和む。
ああ、ゆっくりしてるなあ。ほんとに今日はライブなんだろうか。
いや、やはりライブであった。午後六時近く、AT HALLに着くと、もう他の面々は到着している。
わたしはギターとボーカルだけなので、簡単にサウンドチェックを済ませて、外山さん、倉地さん、そして遊びに来ていた山内桂さんと近くでだんご汁、そして喫茶。だんご汁を食って「ジルベルト汁」というフレーズを思いついたあたりから、おっさんモードにシフトし、駄弁がどうにも止まらなくなる。ほんとに今日はライブなんだろうか。
いや、やはりライブであった。るゥさんがギター一本でしっかりと歌うのを聞いて、まずい、このあとに大分新参者のおっさんとしてヘタクソな弾き語りをするのかと冷や汗が出る。が、もう遅いのである。
三沢洋紀とゆふいんの森。いいバンドだ。どの曲も踊れてせつないごきげんなナンバー。なんというか、青春やなあ。バンドはいいなあ。(みんな座って聞いてたけど、三沢くんに言わせると「大分のお客さんはくすくすという反応が多い」のだとか)
短い休憩のあと、一人のこのこと出て行き、次々と歌わせていただく。例によって歌詞もコードもあちこち間違え、途中でカポを忘れたことに気づいたり、間奏をどうするか決めていないことに気づいたり、客席にいた三沢くんを引っ張り出して無理矢理間奏をやってもらったりした。わりとセーブしたつもりだったが、あとでバクさんからもらった録音ファイルを見たら35分割り当てのところを55分もやっていた。
倉地久美夫・外山明の自在なリズム、自在なことばを惚れ惚れと聞き、自分のプレイのことはすっかり忘れる。終演は夜半近くだったがお客さんはほぼ残っていた。すごいな、大分ライブ。
バクさんの家へ。一緒に泊まる倉地さん、外山さん、ゆうこさん、そして市内に住む山内さん、福岡から来たるゥさんも来て、賑やかに鍋。
「鍋の蓋が、あーつーいー、って文句が倉地さんの歌に出てきそうだなあ」と例によってくだらぬ思いつきを述べると、倉地さんは「なんでも詩にすると、思うなよ」と目玉をきろりとさせてにこにこする。なんでも詩にすると、思うなよ、という文句は、倉地さんの歌に出てきそうである。
外山さんと話すのは初めてだが、プレイは何度か拝見している。以前、京都で見たウォータードラムを使ったプレイにはしびれた記憶がある。小さい頃から風呂であんな風に遊んでいたんだそうだ。
ふと見ると、わたしとゆうこさん以外は全員九州人。山内さんの渓流をどこまでもたどっていく話や、外山さんが見たという宮崎奥の切り株の話を聞いていると、そこはかとなく、九州の山深い感じが、駄弁の中にも漂う。バクさんの初霞をぐんぐん呑む。
20081114
八坂町 2008.11.13



夕方、大分へ。新幹線の中でずっと論文の直し。大分駅に着いたら仕事帰りのバクさんが迎えに来てくれた。明日はそのバクさんのバクまつり。
バクさん宅で本日は宿泊。おみやげのふなずしを肴に夜半まで。
20081113
もうすぐバクまつり@大分
かえるさんソロで大分に行きます。大分は演奏するのももちろん、行くのが初めて。
何を食いまくるか。カボス?お湯?
第4回バクまつり 〜うたうのだ!うたなのだ!〜
 2008年11月15日(土)
2008年11月15日(土)
20:00- (19:30 OPEN)
予約:2300円
フライヤー持参:2000円
AT HALL(大分)
097-535-2567
(←クリックでチラシ拡大)
【出演】
☆るゥ(Vo,G)「雅だよ雅、蝶丁」 from福岡
2006年アコースティックギターでソロ活動開始。
しばらくソロ活動は控えてたが、今回「バクまつり」で久しぶりのソロ演奏。
言葉がうたになる瞬間を感じてくれたらうれしいな!
☆三沢洋紀とゆふいんの森(三沢洋紀Vo,G、足立貴裕G、河村浩Dr、南いちこB)
突出したソング・ライティングや個性的なメンバーゆえ“関西アンダーグラウンド・シーンの象徴”と言われたバンド「LABCRY」のフロントマン三沢洋紀が、大分に戻り出会った仲間たちと組んだ九州限定ユニット。
☆外山明(Dr,Per) from東京
渡辺貞夫、松岡直也らと、そのキャリアをスタート。
今堀恒男らとの「ディポグラフィカ」他、ジャズ、ボサノバ、歌手のUAやeyoなどでの活動も多い。
セネガルやアジア等の民族音楽からのオファーも多く、日本の代表的なドラマーであるだけでなく、他に例のない個性と魅力は多様な場所で純粋な評価を得ている希少な存在。
☆倉地久美夫(Vo,G) from福岡
80年代東京にて活動。鈴木慶一プロデュース「ビックリ水族館」アルバムでデビュー。
自身のバンドで活動後、93年以後福岡に移り、トリオ※外山明Dr/菊地成孔Sax や弾き語り、共演等を全国で行う。
02年「第2回 詩のボクシング全国大会」優勝。5枚のアルバムを発表。
☆かえるさん(Vo,G) from滋賀
報われないのに夢見がちな歌詞とメロディーを携え、さまざまな編成で演奏活動を行っている。
07年、かえる目(かえるさん、宇波拓、木下和重、中尾勘二)で、compare notes(map)から1stアルバム「主観」をリリース。ジャケット画は倉地久美夫。 現在2ndアルバム製作中。
細馬宏通としての執筆活動でも知られており、著書も複数出版されている。
【予約は下記へどうぞ】
『バクの夢』: bakuyume_ken@ybb.ne.jp
AT HALL(大分): info@athall.com
20081112
沼 402: アートを公表するということ
 ヘンリー・ダーガーの話(つづき)
ヘンリー・ダーガーの話(つづき)
この放送をダウンロードする
関連リンク:
畸人研究第25号「アール・ブリュット・宮間さん」
20081111
池田朗子「光景」(青幻社)
あこちゃんから、最近作の「光景」が届く。
グラビア記事を用いてその一部を切り起こして見せる池田朗子のインスタレーションを初めて見たのは、2003年のことだった。それから何度か彼女の起こした立ち人たちを見てきたが、そのときは、どちらかというと、立ち上がった小さな人の存在感に圧倒されていたように思う。(→日記:20050703)
写真を立版古のようにおこす技法というと、糸崎公朗さんらの「フォトモ」が思い浮かぶ。ぼくは「フォトモ」の薄い街も好きなのだが、池田朗子作品には、どうも「フォトモ」と似て非なる感じがあると思っていた。それが何なのか、なかなかうまく言葉にできていなかったのだが、ようやく今回、これかとわかったことがある。
じつは彼女の作品の大きな魅力は、立ち上がった人だけでなく、立ち上がった人が残してきた平面にある。
今回の写真集では、立ち人がアップになったものが多い。そして目を引くのは、その人の足下だ。
足下にはむろん、その人が残してきた風景が広がっている。が、それだけではない。グラビアのつるつるしたページに、立ち人たちの微かな反映が映っている。そのことで、グラビアは二重の意味を帯びる。ひとつは、写真風景を写しこんだ面としてのグラビア。もうひとつは反射面、つまり、立ち人たちのいる世界を写し込んだ面としてのグラビアだ。
この二つが重なることで、立ち人たちが残してきた風景は、あたかも、世界を写すために自らの鮮やかさを殉じ、自ら面に埋葬されているような、不思議な感じを引き起こす。スキーヤーの足下で、ゲレンデもそれを喧伝する文字も、まるごと滑走面となり、クラブを振り上げたゴルファーの足下で、ビルの屋上とそこから見下ろされる階下は、等しくボールを打ち込むためのフェアウェイとなる。滑走面はスキーヤーを映し出し、フェアウェイはゴルファーを映し出す。
これまで、彼女の作品が妙にせつないのは、立ち人のせいだと思っていたのだが、じつは、せつないのは、立ち人の残してきた平面のほうでもあった。
そして、じつは、このせつなさは、写真が本来持っている性質でもある。ダゲレオタイプの昔から、写真という面は、単に事物を写し込んだ面ではなく、そこに世界の反映を写し込む面でもあった。写真上に定着させられた世界は、そこに照り返るこの世といつも交錯し、この世に浸されることを受け入れる。
池田朗子の立ち人たちは、そうした世界から危うく立ち上がってきた使者のようだ。彼や彼女は、グラビアの一部として立ち上がりながら、自らの姿を、かつて自分のいた面に映し、改めて自分を世界に浸している。
ものすごい夕焼けを抜けてきた



ときどき手に負えないほどの夕焼けに覆われることがある。
写真に撮っても無駄な抵抗なんだけど。
彦根から京都へ。夜、高校の同級生と二十年ぶりくらいに会って飲む。
20081110
論文直し、会議などなど。
角さん、御子柴さんと、来月12/6の信楽shiroiro-ieライブの相談。とりあえず「歌と鍋」というタイトルに決定する。信楽焼の飯釜で炊いたおにぎりはうまいらしい。そのおにぎりを頬張りつつ、お酒もしくはお茶も飲みつつ、聴いていただくとという趣向。
20081109
沼:401 ヘンリーダーガーは今年で116才になる。
 オバマ演説のシカゴとダーガーのシカゴ。絵を見とどける時間。
オバマ演説のシカゴとダーガーのシカゴ。絵を見とどける時間。
この放送をダウンロードする
*訂正:放送中、ダーガーのいた施設を「シカゴ市内」と言ってますが、実際には、シカゴから200km以上離れたイリノイ州の施設でした。
「アール・ブリュット」展レクチャー「身体は繰り返す 美の術と身体の術」@滋賀県立近代美術
滋賀県立近代美術館へ。山本さんと浅井さんにご挨拶してから、さっそく展示を見て回る。例によって、あらかじめ送っていただいた資料は(じつは)あまり見ないで、展覧会で見た感覚をできるだけ掘り下げていく。掘り下げるといっても1時間半ほどなので、映像はほとんどすっとばして、作品だけを見ていった感じ。それでも手元のノートはどんどん埋まっていく。いつもなら3時間はかけていただろう。
二時から「身体は繰り返す 美の術と身体の術」というタイトルで話す。オバマ演説とダーガーの生涯を対比させるところから始めて、アール・ブリュットと呼ばれる諸作品に(おおよそ)共通するいくつかの性質、とくに「見せることへの関心のなさ」と形式の必然性との関係について話す。ダーガーで30分、残りの人の作品について1時間ほど。
「作者」「作品」「(作者の)意図」というのがあらかじめあるかのようにふるまっている美術界に対して、今回の展示「作品」は再考を促している。美術館や画廊、あるいはストリートという、公的に承認された場所だけが美術の場なのか、という点に対しても。
・・・というような話を、「美術館」の講演でやっていいのかという気もするが、やってしまったものはしょうがない。
質疑応答の中で、ある養護学校で教えておられるという方から「いままでは絵を描くときに黒を真っ黒に塗れない子を見て、ちゃんと塗りなさいと言ってたのですが、そうじゃない塗り方があるんだということに気づいて、よかったなと思いました」という感想をいただいたのがうれしかった。それで、そうか、学校教育では、黒は真っ黒に塗るべし、という方針があったりするのかと、逆に問題に気づかされもした。
終了後、来場されていた方々とあれこれ話。中で、小暮宣雄さんと話していて「見届けるの『届』ってことばが気になる」「パフォーマンスを見届けるということはできるが、絵を見届けるとはどういうことなのか」という話になる。高橋さんとは「痕跡」という考え方について話す。それらについて考えたことの一部を、沼401で語っている。
20081108
わかってくれない
昨日はこころとからだ研究会で同僚の中村さんの発表があった。ひきこもり・不登校・ニート・摂食障害、リストカットなどの当事者の声を集め、そこに共通する「わかってくれない」ということばから何かを引き出そうとする試み。
もちろん、これという正解がある話ではない。集められたことばを読みながらいろいろ考える。
まず、自分に「しるし」がないことを悩んでいる人が多い。
五体満足で、普通に健康で、経済的に(いまのところ)さほど不自由しているわけでもない。にもかかわらず人と会って話したり、外に出て行くことができない。そこには明らかに不全感があるものの、それはあくまで精神的なもので、その精神に対応する肉体的な「しるし」がない。だから「しるし」によって自分の不全感を説明することができない。「なぜ人と会えないのか」「なぜ外に出れないのか」と問われる。問われても、相手が納得するような「しるし」を自分は持っていない。結局、相手は、怠けや怠慢が原因だと思い込む。
「わかってもらえない」相手というのは、家族や身近な人だったりする。家族は、すでに引きこもっている彼や彼女を、追い出すのではなく、家の中に居させてあげているのだから、ある意味で、家族はすでに彼や彼女を「受容」しているのだといってもよい。しかし、彼や彼女はそのような「受容」を求めているのではない。ただ現状を、しかたがないものとして放置するような「受容」ではなく、本人の「味方」になるような受容が必要とされている。
しかしいっぽうで、どんなことが起これば、本人にとって「この人は味方だ」と思えるのか。その具体的事例を示している例は、驚くほど少ない、と中村さんは言う。
現在に具体的な不満を持っている人の問題には、少なくとも解決のゴールが見える。金がない、肌の色で差別される、といった問題は、もちろん簡単には解けないし、具体的な解決策があるとは限らないが、少なくともどこを目指せばいいのかはわかる。それに対して「わかってくれない」という問題には、具体的なゴールがない。そもそも「何を」「誰に」わかってもらいたいのかが明らかではない。あるいは、それを言うべき相手がいない。
これはどうやら、問いがあって答えを考える、という事態ではない。ここで求められているのは、要求に対する解決という関係ではないし、要求したことに適確に答えてくれる人でもない。
むしろ、何が要求かもわからない状態で、とりあえず耳を傾け、長い時間をかけて聞き続ける人が、求められているのだろう。言い換えれば、家族は、ただ彼や彼女を受け入れるだけではなく、改めて「聴く人」となって、彼や彼女の前に現れることが、求められているのだろう。
聴く、といっても、ただ何のきっかけもないところで、いきなり彼や彼女がぺらぺらとしゃべり出すわけではない(それは「要求のある人」のやることだ)。ことばがぽつぽつと話されるための、種のようなことばが必要となる。
それは「学校に行くのはどうだろう」ということばでもかまわないかもしれない。ただし、解決策としてではなく、聴くためのきっかけとして。
沼:400 しゃべると忘れる。人が覚えている。
 声の論理。かえる目レコーディング。キリンジ「エイリアンズ」。
声の論理。かえる目レコーディング。キリンジ「エイリアンズ」。
この放送をダウンロードする
20081107
書き起こされた声
dotimpactさんが、ラジオ 沼#397をなんと全文書き起こしてくれた。
自分で話したことが文字化されると、つじつまの合わないことだらけなのに改めて気づくいっぽうで、え、そんなこと言ってたっけとけっこう感心したり。しゃべりながら考えたことって、しゃべる時間で作り出される論理で生まれるので、自分でもけっこう忘れてたりする。
とにかくおもしろいので、ここに転載させていただきます。一部表記を直した以外はそのまんま。感謝!>dotimpactさん。
沼 397: 花火と飛行機 (2008.10.29)
こんばんは、「ラジオ 沼」かえるさんです。
昨日はですね、アーティスト集団のChim↑Pomが広島で行った、プレイベントといいますかね、「ピカッ」っていう、カタカナを空に絵が描いたことをめぐっていろいろ話をしたわけです。
実はそのあと、その数日後に一見すごくよく似た催しが行われましたね。それは蔡國強というアーティストが、原爆ドームのうしろに、黒い花火を打上げた。という、まあ、作品ですね。で、これには橋の上から何人もの市民が見に行って、拍手も起こったっていうような話を聞きました。youtubeでもそういう映像が上がっていましたね。
まあ、この二つは一見するとすごく似てるんですよね.両方とも広島の空、というものを問題にしている。そこに何らかの、空にないものをつくりあげる、という点ではたしかにすごく似てるわけですわけです。そしてどちらもある意味で煙なわけです。だからWebには実際、なんでこの国際アーティストだからか知らんけど蔡さんのアートは評価されて、Chim↑Pomのやったことはなんであんなに非難されなあかんのと。変われへんやん、という意見が、まあ、ちらほら見える。
僕はね、結論からいいますと、全然違うなあと思ったんですね。僕は両方とも新聞あるいは youtubeでしか知りませんから、生で見たわけではないんですけども、だから、ほんとにそこにいたらどういう感じがしたかなっていうのは残念ながら憶測でしか言えないんですけども、それでも伝わってくることだけを考えても、全然ちゃうやないですか、ちゃうじゃないですかっていうことを今日は言おうと思うんですけどね。
何が違うかっていうと、あの、まず端的に花火ってどういうもんやっていう話なんですね。花火は飛行機のスモークとぜんぜんちがうんですよ、何が違うかっていうと、音がするんですね、圧倒的な音がしますね。何千発の花火が使われたという話ですから、ものっすっごい人の耳をつんざくような音がしたはずです。圧倒的な音がしたはずですよね。これは飛行機雲なんかと全然ちがう、つまり、もしかしたら気がつかないくらい、あ、また飛行機が飛んでるなぐらいのぶーんって音が鳴るのと、それから、空を見てない人さえも振り向かさせるような、何事が起こったんか、と空を見上げさせるような、圧倒的な音を鳴らすのでは、全然やってる事が違いますね。
そして、その音が鳴り始めてから鳴り止むまで、いわば人を思わずひきつけてしまう、ひきつけるというよりは強制的に振り向かさせるような力を持った時間で、しかもそれは、2分足らずで終わってしまう。この時間の短さも圧倒的に違いますね。昨日も言いましたけども、午前中数回にわたって何度も描かれた、いつからいつまでとは分かりません、そういう、始まりも終わりもよく分からない、というやりかたと、それから、ここから始まってここで終わり、というやり方は全然違うね。
もちろん蔡さんのイベントっていうのは予告されてたわけだから、実際それを待ち構えていた人たちがいっぱいいて、で、さあ始まると思ってね。もちろんその中には非常に反感を持ってる人もいたでしょうね、なにをしやがるんやごらゆうぐらいの気分で見てた人もいると思う、その人たちが納得したかどうか僕は分かりませんけども、しかし少なくとも、そういう人たちですら、今から何が始まるんだろうというのもあって、そうすると大音響が鳴り響いて、そして黒い花火があがる。そしてそれが、ある時間にぱっと終わる。あとに煙だけがのこる。それも消えていく。そういう時間ですね。そういう時間が、非常に考え抜かれて構成されてたと思うんですよね。まあ似たようなことを言ってますけども、それはそうなんだろうな、というのはyoutubeを見てて、僕は思いました。あれは現場にいたらもっと、こうなんかいろいろ考えたのかなって思いますね。見るアングルによっても違ったでしょうね。原爆ドームの背景に上がる、っていうアングルで見た人には、なんか、何とも言えない思いがあったでしょうし、別のアングルから見た人も、なんか無名の空にこういうのが上がるってどういうことやろう、ってすごい考えたと思う。
あと花火っていうのが、すごく飛行機雲と違うのは、花火って、花火の上がってる場所に人がいないんですね。花火っていうのは地上から打上げられて、その打上げてる主体である花火師すらもいったんそれが打上げられてしまうと、どんな風になるかっていうのは手がとどかない、もちろん入念に仕込む訳ですけども、入念に仕込んだとしても、いっぺんもう打上げられてしまうと、それが爆発する場所に人がいることができない。もう手が届かない場所なんだ。ですから、その打上げる花火師自身も、アーティスト自身も地上にいて、見てる人も地上にいて、花火だけが空を、占めている。こういう自体が花火ではおこるわけですね。花火が、短い時間ですけども、いわばこの世の中を専制するわけですね、占有するわけです。
それに対して飛行機で字を描くって言うときは、飛行機に乗ってる人がいるわけですよ。あえていえば、あたかもB-29が、空を飛ぶようにね。人がそこにいるわけですよね。しかもその人からは、基本的には自分がやってることが見えない。もちろんもしかしたら、最近のテクノロジーのこともあるから、飛行機にモニターを積んで、そんで自分が今やってることを見ながら多少は飛べるでしょうけども、それでも、飛行機に乗ってる人は少なくとも地上にいる人のような感覚を味わう事は出来ないね。だから地上にいたらどんな感じがするんだろう、ていうところから切り離された場所で、自分の職務を全うするしかないんですよね。「ピカッ」って文字を書いてください、こんなアングルで、これくらいの大きさで書いてください、って言われたら、そこで、描くしかないわけですよね。地上で今自分が乗ってる飛行機が吐き出してるスモークをみたらどんな感じがするんだろう、ってところから切り離されて、坦々と職務をこなすわけですよね。そういう時間なわけです。で地上から見てる人にとってもそういう時間なわけですよね。自分から切り離された、一人この地上から離れた主体が、いま字を書いているっていう、そういうのを見るわけですよね.だから、誰でもない字がそれを専制しているというよりは、その字を書いてるあのひとは何故あそこにいるんだろう、というのを強烈に感じさせると思うんです.あれはいったい誰のために、あのパイロットは、あの飛行機に乗ってるひとは何のためにあれををやってるんだろう、ということをどうしても考えさせるね、そういうやりかただと思うんですよ.
いま僕が言ってることはまさに、なんというのかな、「空爆」という出来事を地上から見た人が必ず思うことだと思うんです。彼は、何故この地上にいないで、あそこで、しかも、自分が何をやってるかっていうことから切り離されて、自分がやってることが地上になにをもたらすのかっていうことから切り離されて、何故あそこにいるんだろう、ていうことを、まあそんなん考える暇も最初はないと思うんですけどね、少なくとも、飛行機を見るときに、しかもその飛行機が地上になにかをもたらそうとしてるときに、僕らは考えると思うんですね。考えてしまう。
まあ、そういうことも考えていくとね、どうなんでしょう、その、「ピカッ」っていう字を、飛行機で書く、っていうのがね、僕なんかこう、ぜんぜん焦点を結ばないんですね。もしかしたらChim↑Pomの人たちにはそれなりの意図があったんかもしれんが、なんかこうね…わからへんねんな。たとえばですよ、彼らが自分で飛行機の免許とって、自分で自ら字を書くっていうんならまだ、そこまでして、とかねいろいろ考えさせると思うんだけど、うーん、自分たちは地上にいて、パイロットの人にっていうか飛行機会社の人に頼んで書いてもらって…「ピカッ」かあ。って思うんですよね。なんかぜんぜん、こう、やってることが焦点を結ばないんですよね…。
で、まあ、いろいろ考えて、やっぱりね、うーん、彼らには酷な言い方ですけども、さまざまな面でズサンだったんだろうなって思うんです。
僕、結局ね、こういうアートと俗に呼ばれるものが成立するかどうかっていうのは、表面的な形式が問題なんじゃなくって、それを実現するときのディテールだったり、それを実現するための準備だったりっていうとこがほとんどだと思うんですよね。で、それは形にあらわれると思うんです。つまり、黒い花火を上げようと思う、これは誰でもある意味思いつくと思うんですよね。誰でもというかちょっとしたアイデアで確かに思いつくことだと思うんです。でもそれをいざ実現するとしたときに、そこにはいろんな困難がもちろん待ち構えているわけですね。それを、一個一個解決していく過程で、やっぱりアーティストは、これをどこに上げるべきなのか、それはどんな時間となるのか、そこではどういう事が起こるのか、もちろん最後まで予測はできませんけど、少なくともそれを見届けてもらうためには、何が必要なのか。ということをそのプロセスで考えると思うんですね。それが形になってゆくっていうのがひとつアートの重要なポイントやと思う。
僕らが、僕らがというか、思想的に、そのアートの内容に賛成の人も反対の人も、それを、反対やけど認めよかなと思ったり、見届けようかなって思ったときに、そこではなにが起こってるかっていうとね、たぶん、そのアートとして行われたもの、あるいは作られたものっていうのはこの世の人に捧げられてないんですよね。もしこの世の特定の人に向けてそれが行われたものだったとしたら、「おれは反対」「おれは賛成」っていうレベルの話になるんですよ、どうしてもね。おれ捧げられたから支持とかね、おれ捧げられてへんから支持しない、とかそういう話になると思うんですよね。
結局、いろんな人に見届けてほしい、見届けてもらうためにこうしようこうしよう、といういいろんなプロセスを踏むうちに、それは何になっていくかっていうと、結局この世の人ではない、この世ではない人に捧げるものに、なっていくと思うんです。あの世の人、別に死んだ人とは限らないけども、未だこの世に産まれてきてない人でもいいですけども、とにかく、なんていうかな、あなたに捧げます、ではなくて、ここにいないひとに捧げますっていう、そういう形をアートはたぶんとると思うんですね、つまるところ。で、そういう形をとったものだけが、だけがっていったら言い過ぎかな、今、なんか勢いで言ってますけども、そういう形をとったものが、見る者に、ああ、私もこの世にいない人に捧げようと、この、この世にいない人にささげられてるこれを見届けようって気になると思うんです。それはなぜかっていうと、その、アートの持っている形式というか、そのアートの持っている態度かな。態度が、まさにこの世にいない、この世ではないものに向けられてるからなんですよね。この世ではないものにむけられているものを見ると、僕らはこの世ではない場所に、まなざしを、まなざそうとするんだと思うんですね。つまり、その作品に込められてる態度に、添おうと思うんじゃないでしょうか。それが見届けるということだと思うんですよね。
そいじゃまた。
20081106
声の召喚
オバマの演説を聴いていると、つくづくアメリカの政治というのは弁論術の歴史であったのだなと感じる。
そして、オバマの巧いところは、そうした弁論の歴史を汲み取り、先人のことばを自分の言葉に重ねているところだ。
彼が話すと、歴代の大統領や黒人指導者の霊が召喚され、彼の声に重なる。それは、彼が歴史的できごとをコンパクトに言い表し、その頂点で「声」を引用するからだ。声は、そこまで並べ立てられた歴史的場所や時間を引き連れて、いまこの場所にやってくる。
たとえば先の演説で、公民権運動の象徴的場所を次々と挙げてからキング牧師の「We shall overcome」を引用するくだり。
人々はオバマを通してキング牧師の声を聞く。そして人々は、牧師が語ったことば、黒人の苦難の歴史を乗り越えるのだ (「We shall overcome」) という未来形のことばが、いままさに現実となり、黒人大統領の誕生となって、「overcome」されたことを知る。
「We shall overcome」というの声の指し示している場所と時に、自分たちはいま、居合わせている。キング牧師がかつてアラバマから発した声の指す場所と時に、彼が予告した未来に、居合わせている。
声によって、声の発せられた場所と声の届いた場所とを結ぶ回路が開ける。その回路を通じて、モントゴメリーが、バーミングハムが、セルマが、公民権運動が行われてきた場所の記憶が一気に流入してくる。
演説しているのはオバマだが、声はもはやオバマだけではない。先人の声、先人の記憶が彼の声に重なり、この場を覆っている。
このような感覚にひたされた聴衆が、熱狂しないはずがない。
このような声の歴史を、わたしたちは持ち合わせていない。
現在の日本では、歴代の政治家の声をこのように召喚する風習はない。安倍晋三が総理大臣になったとき、多くの雑誌が「岸信介のDNA」というような言い方をしたが、彼の口から岸信介の名言がことあるごとに飛び出して、先々代の政治性の輝きを憑依させた、というようなことはなかった。「美しい国」「戦後レジーム(からの脱却)」といったことばを聞いても、いったい誰がかつてそのようなことばを声にしたのかを言い当てるのは難しかった。もちろん、かつて誰かが随筆や文書に書いたことばなのだろうが、それらは、血肉を伴った声として繰り返されてはこなかった。
そもそも、引用されたとたんに万人の誇りが喚起されるような政治的声というものを、日本は持っていない。
政治の声は読み上げられる。文書に書かれていることを、文書に書かれていますというトーンで読む。そのことによって、自身の声ではなく、文書に責任を預けることができる。読み上げられることばには、文書の論理だけがあって、声の魂は抜かれている。
日本で「美しい国」とか「この国の誇り」といった表現が空疎になってしまうのは、おそらく、わたしたちが依るべき過去の声を持たないことが原因なのだろう。
歴史的経緯はある。敗戦を境に、声は屈曲した。かつてこの国を覆った声は、禍々しい戦いへの鼓舞であり命令であった。うかつに声を引用すると、声の主である霊のみならず、多くの異なる霊の怨念を背負ってしまいかねない。
輝かしい声ではなく、低く頭を垂れて聞く声。ただ読み上げることだけが許される声。わたしたちが負っているのは、そのような声の歴史であり、わたしたちは、うかつに声に恍惚となるわけにはいかないのである。
このあたりに、玉音放送のことを考えるヒントがあるかもしれない。
20081105
106才を折り返し、月に触れる
オバマの勝利演説はすごかった。
とりわけ後半、106才の婦人の指先が電子投票スクリーンに触れる瞬間を起点に、過去106年と未来106年を折り返すくだりは、壮大なる名調子である。そこで語られている歴史は、多分に紋切り型であり、いかにもアメリカ的まとめ方なのだが、そうしたことも忘れさせるほど、コンパクトで鋭いことばの対比が重ねられている。月面にタッチする足と電子投票スクリーンにタッチする指とを重ね合わせることで、その場にいる人、投票を終えた人々に、月に触れたような衝撃を与えている。
あちこちのサイトで全文を読めるが、以下のリンクをとりあえず貼っておこう。
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/nov/05/uselections2008-barackobama
以下、その後半部分。
この選挙では、数々の初めてのできごとが、そして多くのエピソードがありました。それは何世代にもわたって語り継がれるでしょう。でも、今夜わたしの頭に過ぎるのは、アトランタで一票を投じたという一人の女性のことです。彼女もまた、他の何百万人もの人と同じように、行列に並び、この選挙に自らの声を投じました。けれども、ただひとつ違っていたのは、彼女、アン・ニクソン・クーパーは106才だったのです。
彼女は奴隷制がようやく終わりを告げた世代に生まれました。道には車もなく空には飛行機も飛んでいませんでした。彼女のような人は二つの理由で投票できませんでした。ひとつには女性という理由、そしてもうひとつには肌の色という理由で。
今夜、わたしはアメリカで彼女が過ごしてきた20世紀に思いを馳せます。痛みと希望に、苦闘と進歩に、無理だ we can't と言われてきた日々に、それでも突き進んできた人々に、彼らのたずさえていたアメリカの信条に -- Yes we can.
女性の声が封じられ彼女たちの希望が潰えたときにも、彼女は生きていました。そして、女性たちが立ち上がり声を上げ投票権を手にするのを見ました。Yes we can.
黄塵地帯が絶望に覆われ、国中を不況が覆ったときも、国民がその脅威をニューディールによって、新しい職によって、新たな公共目的に目覚めることによって乗り越えるのを、彼女は見ていました。Yes we can.
爆撃が湾に落とされ、暴虐が世界を脅かしたときも、彼女はそこにいて、当時の国民が気高く立ち上がり、民主主義が守られるのを、目撃しました。Yes we can.
彼女はそこにいました。*モントゴメリーのバス、バーミングハムの放水、セルマの橋。そしてアトランタからきた一人の牧師。その牧師は人々にこう言いました「We shall overcome. われわれはきっと乗り越える」と。 Yes we can.
一人の男が月の上に降り立ち、一つの壁がベルリンで倒れ、世界はわたしたちの科学力と想像力によって一つにつながりました。そして今年、この選挙で、彼女の指は電子スクリーンの上に降り立ち、彼女の一票を投じました。アメリカで106年の人生を過ごし、最良の時も最悪の時も知っている彼女は、知っていたのです。アメリカがどう変わりうるのかを。Yes we can.
アメリカ、わたしたちは遠くまでやってきました。多くのことを見てきました。しかし、まだまださらに多くのことをやらねばない。だから今夜、わたしたちはわたしたち自身に問おうではありませんか。もしわたしたちの子どもが次の世紀まで生きるとしたら、もしわたしの娘達が幸運にもアン・ニクソン・クーパーのように長生きしたとしたら、彼女たちはどんな変化を見るのか。わたしたちはどう進歩していけるのか?
今こそこの問いに答えるときです。いまこの瞬間こそわたしたちのもの。いまこそわたしたちの時なのです。人々を仕事に就かせ、子ども達に門戸を開く時。繁栄を取り戻し、平和への足がかりを作る時。アメリカン・ドリームを再び宣言する時なのです。もう一度確かめましょう、根本的な真実を、なによりもまず、わたしたちが一つであることを、息をしていること、希望を持っていることを。そして冷笑や疑念に会っても、無理だ we can't と言い張る人に会っても、わたしたちは答えましょう、あの、人民のスピリットを変わらず表し続けてきた信条を唱えて。Yes We Can.
ありがとう、みなさんに神のご加護を。そして神のご加護がthe United States of Americaにあらんことを。
(Barak Obama's victory speech in Chicago, Nov. 5 2008 和訳:細馬)
*「血の日曜日」の歴史とキング牧師の演説を指している。
20081104
科研費書類最終段階。会議など。
20081103
朝一の新幹線で彦根へ。休日なれど振替講義日。そのあと、ゆうこさんの車で信楽へ。傾斜地に据えられた窯元を訪ね歩く。県大生がかかわった「shiroiro ie」のオープニング。いろんな人と話す。来月はここで弾き語り。
20081102
かえる目レコーディング(第二日)
午前10時にヒバリスタジオへ。まずは宇波君が一人で「じゃんけん式」。そこにボーカルをオーバーダブ。いつもはハイトーンで歌っているのだが、「ペルシヤ風で・・・」という宇波君のわけのわからないリクエストにより、わたしの考えるペルシャ風で歌ってみる。すると「もっと知的な感じで・・・」と、これまたわけのわからないリクエストにより、知的にかつペルシャ風に歌ってみる。我ながらとんでもない歌唱となった。
二人で「北クエスト」「やさしさ」「のびたさん」「渋谷」の取り直し。午後、木下くんと中尾さん登場。バイオリンとドラム、クラリネットを入れていく。
ドラムの録音はどれもほぼワンテイク。およそ30分で終了する。超ハイスピード。
驚くべきことに、夕方には、17曲の録音がとりあえず終わっていた。たった二日。嘘みたいだ。
録音したものを聞き直すうちに、木下くんが「ネオアコってこういうことっしょ」と突如「のびたさん」のコーラスをつけ始める。あまりにおかしいので採用。
このあたりから、抑えられていた何かが噴出し始める。某曲にはクイーカ演奏を追加。全員笑いをこらえ続ける。
さらに前アルバム同様、党員コーラスを入れることに。そして手拍子も。中尾さんの演奏する「時計」も加える。レコーディングの楽しみを刻印する時間。
まだ夜は若い。宇波君のラフミックスを待ちながら、トランプに興じたり、無責任な創作活動に勤しむ。そして二時間後、早くも仮CD-Rが出来上がる。
一同で聞き入る。なんだかやたら陽気なアルバムになりそうな予感。
東中野でカレーを食って解散。
20081101
かえる目レコーディング(第一日)
朝、新宿で宇波くんと待ち合わせ。まずは、レコーディング曲を簡単に確認。簡単に確かめた結果、17曲あることが判明する。これ、1つのアルバムに収めるのか? トータルタイムも想像つかず、早くも前途は多難のはずだが、気持ちは楽観。
朝早くからセッティングをしていた宇波くんは、いくつか足りない機材に気づいたという。マイクケーブルとポップガード(息がマイクを吹くのを防ぐ金魚掬いの網みたいなやつ)を買う。
そうこうするうちに昼。武蔵野うどんを食って、ヒバリスタジオへ。まずは二人でできる曲をかたっぱしから吹き込む。「書架」「とんかつ岬」「とんかつ飛行」「恋のレストラン」「管の歌」「渋谷」「記憶術」「夏に生まれた」「馬喰町」「三輪車」「流出」。三時頃には七曲、残りも六時前には吹き込み終わる。コードの確認をいくつかした他は、ほぼ1テイクずつ。
木下くんが登場、「SPアワー」を録音。さらに中尾さんも来て、ドラム、クラリネットをかぶせていく。
とさらっと書いたが、じつはこれは尋常なレコーディングではない。
通常、別々にレコーディングするときは、先にリズムセクションを録音するか、ドンカマを使ってタイミングを合わせるものだ。ギターと歌が奔放に録音されたあとにドラムが入るなどということは、普通はありえないし、やろうとしてもドラムが合わせるのはほぼ不可能である。「いやあ、多重録音のたまもの!」と中尾さん。中尾さんは、中学時代から自宅で多重録音に親しんできた。すでに録音してしまったトラックにパーカッションを合わせるという経験をやたらと積んできた中尾さんだからこそ、ドラムの後入れができる、というわけ。
家猫エレジーを三人で同録。さらに「SPアワー」「とんかつ岬」「恋のレストラン」のドラム入れ。
というわけで、なんと一日で13曲を吹き込んだ。異様なハイペース。
近くの居酒屋かんじで一日目の打ち上げ。
to the Beach
contents