The Beach : 2009
細馬 宏通
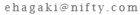
<<前月 | 翌月>>
20090430
他人のためにお金を使ったほうが幸せ
休日にはさまれた木曜日は一日ゼミと講義の日。
御子柴さんの持ってきた論文がなかなか面白かった。昨年のサイエンスに載っていたもの。
Spending Money on Others Promotes Happiness
社会心理学で、収入と幸福度の関係に関する議論は山ほどあるけれど、得たお金をどう使うかに関する議論は意外に少ない。というわけで、著者のダンたちが注目したのは、「お金の使い方によって幸福度はどう変わるか」というもの。彼女たちは、まず平均的なアメリカ人に、年収と支出のカテゴリーを聞いた上で自分自身の幸福度を評定してもらった。すると、明らかに、他人に対してほどこしている人ほど幸福度が高かった。この傾向は、収入が安定してある程度基本的な暮らしができている人でとくに高いという。
彼女たちは被験者に$5もしくは$20を与えて、それをどう使ったか、その後の被験者の幸福度はどうなったかを調べる実験も行っている。この実験でも、チャリティなどの他人へのほどこしをした人のほうが幸福度が高かった。ところがおもしろいことに、人々に「お金を何に使うのが幸福だと思うか」と質問すると、「自分のために使うのがしあわせ」と答える人のほうが多い。つまり、直感的には、お金を自分のために使うのが幸せでも、じっさい使ってみると、じつは他人のために使ったほうが幸せ、というわけ。
彼女たちはこの問題を、Lyubomirskyらが提唱している理論をもとに説明している。旧来の幸福度予測は、生活環境の中の収入やジェンダーや宗教団体への加入といった要因に注目してきたわけだけど、リュボミルスキらによれば、これは、問題設定が間違っている。というのも、人は生活が安定するとそれに慣れてしまうから、長期間単位で見ると、こうした要因は幸福度の上昇に寄与しない。だから、もっと人が主体的に活動できるような要因のほうが幸福度の維持には重要である、ということになる。ダンたちはこの理論と調査結果を結びつけて、「人のためにお金を使うこと」が幸福度の維持に重要である、と結論づけている。
2008年、この論文の出た頃、サブプライムローン問題が盛んにニュースとなり、アメリカ経済が袋小路に入りかけている感じはすでに世間に広がっていた。そのあと、リーマンショックが来た。ひたすら自身のために金を儲ける、というライフモデルに変わるものが、学術論文の世界でも求められ始めているのかもしれない。
20090429
迅さん潤さんパーティー
徳正寺へ。扉野さんと鈴木潤さんの結婚披露パーティー。入口で渡されたしおりが、見ただけで羽良多さんと判るデザイン。表紙から裏表紙まで美しい絵と詩の数々。本堂では次々にすばらしき演奏の数々。潤ちゃんがあんなにウクレレと歌がうまいなんて知らなかった。どなたのお子さんなのか、とにかく「猛毒植物図鑑」を諳んじるのが得意で、「これから言うことは3つあります」と言ってから、三つの猛毒植物について語る。子供なのに(子供だから)間がすばらしい。新郎新婦の父君お二方もなんとも言えない味のあるたたずまいで、すっかり引き込まれてしまった。
夕方、薄花葉っぱ、たゆたう、亀ちゃんと買い出しに。ちょっとしたきっかけですぐ歌っちゃうメンバー。藤井大丸でもそば屋でも鼻歌だらけ。
夜は夜で、ラブラブスパークのごきげんな演奏で始まり、次々と贅沢なライブ。オクノさんの歌は、まっすぐでいいなあ。しみじみとしてしまった。寺川さんの不幸な歌楽し。「健康保険がなーい!」。薄花葉っぱとたゆたうはますます自在で、それでいてちゃんとお祝いになっており、すばらしかった。なかにし礼が訳したという「歓喜の歌」の歌詞。
これらの人々に比べれば、自分は人を祝うことも歌うことも未熟者である。未熟者、ということがわかったのは、よかった。
先日の細川さんのパーティーもそうだったけど、音楽のある宴はいいなあ。
20090428
講義を終えて病院へ。主治医の先生が豚インフルエンザの件で不在とのこと。経過も悪くないので、他の先生にささっと見てもらって帰る。昼、米田さんと成松さんにふかーい話を聞く。お二人とも県大のさまざまな事務方を渡り歩いてこられた「できる人々」で、教員よりも事情通なのである。さらに会議。でもって新入生歓迎会。でもってさらに新任の木村さん、丸山さんの歓迎会。楽しくて久しぶりに飲み過ぎた。
20090427
朝いちばんの新幹線で彦根へ。講義、サーバメンテ、実習。今日はやたらと寒い。途中で熱を出す学生もいて保健室へ。さすがにくたびれた。遅くに飯を食ったらすぐに寝てしまう。
20090426
スタンプショウ三日目
性懲りもなく絵はがきを漁る。さすがに昨日ほどは買わなかったが、プチ発見いろいろ。
みんとりさん、アダチさん、鈴木さんご一行とプチ遭遇。
いとときちゃん、ゆうこさんと飯。
かえる目@パラボリカ・ビス
夕方、大久保の貸しスタジオで練習。新曲を中心に二時間。今回持ってきたのはガットギターで(キーボードは重いので)宇波くんもアコギだったので2ギター編成。毎回、持ち込まれた楽器でアレンジを決めるバンドというのも珍しい。これもメンバーの演奏力あってのことなのだが。浅草橋に移動。
パラボリカ・ビスへ。今野さんとものすごく久しぶりにお会いする。『ステレオ』以来。
お店の一角と聞いていたがけっこう広く、天井も高い。声はよく響くので、マイクなしで。まだ2ndが出回って一ヶ月ちょっとなのに、やる曲の半分以上は新曲。日曜の20:30開始でお客さんが来るのか心配だったけれど、始まってみるといっぱいだった。ありがたい限り。「あの寺にかえりたい」は、なぜかシャウトする方向に。
渋谷タワーレコードで、ユーミンの新譜のそばに、かえる目が置いてあるというウワサ。ほんとかなー。
20090425
スタンプショウ二日目
朝から100均絵はがきの箱をずうっと漁る。
きちんと選別されてビニルカバーのついたやつにももちろん出物はあるのだが、やはり100均のほうがスキマがあって楽しい。ほんとはタンスから出てきたのをそのまま繰るのが一番楽しいのだけれど。
午後、生田さんの出版トークショーに。丹下さんの司会で、生田さん、あほまろさん、わたしというメンバー。絵はがきのことを話し始めるときりがない。トークが終わって、郵趣出版の平林さんも交えて会議室で話し、あほまろさんと100均を繰りながら話し、もんじゃ屋でまた話し、あほまろさんの事務所でさらに話し、ようやく夜半近くに解散。
20090424
スタンプショウ一日目
6Fの展示を見て回る。自分の絵はがき展示はちょっと文字数が少なすぎたなあ。切手のリーフ展示のように、いろいろ構成が工夫できるといいなと思う。次回(があるのか?)はモアベターに行きたい。
7Fの即売場でざっと買う。
夜、久しぶりに金寿司へ。貝づくし。
20090423
木曜は講義とゼミが朝から晩まで。さらに科研の書類を書き、学生の相談。
20090422
新潮社の長井さんが来られる。選書で何か一冊、という話。が、遅筆もいいところの私に確たる約束ができるあてもなく、ひとつ長い目で見ていただき・・・と、例によって例の如くの話に落ち着く。
週末のスタンプショウ展示用のはがきレイアウトと文書作成。ぎりぎりになってしまった。
20090421
夜、シェロー演出ブーレーズ指揮の『ラインの黄金』をDVDで。いやあ、何で今までこれを食わず嫌いしていたんだろう。ずるい、暗い、おもしろい。あれこれ考えること多し。
20090420
今年は書類整理や予算執行が忙しくなりそうなので、綿谷さんに来ていただくことになった。今日は簡単な打ち合わせ・・・のはずが、部屋の段ボールを片っ端からくくっていただくことに。それでもまだ、部屋が片付くには時間がかかりそう。
昨日買った『セヴィリアの理髪師』をDVDで。『セヴィリアの理髪師』を字幕付きで見ると、改めて、Tex Averyの「へんてこなオペラ」のおもしろさが判る。あれ、全く歌詞の意味を考慮せずに、歌の構造だけでアイディアを練ってるんだなあ。そこがすごいところなんだけど。
20090419
今村花子展@ヒルゲード
寺町三条上るの画廊で、今村花子展。左知さん、中村先生と少しお話。絵の具をぼってり絞ったパレット楽し。絵の場合も花子さんの場合は、「置く」という感じだ。画布に置かれた絵の具、パレットに残った絵の具、どちらが絵だろう。画布の下に新聞紙と絵の具の蓋がこびりついているのがいい。
サイエンスカフェ@京大博物館
塩瀬隆之さんのやっておられる「サイエンスカフェ」に。以前、飲み会でお会いした水町衣里さんのお話を聞いたらおもしろそうで、行きます行きますと約束してたのである。
今回のテーマは「しずくをつかまえる」。液体に関する何かを、百均グッズなど安い材料を使って作るという試み。テーマも作り方もじっさいの制作も各班にまかされている。各班には全盲の方が一人いる。だから自然と、視覚以外の感覚に想像力が広がることになる。
一つの班のディスカッションに混ぜていただく。
Oさんが「しゃぼん玉をちゃんと感じたことがないなあ」と言う。Oさんは全盲で、シャボン玉を吹いたことはあるものの、それがどんな形でどんな風に宙に浮いているかを感じたことがないのだという。言われてみればそのはずで、シャボン玉というのは触るや否や「こわれて消える」。
Oさんになんとかシャボン玉(のようなもの)を触ってもらうことはできないか。百均にはスーパーバルーンという、接着剤のような粘液をストローの先につけてふくらます玩具を売っている(似たもので昔よく遊んだ記憶がある)ので、まずはそれを使って、ふくらむ様子を感じてもらうということになった。
さっそく、Oさんに吹いてもらう。これが意外に難しい。この玩具は、最初吹くときにちょっと抵抗感があって、ある強さで吹き込むと突然ぷうっとふくれる。ここで息を緩めて、ほどよいところで息を止めると小さな風船が出来上がる。ところが、Oさんは一気に吹く。風船は何度やってもぱちんとはじけてしまう。「息を緩めてほどよいところで」というのが、Oさんには難しいようだ。
それを見ながら、そうか、自分はバルーンをふくらますとき、息をいつ緩めていつ止めるかを、視覚的に判断していたのだなと気づく。ストローの先の液面がちょっと膨らむその瞬間は、目で見れば明らかだが、息の抵抗感で感じるのは難しい。だから、息を緩めるポイントが判りにくい。さらに、風船はかならずストローの前方へと膨らむとは限らない。先につけた液膜の薄い部分が横からはみ出すようにぷうっといくこともある。おまけに、いったん膨らみ出すと、風船の膨れるスピードは思いがけなく速い。
Oさんは人差し指の先をストローから少し離して構えているのだが、指にバルーンが当たるときには時に遅く、息が強すぎてはじけてしまうのである。人差し指一本で触るというのは、繊細なできごとを捉えるにはとてもいい方法なのだが、このバルーンに関してはどうもうまくいってない。
それでまず、どの方向からバルーンが膨らみ始めても、すぐに判るように、ストローの出口を三本指で覆ってもらうことにした。そして、もし指にバルーンが触ったら、すぐに息を止めるか緩めて、指の感触を確かめながら少しずつ息を入れてもらう。
「ああ、ふくらんできたふくらんできた!」とOさん。これで、何度か、いい感じのバルーンができるようになった。
このチャレンジをOさんは気に入られたようで、余ったチューブを「持って帰って遊びます」と言ってポケットに入れられた。
このスーパーバルーンが「触る玩具」でもあるとは思いもしなかった。
しかし、接着剤のバルーンでは、シャボン玉とはかなり質感が違う。かといって、ただの石鹸水のシャボン玉ではすぐに割れてしまう。そこで、シャボン玉を少し割れにくくすべく、セルロースの粉を石鹸水に混ぜてみる。これだと、少し粘りのある膜になる。触ると割れてしまうことには変わりないのだが、割れる一瞬前に、「触ったな」という感じがする(シャボン玉だと触ったかどうかも判らず、飛沫のかすかな感触があるだけなのだ)。「ああ、ああ、触りましたね」とOさん。ぼくもなんだか、触った気がする。
触った、と判るだけで、形が丸いかどうかはちょっと判らないという。もう少しあれこれ試したかったがここで時間切れとなった。
時間変化を組織化する身体
Oさんとのやりとりは、いろいろと考えさせられた。見ることと触ることとは、単にある一瞬のモダリティが違うだけでなく、感じることの時間変化が全く違うのだ。そして、難しくもおもしろいのは、この時間変化という問題だ。何かを膨らませながら息を調節する、というときに、息と触覚との時間変化をどう組織化し、二つのできごとを関連づけるか。
風船とシャボン玉との違い、というのもあれこれ考える。風船の場合、表面の分子の配列はさほど動かない。ふくらむほど薄くなり、分子間の間隔も広がるのだろうが、配列にとてつもない変化があるわけではない。一方、シャボン玉の場合は、おそらく分子はダイナミックに動いている。小さなシャボン玉のお尻にしたたりかけている滴も、膜の広がりに参加し、分子の供給源となるだろう。玉の膨らみが止まっているときも、表面の虹模様は動き続けている。おそらくはあちこちで薄さが変化して干渉の度合いが変化し続けているのだろう。界面活性剤の分子は、膜状をあちこち動き回りながら、その分子間力によって危うく玉を維持している。風船を触るということは、維持されている配列を触るということであり、いっぽうシャボン玉を触るということは、ダイナミックに変化し続ける配列に触るということだ。配列の安定性ということでいうと、ゴム風船>スーパーバルーン>シャボン玉、というところだろうか。
シャボン玉のように、分子配列がダイナミックに変わってしまうものを触るにはどうすればよいか。別の班では、滴そのものに触れるのではなく、滴の形成される過程をモデル化して、それをザルや竹ひごで表現して、触るモデルを作っていた。そういうアプローチも試してみればよかった。
Oさんが終了間際に別の問いを出された。「波を感じる、というのが難しいんですよ。水位が上がったり下がったりするのはわかるんだけど、それが波になってる、というのを感じるのが難しい。今度はそれがやりたいな」。Oさんの問いはおもしろい。
家に帰って風呂の中でちゃぷちゃぷやりながら、腕の触覚で波を感じる方法を考える。
20090418
かえるさんソロ@でこ姉妹舎
でこ姉妹舎でソロ。事前に西新町錦会商店街をうろうろ。一曲作る。
五条通から入ってちょっと歩いてから嵐電を渡る。未だにギターをたくさん間違える。練習あるのみ。晩餐をでこ姉妹舎でいただき帰宅。
20090417
城さんと竜王の二つの高齢者施設へ。ただお話を聞く、というだけで、あまりに豊かなことが起こりすぎている。
この地域の土地改良の話に及んだときに、みなさんの手がばたばたと動き始めて、田畑の境界を表し始める。ああ、これを撮っておけばなあ。もちろん、初めて訪問させていただいた先でいきなりビデオを回すわけにもいかないので、ただただすごいすごいと思いながら、目に焼き付けるのみ。
日々のミクロな時間のできごとの中に、その土地で長く暮らしてきたことが折りたたまれて、身体はその積み重ねの中で楽々と動き、暮らしぶりの長さを一息に表す。この、贅沢なレイヤーケーキのような動きを、どうすればレイヤーケーキとして伝えることができるだろう。
20090416
ゼミ講義ゼミ、そして夕方から科研の初顔合わせ。デイケア、グループホームでの会話、ジェスチャー分析のプロジェクト。気長に考えれば、いろいろできそうな予感。三年の科研がどうなるか、これから楽しみ。
ワルキューレ@新国立劇場/第二幕
舞台はテレビや映画ではない。巨人国と小人国とを表したり、巨人の小人国における化身を表すとき、テレビや映画なら、同じ人物の大きさを変えて撮影し、合成すればよい。しかし舞台で、異なるスケールの国を表すにはどうすればよいか。
人物を変えることができないならば、環境の大きさを変えればよい。
というわけで、今回のワルキューレの演出は、さながらマリオ64の「ちびでかアイランド」だった。舞台の細部が、いちいち、神の世界と人間界とのスケールの違いに関わるのである。
冒頭、ヴォータンが舞台に入ってきて、赤い槍の穂先を次々に地面に突き刺していくと、その先で地面は緑の春に変わる。先ほどまでジークムントとジークリンデによって劇的なやりとりをしていた剣のことも春のことも、このヴォータンにとっては児戯であることがほのめかされる。
そこにブリュンヒルデが尋常ならぬ声を出して入場してくるのだが、乗っているのは玩具の木馬。白いマントを羽織った宝塚を思わせる衣装との取り合わせも珍妙で、客席からは笑いも聞こえる。ブリュンヒルデはフリッカの登場を告げるのだが、歌詞の運びは、娘が恐妻家の父親を戯れに怖れさせているかのようだ。そして、ブリュンヒルデが玩具の木馬にまたがるこの演出では、このやりとりがいっそうコミカルになる。
左手にある神の座らしきものの上には段ボール箱が雑然と並び、その上には映写機だの計画書だのが措かれている。座は鋭角的な三角で構成された不規則な形で、黒い背景に星座が描かれている。さながら地面でくだけた星空といったところ(この神の座の意匠はあとの演出に効いてくる)。
ヴォータンとフリッカとの問答は、自由意志の問題を巡る。ヴォータンは、ジークムントのことを神の手を離れ神の予測を超える自由な存在と見るのだが、フリッカからすれば、所詮神の手の上で踊る存在である。
ブーレーズはバイロイトでこんな曲を指揮をしたのか。この問答、あたかも、ブーレーズの「管理された偶然」を地でいくようなのである。
ヴォータン:ジークムントはこの剣をみずから、危機のなかで得たのだ。/フリッカ:あなたが彼に、危機を作ってやったのです、あの羨むべき剣と同様に。(オペラ対訳ライブラリー/ワーグナー ニーベルングの指環(上)/高辻知義訳/音楽之友社)
20090415
WはワルキューレのW
学生の頃、ワーグナーを熱く語る人たちの物言いがたいそうで、さらには切れ切れに聞くオーケストラ曲の響きがまたたいそうで、なんとなく敬遠していた。その惰性で、著名なオペラの数々もまるで聞かずにいた。
が、もういい大人になると、音楽がたいそうなくらいで歌を拒むこともなくなった。それに最近、いくつかのオペラをDVDで見ていると、やはりカメラの目を借りてみている気がして、一度、舞台を自分で見て、思うままに注意をあちこちさせたいと思うようになってきた。考えてみれば、生でオペラを観たことがないのである。
そんなわけで、新国立劇場の「ワルキューレ」を見に行った。いささか高くついたが、高いだけのことはあった。正直なところ、ワーグナーをこれほど楽しめるとは思っていなかった。何よりも、リアルタイムの字幕付きで見ると、オペラの歌詞の機微がかくもわかりやすくなるのかと、目から鱗が落ちるようだった(行くまでは、字幕があるとも知らず、さすがに白紙で見たのでは何もわからないと思い、ウィキペディアのあらすじを見て予習していったのである)。
というわけで、考えたことを忘れないうちにいくつかメモ。とはいえ、ワルキューレの騎行というのをてっきり男の兵士だと思いこんでいた人間が書く感想だから、言わずもがなをくだくだしくするのは我慢いただきたい。
Wの悲劇
第一幕を見るうちに、これは命名の劇なのだということが次第にわかり、そこが非常におもしろかった。ウィキペディアには「戦いに傷つき嵐の中を逃れてきたジークムントは館にたどり着く。フンディングの妻ジークリンデはジークムントに水を与え、二人は強く引かれ合う。」とあるが、あらすじとしては間違いではないものの、実際にはそういう物語ではなかった(この点、新国立劇場のステージノートのあらすじはうまく配慮されていた)。
物語は、名告ることのできない男が、とある家に逃げ込むことから始まる。家には、やはり名告ることのできない女がいる。「この家、この妻はフンディングのものです」と、女は主人の名を告げるものの、自身は名告りはしない。
帰ってきた家の主人に名を聞かれて男は、「フリートムント(平和)と呼べるでもない/フローヴァルト(愉快)であればよかったが/ヴェーヴァルト(悲哀)と名告るほかない私です」と言う。「名告るほかない」は「muss, ich mich, nennen」と、単語を区切っていかにも重々しく歌われるのだから、その名は不本意ながら名告らされているのであり、男には不本意でない名前があると知れる。
この件、初めて聞くと、名前に次ぐ名前ではぐらかされたようで、続けて唱えられるヴォルフ Wolfe という父親の名前も、この世 Welt という響きに帳尻を合わせたまでの、かりそめの名前であるかのように響く。(「ヴォルフというのが父親で、双子の一人に生まれたこの世」 Wolfe, der war main Vater; zu zwei kam ich zur Welt)
ぼくはドイツ語音韻の持つ機微には通じていないのだけれど、どうもこれらかりそめの名前には、ヴェーヴェーヴァーヴァーと唇を噛むWの音が耳につく。その音の濁りによって、人間界にいながら異人にさせられているかのようだ。ヴェーヴァルトとWを二つ重ねるその名前は、さしずめWの悲劇というところだろうか。戦さ好き Wehrlich と森 Waldの暗さを隠し持つような響きだ。
引き合いに出される二つの名前がFで始まるところも、Wを強調する作為なのだろう。FはWと同じく唇を噛む音でありながら、無声であることによって濁りを免れ、Wの重さから自由になる。フリートムント/フローヴァルト/ヴェーヴァルトという名前の列なりは、無声のFに有声のWが忍び込んでいく過程に聞こえる。
Wの因縁、Wの解放
そしてこの、ヴェーヴェーヴァーヴァーの連続は、父の実の名前であるヴェルゼWälse、そしてその一族ヴェルズンクWälsungにまで及んでいる。そして父とは、じつは大神 Wotan と来ている。Wの音は、大神の世とこの世を結ぶ父性の音であり、一族の由来をたどる鍵なのかもしれない。
テキストを見てみると、Wのくびきは、名前以外にも及んでいることが判る。やがて女と男のもとから冬が去り、春が訪れるのだが、歌の音を見ると、それは、WからLへの移行なのだ。「は、誰が出て行ったの? 誰が入ってきたの?」という女の思いがけないことば(この部分の急ぎ方は、それまでの鈍重な歩みに馴れた意識を完全に振り切るようですばらしかった)のあと、世界はWでおおわれた季節 Wintersから、Lのあふれる春 Lenz へと変化する。このWとLの対比は、「冬の嵐は去り」の冒頭にはっきりと現れる。
Winterstürme wichen
dem Wonnemond,
in mildem Lichte leuchtet der Lenz;
auf linden Lüften leicht und lieblich,
Wunder webend er sich wiegt;
Wの因縁はさらに続く。男が自分の父親の名を「ヴェルゼ」だと明かすと、女は「ヴェルゼが父君なら、あなたはヴェルズンク族ね? 幹に刺さった剣はあなたのもの。ならばあなたをこう名付けさせて下さい、愛しているのだから」と言って、ここで初めて相手を「ジークムント」と呼ぶ。「ジークムント、あなたをそう呼ぶわ」。このように、ジークムントという名前は、男によって自称される前に、女によって命名されている。
この「ジークムント」の命名のあと、立て続けに名付けが行われる。
ジークムントは剣を命名する。「ノートゥング!ノートゥング!そう名付けよう、剣よ」
そして剣を引き抜き「ジークムント、ヴェルスンクの一族、ここにあり! 花嫁に贈るため、汝、剣をここに取る」
すると、女は、ジークムントと自分を関係づけることで自身を命名する。「ここにいるあなたがジークムントならば、わたしはジークリンデ、あなたの望んでいた者」。
ジークムント、ジークリンデ、ノートゥングという一連の命名は、男と女が過去の名前からWを一掃し、名をWから解放する過程のように聞こえる。
三つの名前からWの音は周到に消されている。しかし、Wは外在化されたものの、なくなったわけではない。彼らの名前はヴェルズンクという族の名前とともに呼ばれることで、Wとのあいだに新たな、危うい契りを得ている。
演出について
第一幕のセットは巨大な机と椅子でできており、机には赤い矢印が突き刺さっている。椅子は階段を使わねば上れぬほどで、広すぎる机は固いベッドのようによそよそしい。登場人物たちが巨人の世界に送り込まれてしまった存在であることがほのめかされている。おそらく、スケールの狂わされているこの世界を生みだした力と、男が名告れない理由とのあいだには、何か関係があるのだろう、という感じが伝わってくる。後半、この机は崩壊し、ジークムントとジークリンデの逃避行は、この世界から文字通り「降りる」ことで幕となる。力の主は明かされぬままだ。
天から降る矢印は赤、地上から生える矢印は緑、という補色関係もおもしろかった。じっと見つめて目を閉じると、赤と緑が逆転するのである。なるほど、春を産む技法とは瞳を閉じることなのか。そして、同じ技法によって、春は血族の呪いへと裏返る。
20090414
朝から講義に会議。まずまず体は大丈夫の模様。
20090413
空低く並び合ひたる北斗星はるけき故国を恋ひわたるかも
細川周平「遠きにありてつくるもの」では、移民の人々が作るさまざまな短詩に、思いは探られるのだが、とりわけ、こちらの心にぐっと来たのがこの一首。
おそらく、何の背景も知らされずにどこかの歌集に入っていたら、通り過ぎてしまった歌かもしれない。が、これが岩波菊治という信濃出身の日系ブラジル人第一世代の手になるものだと知ると、とたんにゆかしくなってくる。
北斗七星は、おそらく日本と真反対のブラジルでは、北空を低く這って消えていく星座なのだろう。その同じ星座が、故国では北極星の回りを大きくわたっていく。ブラジルで託された思いが日本の空で思いがけない大きさになって「恋ひわたる」。歌の中で、ひとつの弧はもう一つの弧へと受け渡されて、円となる。しかし、この場所からは、それは円としてではなく弧としてしか見えない。だから思いがあふれてしまう。
そんな話のあとではあるが
午前中、大学のトイレできばっているうちに尻がえらいことになり、倒れてしまう。あまりに苦しいので携帯で控室に電話。棚瀬さんが病院まで送ってくれる。時間外でなかなか見てもらえないところを、棚瀬さんが必死に頼んでくれて、なんとか急患扱いにしていただく。
診察台で尻を出すと、「あー、これはもう、粘土みたいなんがカッチカチにつまっとるわ」というわけで、下剤投入。すぐに効果は現れ、トイレにかけこみ事を済ませると、申し訳ないほどすっきりした。すっきりし過ぎて、急患で来たことが恥ずかしくなるほどであった。つまりこれは、ただの痔+便秘+貧血だったのではないか。トイレから戻り、お医者さんに「心苦しいですがすっきりしました」と言ったら「心苦しいですか」と笑われた。わたしが医者なら、「便秘でおれの昼休みをつぶしやがって!」と怒鳴るところである。
あまりの我が身のふがいなさに午後は寝てしまう。
20090412
サカナクションのキーボード
いいなあ。フレーズが作り込まれることでこれだけリズムが切り立つとは。古いたとえだけど、ジェフ・ローバー・フュージョンがデビューした頃のことを思い出した。
細川周平「遠きにありてつくるもの」
細川さんの本は、郷愁や情けという、ともすると後ろ向きに評価されがちな感情と正面からつきあったものだ。
フーゴーの「故郷を甘美に思う者はまだ嘴の黄色い未熟者である。あらゆる場所を故郷と感じられる者は、すでにかなりの力をたくわえた者である。だが、全世界を異郷と思う者こそ、完璧な人間である。」というアフォリズムに違和感を感じ、サンパウロの老一世の「自分は故郷が懐かしくてしょうがないが、日本もブラジルも異郷のようなものだ、一体未熟なのか完璧なのか」ということばをむしろ、よりどころとする。
「郷愁」ということばを、嘴の黄色い者の発する鳴き声と切り捨ててしまうと、そのことばの持つ可能性に分け入ることができない。どんな感情であれ、その感情から離れることのできない人間がいて、それはたいていの場合、人がそもそも持っている性質に根ざしており、それは考えるに足る。
故郷が懐かしい、という思いがあふれてしかたがない。そのような感情を、人の営みとしてどうやって掬い取るか。ともすれば思想から切り離されてしまうこのような感情の問題について、細川さんの記述は、注意深く経巡っていく。
で、その受賞パーティー
日曜日、ギターを抱えて六曜社に。オクノさんに「ライブですか?」と問われて、「いえちょっと・・・」と口ごもる。細川周平さんの「遠きにありてつくるもの」読売文学賞受賞記念パーティーに。ミュージシャンが次々と現れ、ほとんどライブのよう。細川さんもジョビンを何曲か弾いていた。ミキサーがニシジマアツシくんで驚いた。
わたしも僭越ながら、かえる目の「浜辺に」を。中村善郎さんが弾いたあとにボサノヴァを歌うというのも厚顔だが、そこはそれ、日本語で誤解されたサウダージということで。幸い、暖かい拍手をいただいた。
20090411
辰巳ヨシヒロ『劇画漂流』
昨年出た辰巳ヨシヒロの自伝的劇画。巻措く能わざるの感。
派手ではないコマ割りだが、ナレーションの入り方がつつましく、するすると読めてしまう。よく見ると、ナレーションが入る前に、ちょっとした捨てコマというか、無言の動作のコマがしばしば入っている。この無言のコマのおかげで、「ん?どういうことかな?」というスキが読者の側に生まれて、そこにナレーションがすい、と入ってくる。内容は、兄弟の相克、出版社との泥臭い駆け引き、と、なかなかにえげつないのだが、語り口がスムーズで、つい次から次へと読まされてしまう。
淡々としたコマ割り、緩急の動作の次に現れるナレーション、というスタイルは、じつは90年代に次々と現れだしたアメリカ、カナダの北方抒情派(と、ぼくは勝手に名付けているのだが)のコミックと相通じるところがある。エイドリアン・トミーネの肝いりでD&Qに連載されたというのもうなずける。アメコミ作家たちは、日本のマンガにすでに自分たちのスタイルが先取りされているのを見出して驚いたのだろう。そして本書では、その手法が、遠い昔、1950年代に、アメコミへの批評的検討から編み出されたことが書かれている。
「たとえばアメリカンコミックスでは激しい動きのあるコマに長々とセリフが書き込まれていた/これだと長いふきだし(セリフ)を読んでいる時間だけ動きのある絵が停止していることになる/動きのあるコマはセリフをなくしてすぐに次のコマに目を移すように工夫する/動きのあるコマは極端に背景を省略して見る時間を短縮させるのだ/人物のアップは表情から心理状態を読みながらすぐに次のコマに移行する/大きく描かれたコマは背景の隅から隅まで目を通すその時間だけこのコマの絵は停止する/一こまに描かれた絵やふきだしの代償によって読者の目がそのコマに留まる時間を計算できるのだ/これが『コマと時間のシンクロ』」(劇画漂流 下巻 p198)
本筋からは離れるが、読んでいておもしろかったのが、3Dマンガを描くところ。主人公は、当時流行の立体アメリカンコミックスを読んで、「立体まんがのしかけ」を察し、付録の赤青メガネをかけながら自己流の3Dマンガを描いてしまうのである(上巻p210)。
20090410
幻燈の種板
彦根のとある旧家におじゃまし、幻燈の種板を見せていただく。渋谷さんのご紹介。院生の御子柴さんも一緒に。
 日清戦争後のものと見え、李鴻章の名前や戦場の名前の入った種板がある。他にも地口やポンチ絵の種板も。木製のスライドホルダーもあり、車ははずれていたが「花輪車」の枠もあった。往時が偲ばれるコレクション。これはぜひ大写しにしてみたい。さっそく幻燈会の相談をさせていただく。
日清戦争後のものと見え、李鴻章の名前や戦場の名前の入った種板がある。他にも地口やポンチ絵の種板も。木製のスライドホルダーもあり、車ははずれていたが「花輪車」の枠もあった。往時が偲ばれるコレクション。これはぜひ大写しにしてみたい。さっそく幻燈会の相談をさせていただく。
覗きからくり

明治期の覗きからくりも拝見する。豊田美術館のカタログのものとほぼ同じ外観だが、「池田屋製」の銘はない。蒔絵のほどこされた瀟洒なつくりで、写真は数十枚が仕込まれている。
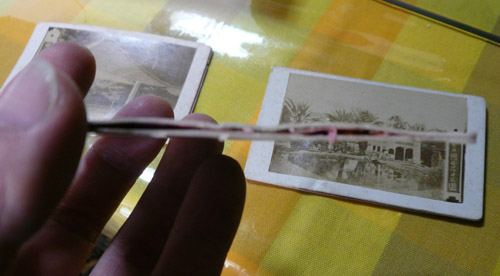 はずされた写真をひとつを手に取ると、それは二枚の写真を背中合わせに貼ったもので、合わせ目が少し開いている。剥がれかけているのかと思ったが、中のからくりを見てその理由がわかった。
はずされた写真をひとつを手に取ると、それは二枚の写真を背中合わせに貼ったもので、合わせ目が少し開いている。剥がれかけているのかと思ったが、中のからくりを見てその理由がわかった。

内部には100枚近くの写真を収めるための布製ベルトが収められている。ベルトには、細い木板が写真の枚数だけずらりと貼り付けてある。木板には二本の針金が突き出ている。この針金に、田楽よろしく写真を突き刺すのである。田楽写真はベルトの上に規則正しく並んで、二つの軸の回りをぐるぐると回る。内部には鈴が仕込んであり、軸に連動した車から突き出た釘が、この鈴を叩く。一枚が眼鏡の正面に送られるたびにチンと鳴る。なんとも愛らしい作りだ。
写真が両面にあるので、眼鏡の方も両面に据えられている。各写真を見たところ、片面は関東、片面は関西というものがほとんど。さながら東西眼鏡合戦である。からくりの両側に人が立ち、東西から眺めている、という図は、なかなか乙なものだ。それぞれの人が、違う写真の登場に声をあげる。お互いが何を見ているのかはわからない。ちょっと皇帝パノラマ館に似ている。
たまに芸者の写真や風俗画が挟まれている。ちょっといっぷく、というところだろうか。
こうしたからくりは、いったん博物館に収められてしまうと、学芸員でもない限り、触らせてもらうことすらできない。こうやって内部のからくりを逐一拝見できるのはありがたい限り。
天気のいい日だった。昼は大学の桜を眺めながらゆうこさんと昼飯。桜の下では、桜は一二本あれば十分である。
20090409
朝からゼミゼミ講義。ああこの季節が始まったなあ、という感じ。科研費の書類や相談。いろいろ忙しい。
20090408
大学院の講義で教室に行ってみると、学生は一人しかいなかった。北向きの教室ではうすら寒いので、吹き抜けに移動して、テーブルで卒論の内容を見せてもらい、ディスカッションをする。
空中脱臼
先月末から暇があるとオペラDVDを見ている。遅々として進まないが、四月に入って見たのは「アイーダ」「フィデリオ」「魔弾の射手」の三本。
このうち、とくにベルクハウス演出アーノンクール指揮の「魔弾の射手」にはいろいろ感じ入るところがあった。斜面を利用した、養老天命反転地のような幾何学舞台。色彩を絞った意匠(アデーテだけが黄色の服、あとはみんな白黒)。影のように通り過ぎる人。演奏に割り入る物音。
おそらくCDで聞いたなら、なぜこの場面で物音がするのか?という疑問があちこちで起こるだろう。それくらい、歌詞と動作音が容易に結びつかない演出になっている。「オペラの初めはあくまで音楽+演劇であったのだが、その歴史の中で音楽が演劇を呑み込んでしまったのだ」とは「クラシックかわらばん」の片山杜秀さんのことばだが、ベルクハウス演出の「魔弾の射手」の舞台は、物音をさせることによって、むしろオペラ音楽で構築された世界を攪乱しているかのようである。
アーノンクール指揮の演奏には、長音の中に切り立つような宙づり感が感じられる。幻のアーフタクトで人々の足どりが中断するように。
20090407
科研費の憂愁
科研費採択内定の通知が来る。
じつは自ら代表として科研費をとったのは初めてである。
生来金勘定が苦手なこともあって、できるだけ金のかかる研究は避けてきた。自分一人でなら、パソコン一台とビデオカメラとHDレコーダーがあれば、基本的な研究はできるし、それでよいとも思ってきた。
が、何人かでプロジェクトを組み、フィールドに取り組むとなると、そうも言ってられなくなってくる。機材を確保し、旅費を出し、研究会を開き、報告書を作らねばならない。通ったものの、なんとなく憂うつである。この不景気に何を贅沢な、と思われるかもしれないが、人様の金を使うには体力がいるものだ。
まあ、そういう時期がやってきた、ということなのだろう。
さかしま
渋谷さん宅におじゃまして、先日のカメラ・オブスキュラの写真を見せていただく。

長時間露光した堂内に映る景色。桜の下にさかさの城、空の青。

この日のために白いスーツで登場した上田くんが、玄関前でおどける姿。
20090406
「交換するオペラ」@クラシックかわらばん
「交換されるオペラ オペラ絵はがきの時代」というタイトルで、web上の連載を始めました。
クラシックの音盤やオペラのDVDを多数発売しているクリエイティヴ・コアさんの企画です。手元の絵はがきを肴にオペラについて語るというのを、これから何度かに分けて書き下ろします。まずは第一回をどうぞ。
クラシックかわらばん
http://www.classic-kawaraban.com/
交換されるオペラ オペラ絵はがきの時代
http://www.classic-kawaraban.com/column_hosoma/
20090405
カメラオブスキュラ@スミス記念堂
よく晴れた。カメラオブスキュラは天候に恵まれている。
お堀端の桜は三分咲きというところ。うっすらと桜色が、白い幕に映り込む。
今回は、渋谷博さんが写真機を持って来られて、堂内で長時間露光を試して下さった。肉眼ではうっすらとしか感知しえない、堂内に映し出された光景が次々と明らかになる。
カメラオブスキュラは何度見ても見飽きない。室内に居ながら外に閉じ込められるという感覚は、何度体験しても、そのつど、この身体の構えを新しくさせる。
後半は上田洋平くんによる八坂町の絵説き。八坂町での聞き取りをもとに、琵琶湖岸のさまざまな生活場面が精緻な絵に書き起こされている。その場面を指しながら、じっさいに聞き取りを行った上田君が話していく。
上田君は、単に話を聞くだけでなく、地元の方々の話に埋め込まれている語の言い回し、イントネーションを体得して、それを再現することで、語りの中に当事者のことばを蘇らせる。ゆっくりとした口調ではあるが、複数の人の声がその語りから聞こえてくる。
20090404
信楽へ。shiroiro-ieにてソロライブ。二階の吹き抜けをはさんで客席とは反対側で歌う。下を見ると1Fのギャラリーが見え、正面を向くと1m向こうにお客さん。非常に不思議なシチュエーション。
まだ、ソロで歌うときは、なかなか緊張が取れず、あれこれ間違えて止まったり歌の細部が至らなかったりする。せめて止まらずに歌えるようになりたいものだが。
20090403
沼 424: joy

この放送をダウンロードする
未来への呪文
Judy & Maryを初めて聞いた場所はなぜかよく覚えている。
たしかアパートの近くの焼肉屋で定食を食っていたときに有線で流れていて、これはただならぬ歌詞だと思い、誰の曲なのかずいぶん捜した。聞き覚えたことばから、てっきりそれは「小さな呪文」というタイトルなのだろうと思っていたのだが、探し当ててみると「小さな頃から」だった。
「小さな頃から」には「じゅもん」ということばが出てくるんだけど、その呪文が何かは歌われない。
YUKIが「joy」で「呪文」ということばを思いついたとき、自分が十年前に作った「小さな頃から」という歌を思い出さずにはいられなかっただろうと思う。
「小さな頃から」の中で唱えられていた「じゅもん」とは何か。おそらく、彼女は、「じゅもん」の中身を歌わないことで、この問いをずっと温めることになったのだろう。
その呪文は「joy」ということばになる。十年前の彼女は、そんなことばになるとはおそらく予想していなかっただろう。でも十年前の彼女が問わなければ、そんなことばは生まれなかった。だからそれは十年前の自分に贈ることばであり、十年前の自分から贈られたことばでもある。
それはおそらく、生まれ来た者に贈ることばであり、生まれ来た者から贈られたことばでもある。そしていまも、その呪文を歌うのだとしたら。
「joy」の一節に「運命は必然じゃなく偶然で出来てる」というフレーズがある。これは飴屋さんに言われて気づいたのだけれど、YUKIはある時期からライブで、「運命は必然という偶然で出来てる」と歌っている。
20090402
ELANで本格的に手元のデータを起こす。みるみる時間が経つ。
沼 423: スピーカーと物音、いまここではない音:『転校生』を観て(2)
 東京芸術劇場「転校生」を観て。その2。
東京芸術劇場「転校生」を観て。その2。
この放送をダウンロードする
20090401
新学期の開始。本年度から教授となった。いろいろ忙しくなりそう。
沼 422: カウントダウンとレイヤーの合成:『転校生』を観て(1)
 東京芸術劇場「転校生」を観て。その2。
東京芸術劇場「転校生」を観て。その2。
この放送をダウンロードする
to the Beach
contents









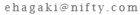
 日清戦争後のものと見え、李鴻章の名前や戦場の名前の入った種板がある。他にも地口やポンチ絵の種板も。木製のスライドホルダーもあり、車ははずれていたが「花輪車」の枠もあった。往時が偲ばれるコレクション。これはぜひ大写しにしてみたい。さっそく幻燈会の相談をさせていただく。
日清戦争後のものと見え、李鴻章の名前や戦場の名前の入った種板がある。他にも地口やポンチ絵の種板も。木製のスライドホルダーもあり、車ははずれていたが「花輪車」の枠もあった。往時が偲ばれるコレクション。これはぜひ大写しにしてみたい。さっそく幻燈会の相談をさせていただく。
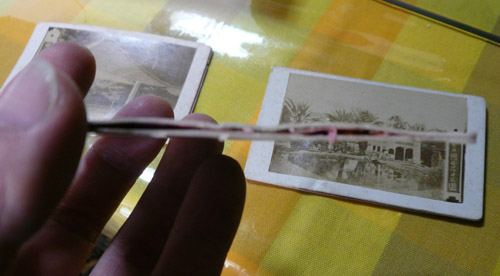 はずされた写真をひとつを手に取ると、それは二枚の写真を背中合わせに貼ったもので、合わせ目が少し開いている。剥がれかけているのかと思ったが、中のからくりを見てその理由がわかった。
はずされた写真をひとつを手に取ると、それは二枚の写真を背中合わせに貼ったもので、合わせ目が少し開いている。剥がれかけているのかと思ったが、中のからくりを見てその理由がわかった。


