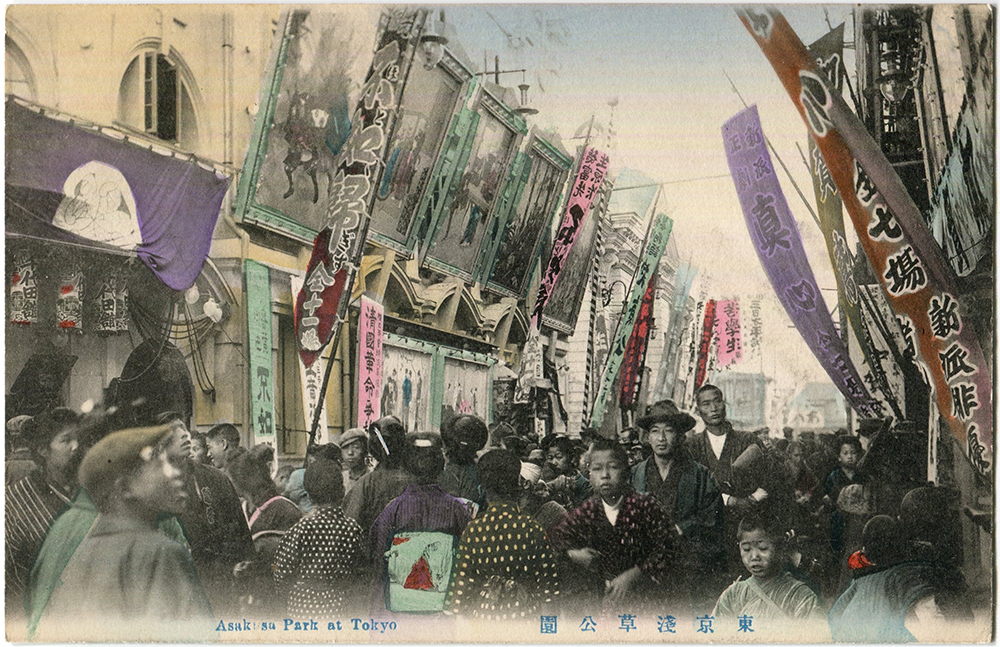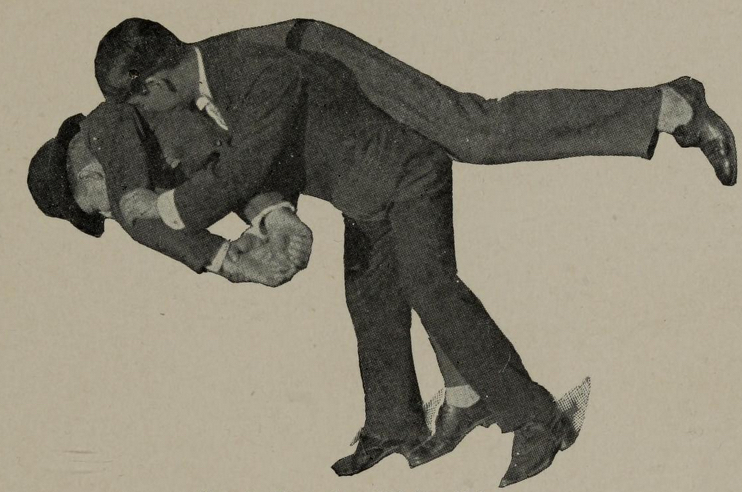勤務先が自転車で15分の場所にあるおかげで、朝の連続テレビ小説を見て出勤するのが長年の習慣になっている。気の合う作品と出会えると、朝の仕事にもその作品に合った調子が出て、半年間がその作品の緩急にうっすら染まる一方、一、二ヶ月で見落とすようになってしまうこともあり、そんな場合は、ドラマもそこそこに出勤してしまう。これまで、最後まで見続けたものは『オードリー』『てるてる家族』『芋たこなんきん』『ちりとてちん』と大阪放送局制作のものが多い。
『カーネーション』を、3/31まで楽しみに見続けた。『カーネーション』を見ていると、作者や演出家、スタッフが、朝の生活をいかに丁寧に描いているかがよくわかった。早い朝、眠い朝、ミシンを踏みながら迎えてしまう朝、朝帰りの朝、子どもを蒲団から追い出す朝の光が描かれ、時代ごとにかわる衣装や家のつくり、調度に配慮が行き届き、物語の朝が、見ているこちらの朝に染みてくる。
尾野真千子演じる糸子が、年齢を重ねたある朝、「おはようございます」と、冒頭のナレーションで挨拶をした。あたかも視聴者に朝の近況報告をするように、あれだけ苦手だった早起きもできるようになるから年はとってみるもんです、と言う。時代がいつかを説明するかわりに、朝のあり方が変わったことを親密に告げ、時代の移り変わりを言い当てる。朝にこの物語を見る視聴者のことが、作者にはよく見えているのだなと思った。
一方で、この物語の一筋縄ではいかない展開には、朝からぎょっとさせられることもあった。
尾野真千子から夏木マリへと役者が交代した三月のある土曜の朝、ほっしゃん。演じる北村を相手に、糸子がだんじりを見る窓の張り出しにもたれ、しみじみと来し方行く末を語る場面。それは同じ日の、千代が一階に集った人びとの合間に善作を見出す場面と並んで、物語のクライマックスだったといってよい。ところが、そのしみじみとしたやりとりを経て、尾野真千子演じる糸子が大写しになった直後に、突然、老いた糸子が蒲団の中で目覚めるところが天井から捉えられる。「おはようございます。年をとりました。」まるで、五ヶ月突き合ってきたこの作品が全部夏木マリの見ていた夢と化したようで、尾野真千子の演じ続けてきた糸子があわれに思えたのを覚えている。
夏木マリのゆっくりとした平坦なナレーションは、当初、阪神で生まれ育ったわたしには違和感のあるものだった。が、それくらいのことで見続けるのをあきらめるには、この物語の続きはあまりにも楽しみだった。それまで好きだったキャラクタはみな写真に収まってしまい、映像はプラスチックな風合いになり、若い孫娘がなじまないサンダルとヤンキー風の服に身を固めてここまでの物語を踏みしだくように登場し、ドラマが保ってきた肌理はすっかり失われてしまったが、この肌理のなさは、いかにも1980年代の肌理のなさであった。そしてこの、さびしさを受け止める肌理すら失われたさびしさの感触は、だんじりの日に北村が糸子に予言するように告げた、どうせいっこずつ消えていく、おまえここにいちゃったら一人でそれに耐えていかないかんねん、しんどいどー、ということばを言い当てているようでもあった。リンリンではなくトゥルルルと鳴る電話、あほぼんたちが差し出すつるつるのワープロの企画書など、細かい演出や小道具にも、時代の肌理の変遷がよく写されていた。暴走族の襲撃で店のガラスが割られ、孫のなけなしのクリスマスケーキがつぶれてしまい、そのつぶれたケーキを夏木マリ演じる糸子が噛みしめる場面を見るにいたって、この肌理のなさは確信犯だなと得心して、新しい糸子による朝の15分を見続けた。
夏木マリ演じる糸子になじみ始めたのは、やはり朝の描写がきっかけだった。階段から落ちて介護ベッドで生活せねばならなくなった糸子は、孫娘とベッドの上でテレビを見るようになり、朝にやっている連続テレビ小説に気づく。それまでの糸子はこの時間にはもうテレビを見る間もなく忙しく働いていたのだな、と改めて思わされる。そのとき、糸子の見るテレビから流れ出した『いちばん太鼓』の音楽は、それを見たことのない人にも、「朝ドラ」と呼ばれる前の「朝の連続テレビ小説」の気分、「主題歌」ではなく「テーマ音楽」で始まり、15分するとニュースへと席を譲る朝の物語の気分を伝えるもので、鳩子の海だとか、マー姉ちゃんだとか、おしんだとか、ふたりっ子だとか、そういう朝のひとつを思い起こさせるようなメロディだった。かつての連続テレビ小説を見る主人公の朝と、それを見ているこちらの朝とが重なるようにも思われ、そこまで少し快活過ぎるほどに見えた夏木マリの声や演技にも、落ち着きや親しみを感じるようになってきた。
江波杏子、山田スミ子、中村優子(まさか最終回に現れるとは…)の絶妙な配役や、糸子がプレタポルテを始め出してからぐっと輪郭の付きだしたあほぼんたちとのやりとり、竹内郁子、小笹将継、中山卓也らの役回りを楽しみながら迎えた三月の最終回もまた、朝に見た。 「おはようございます。死にました。」という夏木マリの人を食ったナレーション。そうだった。『カーネーション』のナレーションは「うち」という主語を要所でうまく略して、前置きなしに近況を単刀直入に告げるのだった。それにしても、死んでもまだ語るのか。
これまで、この物語のナレーションには、第三者の視点を排した、あくまで糸子の意識に沿ったことばがあてられていた。糸子に見えないものは、ナレーションからも語られない。糸子が遅れて気づいたことに、ナレーションも遅れて気づく。ナレーションはそのまま、糸子のひとりごとに漏れることもしばしばだった。尾野真千子演じる糸子の大きな魅力は、子どものようなうかつさにあり、糸子に恋心をいだく男が寄ってきても、幸運が近づいてきても、ナレーションは「なんやのん」「なんで」と、その意味にはっきりと気づくことはない。そして「気がついたら」誰かがそばにいて、何かがうまくいっている。最終回の直前の金曜日、主人公が亡くなってしまい、あの、糸子の意識にぴったり沿ったナレーションはどうなってしまうのかが、まっさきに気になった。そうしたら、死んだ糸子があっさり「死にました」と挨拶した。この声はどのような身分で、どんな意識から発せられている声なのか。
「死にました」と語る糸子のナレーションは、それまでの生身の糸子から解き放たれたように、自分の居場所を自在に移動させていく。「そば/そら」「しょうてんがい/しんさいばし」「みどり/ひかり」。韻を踏んだことばが、ともすると安い詩になるのを嫌うかのように、「しょうてんがい/しんさいばし」というアキナイのことばが差し挟まれて、わらべうたのような稚気を出している。そうした稚気は、呉服屋から始まってずっとあきないの物語の中心にあった主人公の声に似つかわしい。脚本家、渡辺あやのことばづかいは繊細だ。
ナレーションは「みどり/ひかり/みずのうえ」と続いて、韻を破る。そのことで、「緑/光」と名詞の対比に聞こえたことばが、「緑、光り、水の上」とも聞こえる。ひかりは、緑を照らす名のようでもあり、水の上に移る動きのようでもある。名と動きの間で揺れる「ひかり」は、このナレーションが生身を離れたことによって得た、新しい装いであるかのように響く。 みずのうえにそらが映っている。そのみずのうえのそらから離れた声は、「なんぞおもろいもんをさがしにいく」。おもろい、ということばは、たくらみを思いついた善作が幼い糸子ににやりと笑ってささやく呪文、糸子自身が新しいたくらみを思いつくたびに繰り返してきた呪文だ。
自動ドアがあき、なにものかが通ったかのように玄関の植木が揺れる。カメラは視聴者を病院の一室へと誘い、そこから車椅子の女性があらわる。女性の顔はよく見えない。病院の待合室へと押されていくその女性が誰なのか、もはやナレーションは黙して語らない。が、長らくこのドラマを見続けてきたものなら、ここでこのような形でひとり現れるのは、奈津しかいないと直感できる。この物語ではずっと、見る者の感覚が信頼されてきた。最後もやはりそうなのだろう。
その奈津が、待合室のテレビで『カーネーション』の第一回が始まるのを見ている。奈津の見る姿に半年前のわたしを重ねていると、カメラは次第にテレビの画面を大写しにしていく。「8:01」の文字が左上に見える。いまわたしの見ているテレビの画面には、「8:12」の文字が見えている。二つの朝の時刻が近づきながら、物語の中の90年間とこの半年間とを、二つながらきゅうと圧縮していく。やがて画面は一つになり「二人の糸子の歌」が流れる。10月、この歌の場面のもつ遊び心に、きっといい半年になるなという予感を持ったことを思い出す。その半年前に、年老いた奈津が配されている。さきほどまであちこちしていた声の主も、いまはその「そば」にいるのだろう。
半年前、わたしのまだ知らない物語の始まりを、わたしは見ていた。その物語の終わりに、物語を終えようとする彼女たちがその始まりを見ている。これはただの入れ子でもループでもない。半年間という長い時間の感覚を、人の生というさらに長い時間に重ね、その重なりを記憶の時間として花束のように差し出す、愛らしい物語の閉じ方だ。これから先、幾度か思い出すことになるだろうこの物語の始まりは、ただの始まりではなく、奈津の見る物語の始まり、奈津の覚えている糸子の物語の始まりとなるだろう。
朝といえば、ほっしゃん。演じる北村が、小原家の畳の間で迎える朝の場面は、これまでの連続テレビ小説では見たことのない朝だった。
前日、小原家で洋装店の見学をした北村は、そのまま夕食の歓待を受ける。男家族に育ったという北村は、糸子の母千代の柔らかい物腰にすっかり参ってしまい、「おかあさん、仏さんでっか」と酔いながら絶賛するうちに、寝入ってしまった。
朝、食事の支度の音とともに、おっちゃん寝てるよってな、おこさんようにな、と糸子の柔らかい声がする。畳の上を駆ける子どもの丸い物音が近づいてくる。その末娘の聡子の足が、北村の目の前を通り過ぎて、表の新聞を取りにいく。からりと扉が開いて、朝の淡いひかりが北村にかかる。北村は薄目を開けて、しかし体を起こすことなく、おこされなかったおっちゃんの振りをしている。糸子の気遣いを裏切ることなく、幼い足取りを裏切ることもなく、聡子の招き入れた朝のひかりを浴びながら眠っているふりをすることで、北村は小原家にとって、特別な存在になる。おそらく、この場面のほっしゃん。の表情で彼のファンになってしまった人は全国で一千万人いるのではないか(わたしもその一人だ)。
その後、北村が、長じた聡子に喫茶でケーキやパフェを譲る「茶番」を繰り返すたびに、ああこれは、あの朝からずっと続く聡子との契約なのだな、と、北村のしあわせをお裾分けしてもらうような気がして、すがすがしくなった。『カーネション』のある朝は、そういう朝だった。
2012.4.1. 細馬宏通
(旧ブログ「Fishing on the Beach」掲載)