かえるさんレイクサイド (38)
昼の名残りで、夕暮れは暖かかった。後ろから爆音が近づいてきた。爆音は橋を渡っているかえるさんの少し前をめがけて減速した。「よお」番長が振り向いた。「暖かいな。腹減ってないか?」そういわれると夕焼けがずんと腹にこたえるような気がした。「こういう日は、レストランにいいんだ、乗れよ」
 川沿いのカーブが暮れなずむのをぱりぱりと切り裂きながら、番長のハンドルがうねった。しばらく行くと、ぱちぱちと何かが顔に当たる。「ほら、前菜だ、口開けろ」言われるままに口を開けると、そのぱちぱちが口の中に飛び込んできた。「あだいめるらお」番長も口を開けているらしかった。
川沿いのカーブが暮れなずむのをぱりぱりと切り裂きながら、番長のハンドルがうねった。しばらく行くと、ぱちぱちと何かが顔に当たる。「ほら、前菜だ、口開けろ」言われるままに口を開けると、そのぱちぱちが口の中に飛び込んできた。「あだいめるらお」番長も口を開けているらしかった。
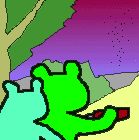 小さなぱちぱちがほほに貯まってきた。「前菜終わり」番長の声で口を閉じると、さりさりと、ほこりっぽいようないがらっぽいような音が口の中で動いた。「ヨコバイだ、まだちっちゃいから、あっさりしてるだろ。次いくぞ」番長は細いあぜを正確に走った。「よし次だ、口開けて」蚊柱に突っ込んだかと思うと、あっという間にユスリカが口に入った。羽化したてのユスリカはやわらかで、日向水の味がした。
小さなぱちぱちがほほに貯まってきた。「前菜終わり」番長の声で口を閉じると、さりさりと、ほこりっぽいようないがらっぽいような音が口の中で動いた。「ヨコバイだ、まだちっちゃいから、あっさりしてるだろ。次いくぞ」番長は細いあぜを正確に走った。「よし次だ、口開けて」蚊柱に突っ込んだかと思うと、あっという間にユスリカが口に入った。羽化したてのユスリカはやわらかで、日向水の味がした。
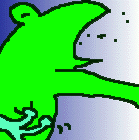 「まだまだ。あそこにしめった丸太が積んであるだろ、あれが今日のメインな」バイクは田んぼの真ん中を突っ切ると、農具小屋に近づいて、ぐるぐる回り始めた。番長はもう口を開けていた。かえるさんも口を開けてしばらく待つと、何かが飛び込んでわさわさし始めた。しばらくすると別のわさわさが加わった。「来たか?」かえるさんはうなずくかわりにぎゅっと番長の腰を握った。「ここのガガンボは甘いだろ、いい丸太食ってるから。」それはほんとうにけろっととろけるようなガガンボだった。
「まだまだ。あそこにしめった丸太が積んであるだろ、あれが今日のメインな」バイクは田んぼの真ん中を突っ切ると、農具小屋に近づいて、ぐるぐる回り始めた。番長はもう口を開けていた。かえるさんも口を開けてしばらく待つと、何かが飛び込んでわさわさし始めた。しばらくすると別のわさわさが加わった。「来たか?」かえるさんはうなずくかわりにぎゅっと番長の腰を握った。「ここのガガンボは甘いだろ、いい丸太食ってるから。」それはほんとうにけろっととろけるようなガガンボだった。
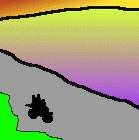 「じゃ、デザートいくか」バイクは湖岸に向かった。湿った風が顔をなで始めた。前線が近づいている。明日はきっと雨だ。もう口は開けなくていいに違いない。これが最高のデザートなのだ。番長は何もいわずに湖岸を飛ばし続けた。
「じゃ、デザートいくか」バイクは湖岸に向かった。湿った風が顔をなで始めた。前線が近づいている。明日はきっと雨だ。もう口は開けなくていいに違いない。これが最高のデザートなのだ。番長は何もいわずに湖岸を飛ばし続けた。
|