かえるさんレイクサイド (12)
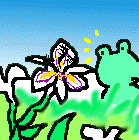 いつになく明るい月夜で、かえるさんはずいぶん遠出をしてしまい、犬上川に戻るころにはすっかり夜が明けていた。川辺を行くと、竹林の縁に沿うように朝露に濡れた白い花が群れていた。いつも見かけるありふれた花だが、徹夜明けのしょぼしょぼした目には、まぶしい色だった。花びらの中にぎざぎざしたものがあって、少しだけかえるのてのひらにも似ているような気もする。かえるさんはこの花に触ったことがなかった。
いつになく明るい月夜で、かえるさんはずいぶん遠出をしてしまい、犬上川に戻るころにはすっかり夜が明けていた。川辺を行くと、竹林の縁に沿うように朝露に濡れた白い花が群れていた。いつも見かけるありふれた花だが、徹夜明けのしょぼしょぼした目には、まぶしい色だった。花びらの中にぎざぎざしたものがあって、少しだけかえるのてのひらにも似ているような気もする。かえるさんはこの花に触ったことがなかった。
 シャガの花の上にのぼってみると、花の内側には、さっき見たぎざぎざがあった。ちょうどサギが羽を広げたような形だった。その羽の下に、かえるさんは頭を差し入れてみた。羽が頭をざわざわとなでた。頭を抜いてみると、またなでられた。入れるときとちょっと違う。入れることと抜くことは逆だが、なでられ方は逆ではない。ちょっと違う。そこで、かえるさんは逆の逆に入れて、逆の逆の逆に抜いてみた。するとやはり、逆の逆の逆のなでられ方は、逆の逆のなでられ方の逆ではなく、ちょっと違うのだった。
シャガの花の上にのぼってみると、花の内側には、さっき見たぎざぎざがあった。ちょうどサギが羽を広げたような形だった。その羽の下に、かえるさんは頭を差し入れてみた。羽が頭をざわざわとなでた。頭を抜いてみると、またなでられた。入れるときとちょっと違う。入れることと抜くことは逆だが、なでられ方は逆ではない。ちょっと違う。そこで、かえるさんは逆の逆に入れて、逆の逆の逆に抜いてみた。するとやはり、逆の逆の逆のなでられ方は、逆の逆のなでられ方の逆ではなく、ちょっと違うのだった。
 何度もちょっと違っているうちに、かえるさんの頭はなんだか乾いて突っ張ってきた。頭だけでなく、あしの付け根のあたりも少し熱っぽくなってきた。そのうち猛烈にかゆくなってきた。こんなかゆさははじめてだった。かえるさんは吸盤で頭をごしごしこすったが、かゆさは増すばかりだった。この花はもしかすると毒なのだろうか。毒をずっと頭にざわざわさせていたのだろうか。こんなにざわざわさせたかえるが、かつていただろうか。これはかえる史上初のかゆさかもしれない。もうお医者にも行けないくらいかゆくなってしまったかもしれない。このままかゆくて死んでしまうかもしれない。
何度もちょっと違っているうちに、かえるさんの頭はなんだか乾いて突っ張ってきた。頭だけでなく、あしの付け根のあたりも少し熱っぽくなってきた。そのうち猛烈にかゆくなってきた。こんなかゆさははじめてだった。かえるさんは吸盤で頭をごしごしこすったが、かゆさは増すばかりだった。この花はもしかすると毒なのだろうか。毒をずっと頭にざわざわさせていたのだろうか。こんなにざわざわさせたかえるが、かつていただろうか。これはかえる史上初のかゆさかもしれない。もうお医者にも行けないくらいかゆくなってしまったかもしれない。このままかゆくて死んでしまうかもしれない。
 気がつくと、かえるさんは、金亀皮膚科の前にいた。あまりのかゆさに、あしが必死でじたばた跳ねて、いつのまにかここまで来たのだった。皮膚科は大賑わいで、入りきれないかえるが玄関にたむろしていた。かえるさんは256番だった。256かえるも待つ間に死んでしまうかもしれない、とかえるさんは思った。かゆさを我慢しようと玄関先をうろうろしている間にも、一匹また一匹と玄関に吸い込まれていった。255番が吸い込まれても、かえるさんはまだ死ななかった。
気がつくと、かえるさんは、金亀皮膚科の前にいた。あまりのかゆさに、あしが必死でじたばた跳ねて、いつのまにかここまで来たのだった。皮膚科は大賑わいで、入りきれないかえるが玄関にたむろしていた。かえるさんは256番だった。256かえるも待つ間に死んでしまうかもしれない、とかえるさんは思った。かゆさを我慢しようと玄関先をうろうろしている間にも、一匹また一匹と玄関に吸い込まれていった。255番が吸い込まれても、かえるさんはまだ死ななかった。
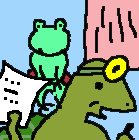 「かえるさん」と名前を呼ばれて診察室に入ると、金亀先生がいた。先生はかえるさんの頭を見るなり「あ、こりゃ月光にやられましたな」と言った。「長いこと月の光を浴びたでしょう、今年は月が強くてかゆいのが流行っているんです。でっぱっているところがかゆいでしょう、それは何度もこすったからです。本当はかえるの面には強いお薬がいいんですが、あなたにはガマの油をあげます。付け根には別に強いお薬をあげます。吸盤でこするとばいきんが広がるのでがまんしてください。はい、けっこうです。」先生はそこまで一気にしゃべった。かえるさんはまだ何かあるような気がして椅子に座っていたが、先生がもう一度「けっこうです」と言ったので、診察室を出た。
「かえるさん」と名前を呼ばれて診察室に入ると、金亀先生がいた。先生はかえるさんの頭を見るなり「あ、こりゃ月光にやられましたな」と言った。「長いこと月の光を浴びたでしょう、今年は月が強くてかゆいのが流行っているんです。でっぱっているところがかゆいでしょう、それは何度もこすったからです。本当はかえるの面には強いお薬がいいんですが、あなたにはガマの油をあげます。付け根には別に強いお薬をあげます。吸盤でこするとばいきんが広がるのでがまんしてください。はい、けっこうです。」先生はそこまで一気にしゃべった。かえるさんはまだ何かあるような気がして椅子に座っていたが、先生がもう一度「けっこうです」と言ったので、診察室を出た。
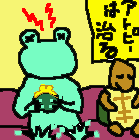 あまりに早かったので、かえるさんはだまされたような気がした。まるで別のところを治されたような気がした。見まわすと、みんな静かに薬をもらうのを待っていた。きっとあれが正しい治し方だったのだ。でも、羽のような花のことも、逆の逆を試したことも、ちょっと違うことも話せなかった。かえるさんは薬を待ちながら、頭を少し前に出してみた。何かになでられたような感じがした。それから猛然とかゆくなってきた。
あまりに早かったので、かえるさんはだまされたような気がした。まるで別のところを治されたような気がした。見まわすと、みんな静かに薬をもらうのを待っていた。きっとあれが正しい治し方だったのだ。でも、羽のような花のことも、逆の逆を試したことも、ちょっと違うことも話せなかった。かえるさんは薬を待ちながら、頭を少し前に出してみた。何かになでられたような感じがした。それから猛然とかゆくなってきた。
第十三話 | 目次
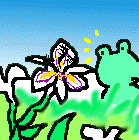 いつになく明るい月夜で、かえるさんはずいぶん遠出をしてしまい、犬上川に戻るころにはすっかり夜が明けていた。川辺を行くと、竹林の縁に沿うように朝露に濡れた白い花が群れていた。いつも見かけるありふれた花だが、徹夜明けのしょぼしょぼした目には、まぶしい色だった。花びらの中にぎざぎざしたものがあって、少しだけかえるのてのひらにも似ているような気もする。かえるさんはこの花に触ったことがなかった。
いつになく明るい月夜で、かえるさんはずいぶん遠出をしてしまい、犬上川に戻るころにはすっかり夜が明けていた。川辺を行くと、竹林の縁に沿うように朝露に濡れた白い花が群れていた。いつも見かけるありふれた花だが、徹夜明けのしょぼしょぼした目には、まぶしい色だった。花びらの中にぎざぎざしたものがあって、少しだけかえるのてのひらにも似ているような気もする。かえるさんはこの花に触ったことがなかった。
 シャガの花の上にのぼってみると、花の内側には、さっき見たぎざぎざがあった。ちょうどサギが羽を広げたような形だった。その羽の下に、かえるさんは頭を差し入れてみた。羽が頭をざわざわとなでた。頭を抜いてみると、またなでられた。入れるときとちょっと違う。入れることと抜くことは逆だが、なでられ方は逆ではない。ちょっと違う。そこで、かえるさんは逆の逆に入れて、逆の逆の逆に抜いてみた。するとやはり、逆の逆の逆のなでられ方は、逆の逆のなでられ方の逆ではなく、ちょっと違うのだった。
シャガの花の上にのぼってみると、花の内側には、さっき見たぎざぎざがあった。ちょうどサギが羽を広げたような形だった。その羽の下に、かえるさんは頭を差し入れてみた。羽が頭をざわざわとなでた。頭を抜いてみると、またなでられた。入れるときとちょっと違う。入れることと抜くことは逆だが、なでられ方は逆ではない。ちょっと違う。そこで、かえるさんは逆の逆に入れて、逆の逆の逆に抜いてみた。するとやはり、逆の逆の逆のなでられ方は、逆の逆のなでられ方の逆ではなく、ちょっと違うのだった。
 何度もちょっと違っているうちに、かえるさんの頭はなんだか乾いて突っ張ってきた。頭だけでなく、あしの付け根のあたりも少し熱っぽくなってきた。そのうち猛烈にかゆくなってきた。こんなかゆさははじめてだった。かえるさんは吸盤で頭をごしごしこすったが、かゆさは増すばかりだった。この花はもしかすると毒なのだろうか。毒をずっと頭にざわざわさせていたのだろうか。こんなにざわざわさせたかえるが、かつていただろうか。これはかえる史上初のかゆさかもしれない。もうお医者にも行けないくらいかゆくなってしまったかもしれない。このままかゆくて死んでしまうかもしれない。
何度もちょっと違っているうちに、かえるさんの頭はなんだか乾いて突っ張ってきた。頭だけでなく、あしの付け根のあたりも少し熱っぽくなってきた。そのうち猛烈にかゆくなってきた。こんなかゆさははじめてだった。かえるさんは吸盤で頭をごしごしこすったが、かゆさは増すばかりだった。この花はもしかすると毒なのだろうか。毒をずっと頭にざわざわさせていたのだろうか。こんなにざわざわさせたかえるが、かつていただろうか。これはかえる史上初のかゆさかもしれない。もうお医者にも行けないくらいかゆくなってしまったかもしれない。このままかゆくて死んでしまうかもしれない。
 気がつくと、かえるさんは、金亀皮膚科の前にいた。あまりのかゆさに、あしが必死でじたばた跳ねて、いつのまにかここまで来たのだった。皮膚科は大賑わいで、入りきれないかえるが玄関にたむろしていた。かえるさんは256番だった。256かえるも待つ間に死んでしまうかもしれない、とかえるさんは思った。かゆさを我慢しようと玄関先をうろうろしている間にも、一匹また一匹と玄関に吸い込まれていった。255番が吸い込まれても、かえるさんはまだ死ななかった。
気がつくと、かえるさんは、金亀皮膚科の前にいた。あまりのかゆさに、あしが必死でじたばた跳ねて、いつのまにかここまで来たのだった。皮膚科は大賑わいで、入りきれないかえるが玄関にたむろしていた。かえるさんは256番だった。256かえるも待つ間に死んでしまうかもしれない、とかえるさんは思った。かゆさを我慢しようと玄関先をうろうろしている間にも、一匹また一匹と玄関に吸い込まれていった。255番が吸い込まれても、かえるさんはまだ死ななかった。
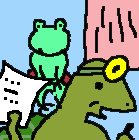 「かえるさん」と名前を呼ばれて診察室に入ると、金亀先生がいた。先生はかえるさんの頭を見るなり「あ、こりゃ月光にやられましたな」と言った。「長いこと月の光を浴びたでしょう、今年は月が強くてかゆいのが流行っているんです。でっぱっているところがかゆいでしょう、それは何度もこすったからです。本当はかえるの面には強いお薬がいいんですが、あなたにはガマの油をあげます。付け根には別に強いお薬をあげます。吸盤でこするとばいきんが広がるのでがまんしてください。はい、けっこうです。」先生はそこまで一気にしゃべった。かえるさんはまだ何かあるような気がして椅子に座っていたが、先生がもう一度「けっこうです」と言ったので、診察室を出た。
「かえるさん」と名前を呼ばれて診察室に入ると、金亀先生がいた。先生はかえるさんの頭を見るなり「あ、こりゃ月光にやられましたな」と言った。「長いこと月の光を浴びたでしょう、今年は月が強くてかゆいのが流行っているんです。でっぱっているところがかゆいでしょう、それは何度もこすったからです。本当はかえるの面には強いお薬がいいんですが、あなたにはガマの油をあげます。付け根には別に強いお薬をあげます。吸盤でこするとばいきんが広がるのでがまんしてください。はい、けっこうです。」先生はそこまで一気にしゃべった。かえるさんはまだ何かあるような気がして椅子に座っていたが、先生がもう一度「けっこうです」と言ったので、診察室を出た。
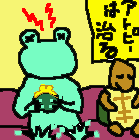 あまりに早かったので、かえるさんはだまされたような気がした。まるで別のところを治されたような気がした。見まわすと、みんな静かに薬をもらうのを待っていた。きっとあれが正しい治し方だったのだ。でも、羽のような花のことも、逆の逆を試したことも、ちょっと違うことも話せなかった。かえるさんは薬を待ちながら、頭を少し前に出してみた。何かになでられたような感じがした。それから猛然とかゆくなってきた。
あまりに早かったので、かえるさんはだまされたような気がした。まるで別のところを治されたような気がした。見まわすと、みんな静かに薬をもらうのを待っていた。きっとあれが正しい治し方だったのだ。でも、羽のような花のことも、逆の逆を試したことも、ちょっと違うことも話せなかった。かえるさんは薬を待ちながら、頭を少し前に出してみた。何かになでられたような感じがした。それから猛然とかゆくなってきた。