 ドルーピーが現れ、音楽は思い出そうとしても忘れられない
ドルーピーが現れ、音楽は思い出そうとしても忘れられない
まずは重箱の隅クイズ。
「Northwest Hounded Police (迷探偵ドルーピーの大追跡)」
で、山小屋に逃げ込んだ狼が閉める扉はいくつ?
・・・
正解:8つ
木板の扉
網戸
空色の扉
飾り窓
鉄扉(鋲付き)
木の柵
金庫扉(ダイヤル付き)
重い木の扉(鍵付き)
ドルーピーから逃げてきた狼が、念を入れまくって、ドアを次々閉めていくシーンだ。狼がバーンと扉を閉める時、ご丁寧にもそれぞれ扉の材質に合わせて、効果音が少しずつ変えてある。閉まる音の直前に刀を振るような「ヒュッ」という音が入っているのがまた気持ちがいい。世界中の扉を閉めて回りたくなる。
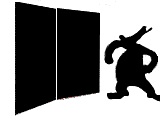 この「ヒュッ」という音は、音質からすると扉がびゅんとスウィングする音のようだけど、じつは音の出るタイミングは狼が扉を閉めようとして上半身をぐっとかがめ、腰をためるあたりに同期している。音効さん、狼に合わせて体を動かしてたんじゃないだろうか。だから、これは狼の体の音なのだ。もちろん体からそんな音がするはずはないが、マンガだからこれでいいのだ。
この「ヒュッ」という音は、音質からすると扉がびゅんとスウィングする音のようだけど、じつは音の出るタイミングは狼が扉を閉めようとして上半身をぐっとかがめ、腰をためるあたりに同期している。音効さん、狼に合わせて体を動かしてたんじゃないだろうか。だから、これは狼の体の音なのだ。もちろん体からそんな音がするはずはないが、マンガだからこれでいいのだ。
この種の、むやみにむやみを上塗りしたような表現は、テックス・アヴェリーの特徴だとよく言われる。特にこの「迷探偵ドルーピーの大追跡」は、高すぎる山、びっしり並んだ飛行機の計器、あり得ない速度と移動距離、などなど「何をそこまで」の連続と言っていい。
では、こうした「むやみさ」を、音で表現するにはどうすればいいか?
まず考えつくのは「大きな音を出す」「何度も音を出す」という方法。つまり、音量や音数を増やして「量」を表すわけだ。確かにこういう方法はよく取られてはいる。
しかし、それだけならじきに飽きが来る。バンドがひたすらフォルテでがなり立ててるだけなら、テックス・アヴェリーの作品はあそこまでおもしろくはならないだろう。
ここでちょっと考えてみよう。
「むやみ」とは何か?
それは単に「量が多いこと」ではない。
箱いっぱいのパチンコ球を見るとうれしいが、むやみだとは思わない。
「むやみ」だなあ、と感じるとき、
そこには、何かが失われている気がする。
頭の中で「むやみでない状態」を探そうとする
つまり「むやみ」とは、
「むやみでないこと」とともにその姿を表す。
「むやみ」は単独では定義できない。
たとえば「度を越すさま」(岩波国語辞典)と、「度」とともに定義される。
ぼくはテックス・アヴェリーの「むやみ」を次のように定義しておきたい。
「あるべき質が失われていること」。
さらに
「それにしても、あるべき質が何だったか忘れてしまったこと」。
さらにさらに
「忘れようにも思い出せない」。
さらにさらにさらに
「思い出したくても忘れられない」。
さて、具体的に行こう。
狼は8つの扉を念入りに閉めた後、振り返ると、そこに追っ手のドルーピーがいるのを見て全身真っ白になる。で、8つの扉をいちいち全部開けていく。最後の扉を開けるとまたしても、そこにはドルーピーがいる。
では、このシーンで音はどのようについているか?
 扉を閉めたときが効果音だったのに対し、開けるときは楽音だ。
扉を閉めたときが効果音だったのに対し、開けるときは楽音だ。
1つの扉を開けるごとにバイオリンとビオラがフォルテで和音をひとつ奏でる。扉が開くに従って音程がずんずん上がる。最後の8つめの扉を開くとそこにはまたしてもドルーピーがいる。この間、約3秒足らず。
閉めた時の音に対して、開けたときの音は、質の変化を失っている。まず、扉を閉めたときに効果音にあった、材質に見合った音質の変化。開けるときは、どの扉も同じ音色で演奏される。さらに、音程の変化も均一だ。最後のドルーピーが現れる扉を除いて、和音はホールトーン・スケールで上昇する。ホールトーン、つまり、扉と扉の間の音程差は一音に保たれている。音楽は、さっきまであったはずの扉どうしの質の違いを忘れてしまった。忘れさせたのはドルーピーだ。
つまり、この山小屋の扉ギャグでは、音の論理によって、あるべき質を忘れるという演出がなされているのだ。
またしてもドルーピーを見てしまった狼は扉をバタンとしめる。木の扉の音。音は一度だけだ。8つあったはずの扉は、ドルーピーの前でただの一枚の扉に成り下がった。かくして量は質を失い、悪夢のような追跡劇が始まる。陸海空、世界のすべての場所で、ドルーピーは狼から質を剥奪していく。にもかかわらず狼がなぜ走るのか、それは思い出したくても忘れられない。
狼が腰をためる「ヒュッ」という音と、狼がタクシーを飛ばして北半球を横断するときの音を思い出すと、ぼくは体がうずうずする。体からそんな音がしそうな気がする。タクシーは走り出すとき、ちょっと後ろに身を引いて「腰をためる」。車がそんなことをするわけはないが、マンガだからこれでいいのだ。
(98.03.20)

to Cartoon Music! contents

 ドルーピーが現れ、音楽は思い出そうとしても忘れられない
ドルーピーが現れ、音楽は思い出そうとしても忘れられない
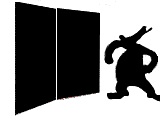 この「ヒュッ」という音は、音質からすると扉がびゅんとスウィングする音のようだけど、じつは音の出るタイミングは狼が扉を閉めようとして上半身をぐっとかがめ、腰をためるあたりに同期している。音効さん、狼に合わせて体を動かしてたんじゃないだろうか。だから、これは狼の体の音なのだ。もちろん体からそんな音がするはずはないが、マンガだからこれでいいのだ。
この「ヒュッ」という音は、音質からすると扉がびゅんとスウィングする音のようだけど、じつは音の出るタイミングは狼が扉を閉めようとして上半身をぐっとかがめ、腰をためるあたりに同期している。音効さん、狼に合わせて体を動かしてたんじゃないだろうか。だから、これは狼の体の音なのだ。もちろん体からそんな音がするはずはないが、マンガだからこれでいいのだ。 扉を閉めたときが効果音だったのに対し、開けるときは楽音だ。
扉を閉めたときが効果音だったのに対し、開けるときは楽音だ。