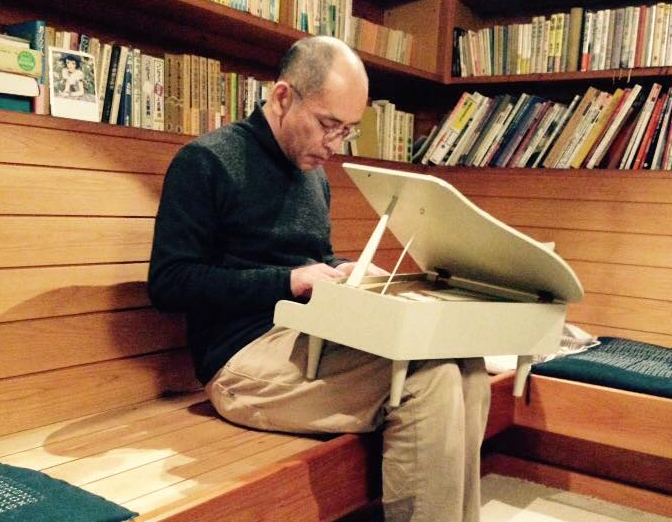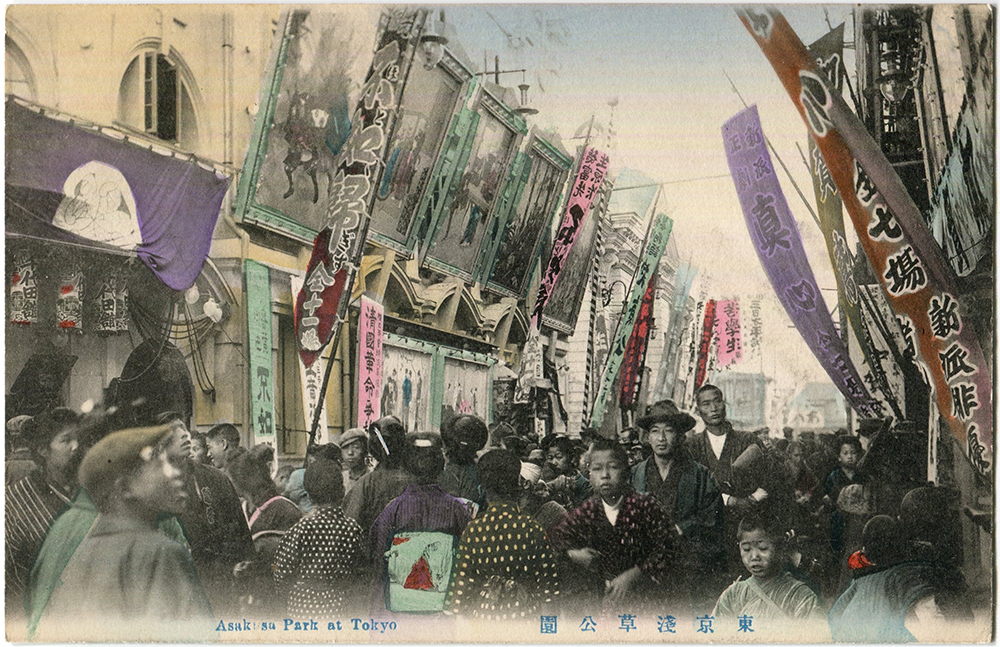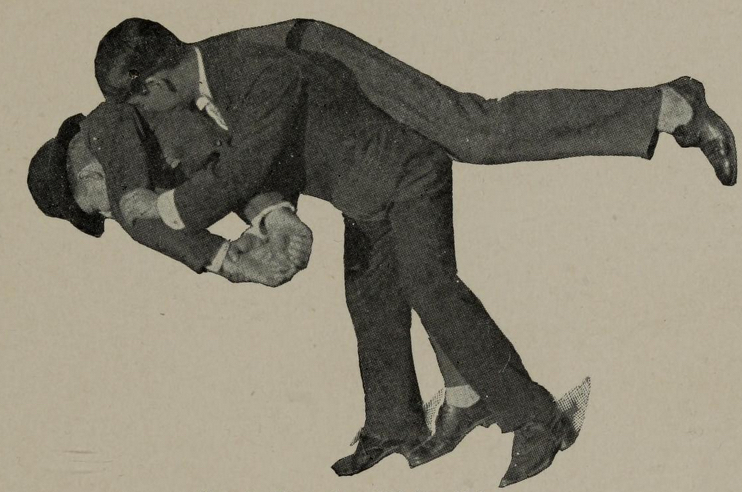このところ、『CHITENの近現代語』『光のない』そして今回の『駆込ミ訴ヘ』を見て、わたしにとっての「地点」の劇はますますはっきり像を結んできている。それは、短く言えば、「代名詞句の劇」ということだ。ただ、代名詞句がキーになっているというだけではない。代名詞句によって、観客と演じ手の立場をがらりと変え、それまで積み上げてきた会話をがらりと別物に変換してしまう。
『駆込ミ訴ヘ』では、それは、「あの人」であり「あなた」であり「あいつ」だ。
——-以下、内容に触れています。これから観たい方は見終わってからどうぞ——
・
・
・
・
・
・
・
今回の『駆込ミ訴ヘ』は、原作を読んでから観た。劇で用いられることばはすべて原作のものだったが、原作を読んだときとはまるで違う感覚を引き起こされた。
原作の『駆込ミ訴ヘ』は、「申し上げます。申し上げます。旦那さま。」という声から始まる。題名を裏付けるように、駆け込んできた1人の男が「旦那さま」に訴えるかのように始まるのだ。
ところが、地点の劇の始まりはちょっと違う。まず冒頭から5人の登場人物が、あたかもマラソンの練習でもしているかのように、前後しながら舞台上で駆けている。5人は常に観客の方を向いており、お互いにことばを交わしあうことなく、語る細胞のように離合集散する。彼らのことばは掛け声をかけたり奇声を発したりしながらあちこち重なっており、最初の「申し上げます。旦那様。」という文言は言ったのか言われなかったのかはっきりと聞き取れない。気がつくと、「あの人は、酷い。酷い。」と、語りはもう、旦那さまをすっとばして「あの人」の話を始めている。
観客はしばし「あの人」の話につきあわされる。おかしなことだ。これは「訴え」なのに。
「あの人」ということばは、聞き手を待たせる。「あの」ということばは、話し手と聞き手を非対称にする。「この」と言われればそこに注意を向ければいいし、「その」と呼ばれたら過去の会話を探せばよい。けれど、「あの」と語り手が呼ぶならば、聞き手は、語り手がその「あの」を思い出すまで待つよりほかない。聞き手は、訴えられているというよりは、待たされているのだ。
語りには、「あの人」という呼称とは別にもう一つ、聞き手を揺らす装置が仕組まれている。それは語尾変化だ。語りは、「です」と報告をするように丁寧語を使うかと思えば、「だ」と独白するように断定する。「あの人」を想起しようとして報告と独白の間で揺れる語りを聞きながら、聞き手である観客はただ壁パスの壁よろしく、語り手が思い出すための壁にさせられるかのようだ。
この、観客にとってもやもやとした時間が、突然、変化したように思えたのは、安部聡子が「私はあなたを愛しています」といったときだった。突然、語りが軽くなった。
わたしはあなたをあいしています。あちこち屈曲するイントネーション。傀儡のように上半身をこつ、こつと倒しながら(しかも駆けながら)安部聡子が語るその台詞には、「愛しています」ということばの素直さも陳腐さも響いていない。そのかわりに、その軽い語りの中で浮き出しているのは、「あなた」という二人称の響きだ。これは告白だ。
告白なら、もっと重いはずだ。しかしこの告白は軽い。「あ↑な↓たはわ↑た↓しをあい『し』ています」。聞き手にその内容を聞かせるためとは到底思えない、変形されたことば。ことばのイントネーションだけを届けるようなことば。「あなた」は観客ではない。語り手はまるで観客のことなどお構いなしに、頭の中でありありと「あなた」を想念している。もはや聞き手のわたしは「あの人」を待つ必要がなくなった。待たされる役から離れて軽くなり、いまや「あなた」に耽溺する語り手たちの目撃者となっている。
この軽さには驚いた。
あとで、原作のこの箇所を読み返して、二度驚いてしまった。
一度、あの人が、春の海辺をぶらぶら歩きながら、ふと、私の名を呼び、「おまえにも、お世話になるね。おまえの寂しさは、わかっている。けれども、そんなにいつも不機嫌な顔をしていては、いけない。寂しいときに、寂しそうな面容《おももち》をするのは、それは偽善者のすることなのだ。寂しさを人にわかって貰おうとして、ことさらに顔色を変えて見せているだけなのだ。まことに神を信じているならば、おまえは、寂しい時でも素知らぬ振りして顔を綺麗に洗い、頭に膏《あぶら》を塗り、微笑《ほほえ》んでいなさるがよい。わからないかね。寂しさを、人にわかって貰わなくても、どこか眼に見えないところにいるお前の誠の父だけが、わかっていて下さったなら、それでよいではないか。そうではないかね。寂しさは、誰にだって在るのだよ」そうおっしゃってくれて、私はそれを聞いてなぜだか声出して泣きたくなり、いいえ、私は天の父にわかって戴かなくても、また世間の者に知られなくても、ただ、あなたお一人さえ、おわかりになっていて下さったら、それでもう、よいのです。私はあなたを愛しています。(『駆込ミ訴ヘ』)
原作でも、このとき語り手はまさに、「あの人」のことばを想起した直後に、「あの人」を「あなた」と呼び変えている。しかし読んだときには、このさりげない変化に正直気づかなかった。そして原作では、この語り口の変化は「軽さ」として感じられるどころか、むしろ想念が真に迫っていくように響いている。地点の劇を観て、初めて、「あなた」という呼びかけから「軽さ」が生じうることに気づいたのだ。
語り手は、「あの人」の行為をただ評するのではなく、「あの人」が自分に向けて語ったことばを思いだそうとして、もはや「あの人」を「あの人」と呼ぶ距離を保てなくなっている。「あの人」のことばに応えるように、語り手は「あの人」を「あなた」と呼ばざるをえない。そのような、「あの人」と「私」の距離の変化が露頭のように剥き出しになったのが「わたしはあなたをあいしています」だった。「あなた」のほうが語り手に近く切実なはずなのだが、観客にとっては「あなた」の方が軽い。それはたぶん、もう待たなくてよくなったからだ。「あの人」がどのような人であるか、その報告を待つことから解放される軽さは、劇の発明だ。(「ペテロも来い、ヤコブも来い、ヨハネも来い、みんな来い。」と唱えるときの、安部聡子による猩々寺のたぬきばやしのような韻律の軽さが忘れられないのだけれど、これも「あなた」の軽さによるものだ)。
劇中、オープンリールのテープレコーダーを持った男が歌いながらやってきて、この劇で繰り返される「得賞歌」を生の声で歌う。「ダビデの子」を称える歌。それは、キリストのエルサレム入場を迎える讃美歌だ。
日本の表彰式で決まって流される『得賞歌』は、歴史的にいくつものレイヤーを持っている。まず、『得賞歌』はもともと、ヘンデルのオラトリオ『ユダス・マカベウス』の中で歌われる『見よ勇者は帰る』というタイトルである。(オラトリオのタイトルは「ユダ」を、『見よ勇者は帰る』というタイトルは『走れメロス』を想起させる)。さらに、それは19世紀に「よろこびやたたえよや」というイエスのエルサレム入場を迎える讃美歌となった。讃美歌は、原作の『駆込ミ訴ヘ』で語り手が告げる「私たちは愈愈あこがれのエルサレムに向い、出発いたしました。」というエルサレム入場の場面を歌っており、歌い手の入場は、あたかも想念されている「あの人」の入場を先導するようだ。
先導するようだ、と書いたけれど、歌い手のあとから「あの人」がついてくるわけではない。そのかわりに、歌い手はオープンリールのテープレコーダーを携えてきており、そこでは陰陽師の用いるヒトガタのような紙の十字架が、くるくる回っているのである。観客にとっての「あの人」、語り手の想念の中だけにあって観客には手の届かない記号のような「あの人」よろしく、ぺらぺらの紙の十字架は、周回することをやめない駆けっこのように回り続けている。まるで、「あの人」を待つことの空しさと終わりのなさを示すように。
劇の後半、観客の立場は、再び変化させられる。
それは窪田史恵が、「旦那さま」ということばを高らかに発したときだった。
「旦那さま」ということばを聞いて、そこまで「あの人」と「あなた」の往復にはまっていたわたしの頭はにわかに冴えた。劇を観ているうちに、わたしはこれが「訴え」だということをすっかり忘却の彼方においていた。それが「旦那さま」ということばで急に思い出された。そうそう、この語りのすべては「訴え」だった。「あなた」によって軽くなった告白は、「旦那さま」という相手を得てまた重くなる。「あの人」は、もはや「あいつ」とまでにののしられる。これは「訴え」が諄々と行われる劇ではない。告白の情動が、訴えへと形を為していく、その時間をそっくりそのまま、劇にしたものだ。語りの形式が情念を駆動し、訴えを産み出し、観客を産み出していく。
訴えはさらに緊張を帯びる。語り手は、訴えの報酬である金を受け取ろうとして思わず、床にたたきつける。「金が欲しくて訴え出たのでは無いんだ。ひっこめろ!」硬貨のばらばらと散る、硬い音とともに、訴えが一瞬、独白へと引き戻る。ここにはパンも血もない。訴えの対象は血肉を持たない。乾いた金の音だけがある。「いいえ、ごめんなさい、いただきましょう」。語り手は、また下卑た丁寧語を発して、いったんはたたきつけた金を受け取る。訴えがいよいよ押し詰まったとき、語り手は自らの名前を名乗る。「はい、有難う存じます。はい、はい。申しおくれました。」と丁寧なことばづかいのあと「旦那さま」に対して発せられるその名前は、原作では訴えの終わりにぽつんと置かれている。
イスカリオテのユダ。
原作では、その名前は、訴えに釣り合う重みを持って、物語の終結に置かれる。その名前は、物語では唱えられないもう一つの名前、イエス・キリストのことを想起させる。
しかし、小林洋平はこの名前を、「ユ、だー」と、あたかも断定の助動詞を口にするように発音する。まるで下卑たバカ丁寧な報告から、独白へととつぜん想念の向きを変えるかのように。そして同時に、旦那さまという報告の相手を消去し、観客へととつぜん想念の向きを変えるかのように。ユダとイエス・キリストを想起させる代わりに、舞台と客席の関係を想起させるかのように。
5人の語り手は、今やへっへと笑い、訴え手であることを辞めて、語りのオブジェのように突っ立っている。傾斜のついた高い天井のある舞台でぽつんと立っている5人は、埋まらない空間を、巨大な空白を空白のまま、さし示すかのようだ。オープンリールを抱えた歌手が「あの人」の入場を称える歌を歌っている。紙の十字架が回っている。「あの人」はいない。ここに「あの人」がいないからこそ、「あの人」を語るこの独白は訴えになる。訴えは訴え先を必要としている。それはあなただ観客さま、と、終わりのことばはわたしのことを言いあてるようだ。「ユ、だー」。